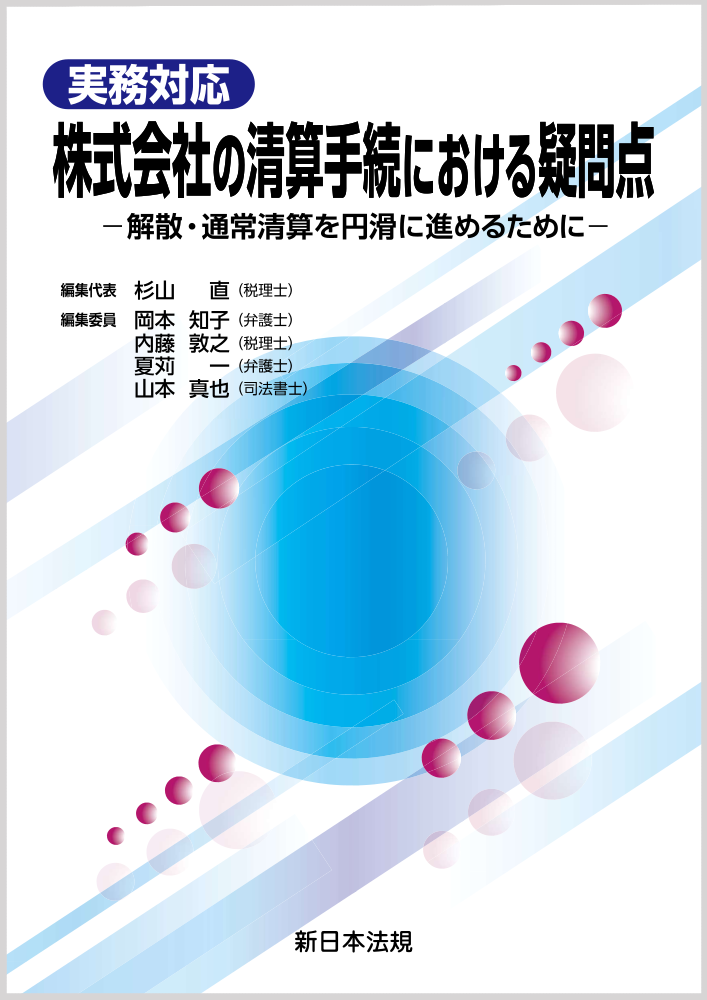一般2024年11月14日 スポーツ団体による適正な調査・処分とスポーツ仲裁 執筆者:多賀啓

1. スポーツ団体は、所属・登録する選手や指導者、役職員等に対して懲戒処分を下すことがあります。
懲戒処分は処分対象者のスポーツをする権利を制限するものですから、中央競技団体か、中央競技団体以外のスポーツ団体(一般スポーツ団体)かに関わらず、懲戒処分を下す場合には、必要な規程の整備、適切な証拠に基づく事実認定、規程に沿った適正な手続の進行、基準を踏まえた処分内容の決定等、厳格な調査と手続が求められます。これらを欠いた場合、当該懲戒処分決定に対してスポーツ仲裁を申し立てられ、決定が取り消されるという事態に発展してしまいます。
懲戒処分は処分対象者のスポーツをする権利を制限するものですから、中央競技団体か、中央競技団体以外のスポーツ団体(一般スポーツ団体)かに関わらず、懲戒処分を下す場合には、必要な規程の整備、適切な証拠に基づく事実認定、規程に沿った適正な手続の進行、基準を踏まえた処分内容の決定等、厳格な調査と手続が求められます。これらを欠いた場合、当該懲戒処分決定に対してスポーツ仲裁を申し立てられ、決定が取り消されるという事態に発展してしまいます。
2. スポーツ団体ガバナンスコード<中央競技団体向け>原則101は、中央競技団体において「懲罰制度を構築すべきである。」とし、(1)懲罰制度における禁止行為、処分対象者、処分の内容及び処分に至るまでの手続を定め、周知すること、(2)処分審査を行う者は、中立性及び専門性を有すること、を求めています。これらは、各団体が懲罰制度、具体的には倫理規程や懲罰規程(処分規程)を整備する際の指針となります。
3. 実際の調査にあたって重要なことは、客観的な証拠を収集すること、また、関係者に対しヒアリングを実施して各人が認識している事実関係を詳細に聴取し、それを証拠化しておくことです。JSAA-AP-2016-001号仲裁事案2では、スポーツ団体が不利益処分を行う場合には、その処分の根拠となる事実についてはスポーツ団体が立証責任を負うとされています。すなわち、懲戒処分決定が争われ、スポーツ仲裁の場で検証が行われる場合、スポーツ団体が証拠をもって事実認定に誤りがないことを主張立証しなければならないということになります。
4. 手続の進行にあたり、手続に瑕疵や遺漏があった場合には、そのことを理由にスポーツ仲裁において懲戒処分決定が取り消されることもあります。例えば、JSAA-AP-2016-006号仲裁事案3等では、スポーツ団体が不利益処分を行う際には、行政手続法等が求めるものと同等の弁明の機会を付与することが不可欠であると解すべきで、具体的な手続として懲戒の対象となる事実の告知、及び、弁解聴取の機会の確保の2点が必須とされています。
また、JSAA-AP-2017-001号仲裁事案4では、不利益処分においては、被処分者が防御を行える程度に弁明の機会を付与すること、処分の対象となる事実を確定し、処分決定手続きを経て、処分の対象となる事実の告知を行い、処分が相当であることが不可欠の要件であることが明示されました。もっとも、同事案においては、処分対象事実が特定されていないことを理由に、手続に瑕疵があるとして懲戒処分決定が取り消されました。
こうした手続の瑕疵を指摘されないためには、スポーツ団体ガバナンスコード<中央競技団体向け>原則10の要請を踏まえた規程を整備し、同規程に沿った手続を厳格に履践していくことが必要となります。
また、JSAA-AP-2017-001号仲裁事案4では、不利益処分においては、被処分者が防御を行える程度に弁明の機会を付与すること、処分の対象となる事実を確定し、処分決定手続きを経て、処分の対象となる事実の告知を行い、処分が相当であることが不可欠の要件であることが明示されました。もっとも、同事案においては、処分対象事実が特定されていないことを理由に、手続に瑕疵があるとして懲戒処分決定が取り消されました。
こうした手続の瑕疵を指摘されないためには、スポーツ団体ガバナンスコード<中央競技団体向け>原則10の要請を踏まえた規程を整備し、同規程に沿った手続を厳格に履践していくことが必要となります。
5. また、処分内容、すなわちどの程度重い処分にするかという点については、あらかじめ処分基準を決めておくことや、過去の同種事例との均衡を保つことが望まれます。
6. 最後に、一連の調査・処分にあたり、時間がかかり過ぎることも大きな問題です。適切な証拠に基づく事実認定を行い、手続に瑕疵もなく、処分内容も妥当な結論に至ったとしても、あまりに時間がかかり過ぎれば、処分対象者だけでなく、他のステークホルダー(例えば被害者等)の納得感も失われてしまいます。もちろん、調査・処分手続には一定の期間を要しますが、できる限り迅速に手続を進行することは常に意識しなければなりません。
7. スポーツ団体にとって、懲戒処分手続は「当然にやらなければならないこと」の一つです。特に中央競技団体は、冒頭で述べたとおりスポーツ団体ガバナンスコード<中央競技団体向け>原則10を遵守することが求められています。
本稿で概観したように、適正な調査・処分の実現は容易いものとはいえませんが、仕組み作りを含め、スポーツ団体はその実現に向けて進み続ける必要があります。
本稿で概観したように、適正な調査・処分の実現は容易いものとはいえませんが、仕組み作りを含め、スポーツ団体はその実現に向けて進み続ける必要があります。
(2024年11月執筆)
(本記事の内容に関する個別のお問い合わせにはお答えすることはできません。)
人気記事
人気商品
執筆者

多賀 啓たが ひろむ
弁護士
略歴・経歴
パークス法律事務所・弁護士
東京都立大学法科大学院・講師
尚美学園大学スポーツマネジメント学部・講師
学歴
2010年 首都大学東京都市教養学部法学系(現 東京都立大学法学部)卒業
2012年 首都大学東京法科大学院(現 東京都立大学法科大学院)修了
取扱分野
スポーツ法務、企業・団体法務、訴訟・仲裁その他紛争解決
著書
『スポーツの法律相談』(共著)青林書院(2017年3月)
『スポーツ事故対策マニュアル』(共著)体育施設出版(2017年7月)
『Q&Aでわかる アンチ・ドーピングの基本』(編著)同文館出版(2018年11月)
『法務担当者のための契約実務ハンドブック』(共著)商事法務(2019年3月)
執筆者の記事
執筆者の書籍
この記事に関連するキーワード
-

-

団体向け研修会開催を
ご検討の方へ弁護士会、税理士会、法人会ほか団体の研修会をご検討の際は、是非、新日本法規にご相談ください。講師をはじめ、事業に合わせて最適な研修会を企画・提案いたします。
研修会開催支援サービス -

Copyright (C) 2019
SHINNIPPON-HOKI PUBLISHING CO.,LTD.