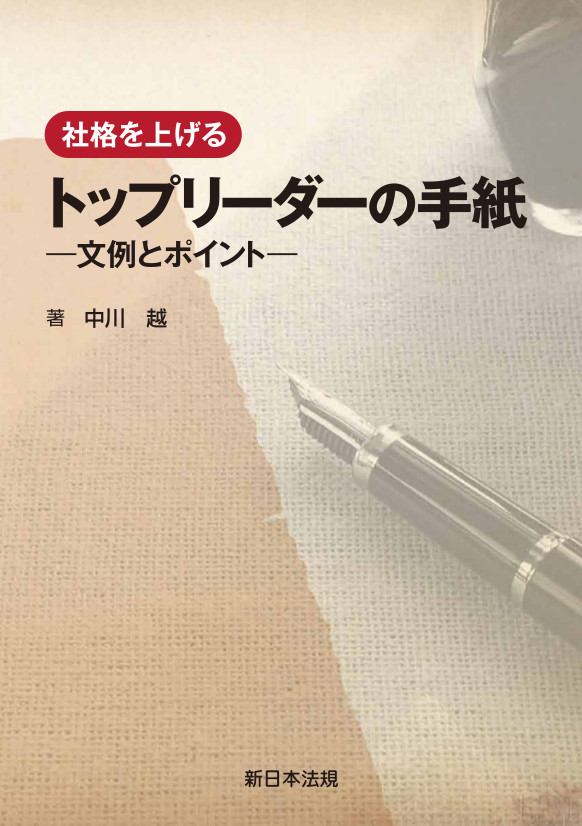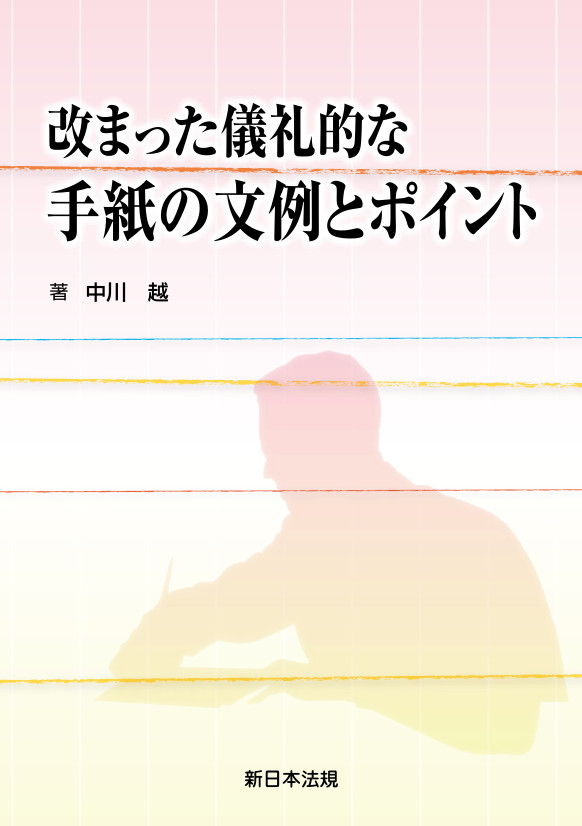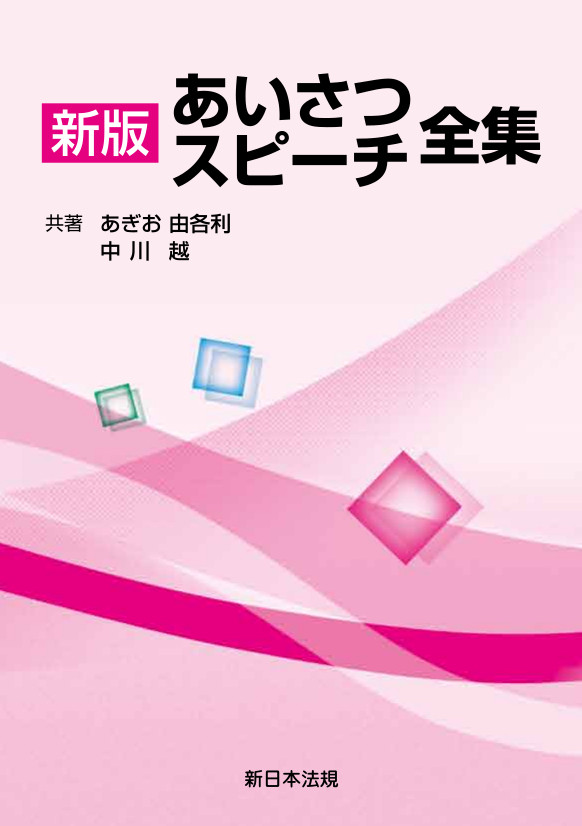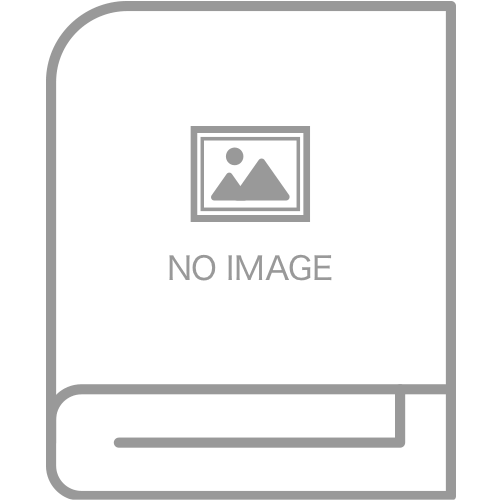一般2025年05月14日 契約に関わる文豪書簡(1)―法律の条文のような諭吉・らいてふの書簡―(法苑WEB連載第16回)執筆者:中川越 法苑WEB

●愛息に託した福沢諭吉の条文
法律といえば、条文という形式が思い出されます。そこで今回は、条文化された文豪書簡についてのお話を、二つご紹介します。
先ず、このほど長らく占めていた一万円札の座を、渋沢栄一に譲った福沢諭吉が、留学する愛息二人に託した巻紙の書簡からです。
明治の初め、日本の人口がまだ3000万人ぐらいだった頃、300万部の大ベストセラーとなった本があります。当時の日本人の10人に1人が読んだのは、福沢諭吉の『学問のすすめ』です。現在の総人口は約1億2000万人。今なら1200万部のビリオンセラーです。
福沢諭吉は、江戸時代末の天保5(1835)年に、豊前中津藩(大分県)の下級武士の子として生れ、大坂で蘭学者緒方洪庵に学び、蘭学塾(後の慶応義塾)を開きます。その後英語を独修し、32歳とき幕府の遣米使節に同行して咸臨丸で渡米し、以後さらに2回欧米を視察。銀行、郵便、選挙制度、議会制度など、欧米の進んだ社会制度を学び、維新後は下野し、啓蒙思想家、教育家として活躍しました。
そんな諭吉が27歳のときに書いた『学問のすすめ』の有名な書き出しは、次の通りです。
「『天は人の上に人を造らず人の下に人を造らず』と言えり。されば天より人を生ずるには、万人は万人みな同じ位にして、生まれながら貴賤上下の差別なく、万物の霊たる身と心との働きをもって天地の間にあるよろずの物を資り、もって衣食住の用を達し、自由自在、互いに人の妨げをなさずしておのおの安楽にこの世を渡らしめ給うの趣意なり。されども今、広くこの人間世界を見渡すに、かしこき人あり、おろかなる人あり、貧しきもあり、富めるもあり、貴人もあり、下人もありて、その有様雲と泥との相違あるに似たるはなんぞや。」
人間は本来平等で、すべての人は、お互いに人の邪魔をすることなく、この世を楽しく生きることを目的にしているのに、実際は平等ではなく、賢愚、貧富、身分の差がある、と言っています。そして、その差は何によって生れるかを、端的に説きます。文中の『実語教』は庶民向けの教訓書です。
「その次第はなはだ明らかなり。『実語教』に、『人学ばざれば智なし、智なき者は愚人なり』とあり。されば賢人と愚人との別は学ぶと学ばざるとによりてできるものなり。」
すなわち、学問をすすめたのでした。
この理念は、当然、諭吉自らの子供たちにも適用され、明治16(1883)年、19歳の長男一太郎と、17歳の次男捨次郎は、アメリカに留学することになりました。
その際諭吉は、渡航する直前の二人に、留学中の心得を巻紙に記し、二重の封筒に納めて渡しました。こんな内容が、列記されていました。
「一、一太郎ハ農学ト方向ヲ定メタル上ハ、専ラ其業ヲ修メ、且農学ノ理論ヨリモ実際ノ事ニ力ヲ用イ…
一、捨次郎ハ物理学ノ一科ニ志シ、或ハ電気学ナド如何ト思ヘドモ、其辺ハ本人の見込ミニ任スル事。
一、両人共、学問ノ上達ハ第二ノ事トシテ、苟モ身体の健康を傷ウ可カラズ。…」
勉学の方向性のアドバイスだけでなく、健康への留意を優先せよと、優しい親心が垣間見えます。さらに、こんな訓戒まで加えました。
「一、一太郎ハ酒量深キニ非ズシテ寧ロ酔フニ易キモノト云ウ可シ。…幸ニシテ生来尚未ダ飲酒ノ習慣ヲ成サズ、今ニシテ之ヲ禁ズルハ甚ダ容易ナル可ケレバ、断然酒ヲ飲ム勿レ。…学問執行中ニ酒ニ酔ウナドノ事アリテハ、人二軽侮セラレテ、本人ノ不幸ハ無論、父母モ為ニ心ヲ痛マシムルコト少ナカラズ。呉々モ慎シム可キモノナリ。」
酒で失敗しないようにと、老婆心を働かせています。自ら三度も欧米に渡り、彼の地の事情は心得ていたものの、やはり開国間もない日本からの留学生が、どのような処遇を受けるか、心配でならなかったようすがうかがえます。
しかしやはり、近代日本の大きな精神的礎を築いた明治の猛者の一人、福沢諭吉です。我が子を千尋の谷に落とす気概と覚悟も、併せて持ち合わせていたようです。
この心得書の第一項は、次の言葉でした。
一、執行中、日本二如何ナル事変生ズルモ、此方ヨリ父母ノ命ヲ得ルマデハ、帰国スルニ及バズ。父母ノ病気ト聞クモ、狼狽シテ帰ル勿レ。
父が託した条文形式の厳格で力強い心得は、二人によく効いたようです。二人は父の教えをよく守り学問を修め、一太郎はその後、慶応義塾の塾長となり、捨次郎は、諭吉がつくった新聞社、「時事新報社」の社長になりました。
●まさに法律の条文のような平塚らいてふの求愛の書簡
次にご紹介するのは、「元始、女性は太陽であった」という言葉で知られる平塚らいてふの書簡です。
ちなみに元始云々は、らいてふが明治44(1911)年25歳のとき、雑誌青鞜創刊し、その第1号に載せた序文のタイトルです。
らいてふは、明治、大正、昭和にわたり、女性が本来持つべき権利を獲得するために、旧来の理不尽な社会制度や社会的圧力と果敢に戦い続けました。
創刊号の序文には、こんなことが書かれていました。
「元始、女性は実に太陽であった。真正の人であった。
今、女性は月である。他に依って生き、他の光によって輝く病人のような蒼白い顔の月である。
私共は隠されて仕舞った我が太陽を今や取戻さねばならぬ。
『隠れたる我が太陽を、潜める天才を発現せよ、』こは私共の内に向っての不断の叫声、押えがたく消しがたき渇望、一切の雑多な部分的本能の統一せられたる最終の全人格の唯一本能である。」
らいてふのこの大胆な発言は、同時代の進歩的な女性たちの共感を得る一方、男性からは顰蹙を買うことになります。しかし彼女はめげることなく、ラジカルな発言を繰り返しました。
たとえば結婚についても次のように、恋愛結婚を推奨しました。
「私はこの四五年…幾度となく、性的道徳の標準として男女の結合は相互の愛情によらねばならぬこと。結婚の第一若しくは中心要素は恋愛であらねばならぬとを反復して参りました」
では、かく言うらいてふ自身は、どのような結婚をしたのでしょうか。気迫に満ちた社会活動家らしく、「性的道徳の標準」「男女の結合」「結婚の中心的要素」など、いかめしい言葉を駆使する人は、どんな恋をして、どんな結婚をしたのでしょうか。
らいてふは明治45(1912)年26歳のとき、画家志望の21歳の奥村博史に出会い、こう思いました。
「大きな赤ん坊のような、よごれのない青年に対して、かつてどんな異性にも覚えたことのない、つよい関心がその瞬間生まれたのでした」
二人はすぐに恋に落ちますが、結婚に踏み切るためには互いの気持ちを確かめ合う必要がありました。二人が出会った翌年に、まずらいてふが、八か条に及ぶこんな手紙を奥村に出しました。
一、今後ふたりの愛の上にどれ程の困難や面倒なことが起ろうとも、あなたと私と一緒によく堪えるか。ふたりの愛の真実が消えない限りは外的のどんな圧迫がふたりの上に降りかかってこようとも、あなたは私から去らないか。
二、もし私があなたに結婚を要求するものと仮定したら、あなたはこれに何と答えられるか。
三、もし私が最後まで結婚を望まず、寧ろ結婚による男女関係(殊に今日の制度としての)を憎むものとすれば、あなたはこれに対してどういう態度をとられるか。
四、もし私があなたに対して結婚はしないが同棲生活を望むものとすれば、あなたはどうされるか。
五、もし私が結婚も同棲も望まず、最後まで別居してふたりで適当の昼と夜をもつことを望むとすれば、あなたはどうされるか。
六、子供についてあなたはどんな考えをもっていられるか。私に恋愛があり欲望があっても生殖欲がないとすれば、あなたはどうされるか。
… 〔七、八は省略〕 (大正2年8月17日付)
なんともぎこちなく堅苦しい内容です。同棲もしくは結婚の覚悟を確かめるための箇条書きの質問状です。
これに対して奥村は三日後に、各項にていねいに答える手紙を返信しました。
「1,大丈夫。2,しましょう。3,今の制度がどうあろうとも、それはもともと人間が作ったものですからどうでも好いのです。もし結婚が嫌ならこのままでいましょう。4,あなたの言う意味がよく分りません。愛し合うふたりの人間が同棲することがほんとうの意味の結婚というものではないのですか? … 6,ふたりで外を歩いている時にもおわかりでしょうが、わたしはどの子供も(世界中の子供と言いたい)限りなく好きですし、また実際可愛いのです。だから、ましてふたりの子供なら一層そうだろうと思います。…」
この返信をらいてふは、奥村らしく自然で率直なものと感心し、奥村と暮らしを持つことを決めました。契約成立です。二人はその後二人の子供を授かりました。
本来、らいてふが出したような法律の条文や契約書まがいの味気なく興ざめな質問状は、二人の関係を悪化させそうな気もしますが、ここでは功を奏しました。
それは、客観的で事務的な文体を目指しながらも、意図しないあたたかさが文章にこもり、いたいけで切ない願いが見え隠れする愛くるしいラブレターになっていたからだと思われます。
たとえば、「もし私があなたに結婚を要求するものと仮定したら、あなたはこれに何と答えられるか。」は、〈仮にですよ、仮に、万一私が結婚したいなどといってしまったら、どう答えますか? あくまでも仮にの話だけど〉と奥村には聞こえたはずです。おずおずと怯えるらいてふを、奥村は強く抱きしめたくなったのだと思います。
法律の条文形式を、求愛に利したのは、らいてうの前にも後にも、誰一人いないでしょう。
【中川 越 なかがわ・えつ プロフィール】
手紙文化研究家・コラムニスト。東京新聞「文人たちの日々好日」連載中/日本絵手紙協会の「月刊絵手紙」〈手紙のヒント〉」連載中/「月刊日本橋」〈発掘!日本橋逸聞逸事〉連載中/〇主な著書 『すごい言い訳!―漱石の冷や汗、太宰の大ウソ―』(新潮文庫)/『文豪たちの手紙の奥義 ―ラブレターから借金依頼まで―』(新潮文庫)/『夏目漱石の手紙に学ぶ 伝える工夫』(マガジンハウス)/『漱石からの手紙 人生に折り合いをつけるには』(CCCメディアハウス)/『文豪に学ぶ 手紙のことばの選びかた』(東京新聞)/『NHKラジオ深夜便 文豪通信』(河出書房新社)など。
(本記事の内容に関する個別のお問い合わせにはお答えすることはできません。)
法苑WEB 全19記事
- 「始皇帝モノ」は面白い。連載コラムその4 ─応用編⑵『コウラン伝 始皇帝の母』 (前半・1~38話)の紹介─(法苑WEB連載第19回)執筆者:坂和章平
- 私たちが負担した消費税は国に納められているか~インボイス制度からみる消費税のしくみ(前編)(法苑WEB連載第18回)執筆者:深作智行
- 契約に関わる文豪書簡(2)―離縁状できれいに婚姻関係を解消した永井荷風とその妻―(法苑WEB連載第17回)執筆者:中川越
- 契約に関わる文豪書簡(1)―法律の条文のような諭吉・らいてふの書簡―(法苑WEB連載第16回)執筆者:中川越
- 子どもの意見表明の支援は難しい(法苑WEB連載第15回)執筆者:角南和子
- 「始皇帝モノ」は面白い。連載コラムその3 ─応用編⑴『大秦帝国』シリーズ全4作の紹介─(法苑WEB連載第14回)執筆者:坂和章平
- コンダクト・リスクの考え方~他律から自律への転換点~(法苑WEB連載第13回)執筆者:吉森大輔
- 消防法の遡及制度(法苑WEB連載第12回)執筆者:鈴木和男
- 「始皇帝モノ」は面白い。連載コラムその2 ─入門編は『キングダム~戦国の七雄』から─(法苑WEB連載第11回)執筆者:坂和章平
- 株分けもの(法苑WEB連載第10回)執筆者:村上晴彦
- 「始皇帝モノ」は面白い。連載コラムその1 ─『キングダム』シリーズ全4作を楽しもう!─(法苑WEB連載第9回)執筆者:坂和章平
- 小文字の世界(法苑WEB連載第8回)執筆者:田中義幸
- 20年ぶりに「学問のすすめ」を再読して思うこと(法苑WEB連載第7回)執筆者:杉山直
- 今年の賃上げで、実質賃金マイナスを脱却できるか(令和6年の春季労使交渉を振り返る)(法苑WEB連載第6回)執筆者:佐藤純
- ESG法務(法苑WEB連載第5回)執筆者:枝吉経
- これからの交通事故訴訟(法苑WEB連載第4回)執筆者:大島眞一
- 第三の沈黙(法苑WEB連載第3回)執筆者:相場中行
- 憧れのハカランダ(法苑WEB連載第2回)執筆者:佐藤孝史
- 家庭裁判所とデジタル化(法苑WEB連載第1回)執筆者:永井尚子
執筆者

中川 越なかがわ えつ
略歴・経歴
コラムニスト、手紙文化研究家。東京都出身。書籍編集者を経て執筆活動に入る。
主な著書は以下の通り。
「改まった儀礼的な手紙の文例とポイント」(新日本法規出版)
「新版あいさつ・スピーチ全集(共著)」(新日本法規出版)
「気持ちがきちんと伝わる! 手紙の文例・マナー新事典」(朝日新聞出版)
「実例大人の基本手紙書き方大全」(講談社)
「文豪に学ぶ手紙のことばの選びかた」(東京新聞)
「文豪たちの手紙の奥義」(新潮文庫)
「すごい言い訳!―漱石の冷や汗、太宰の大ウソ―」(新潮文庫)
「高等学校国語表現Ⅱ」(第一学習社版)〈中川越「心に響く手紙」が3頁にわたり収載〉
執筆者の記事
執筆者の書籍
関連カテゴリから探す
-

-

団体向け研修会開催を
ご検討の方へ弁護士会、税理士会、法人会ほか団体の研修会をご検討の際は、是非、新日本法規にご相談ください。講師をはじめ、事業に合わせて最適な研修会を企画・提案いたします。
研修会開催支援サービス -