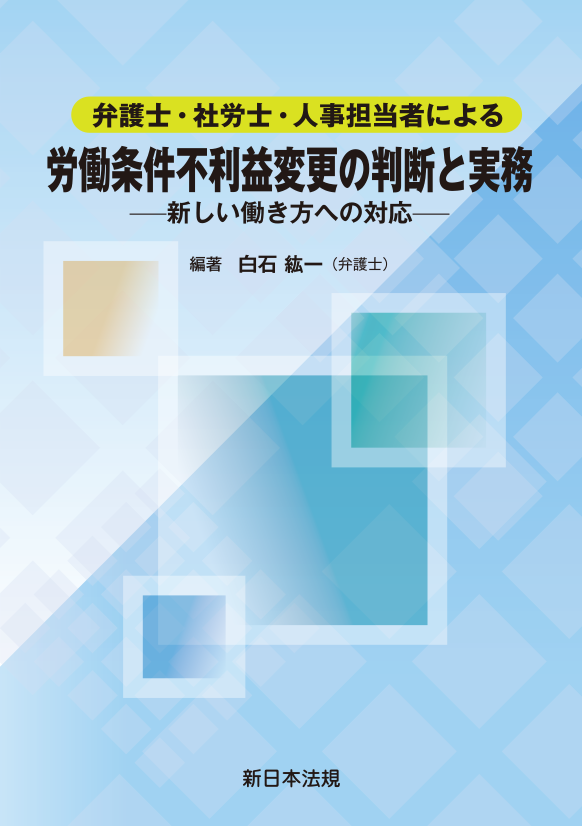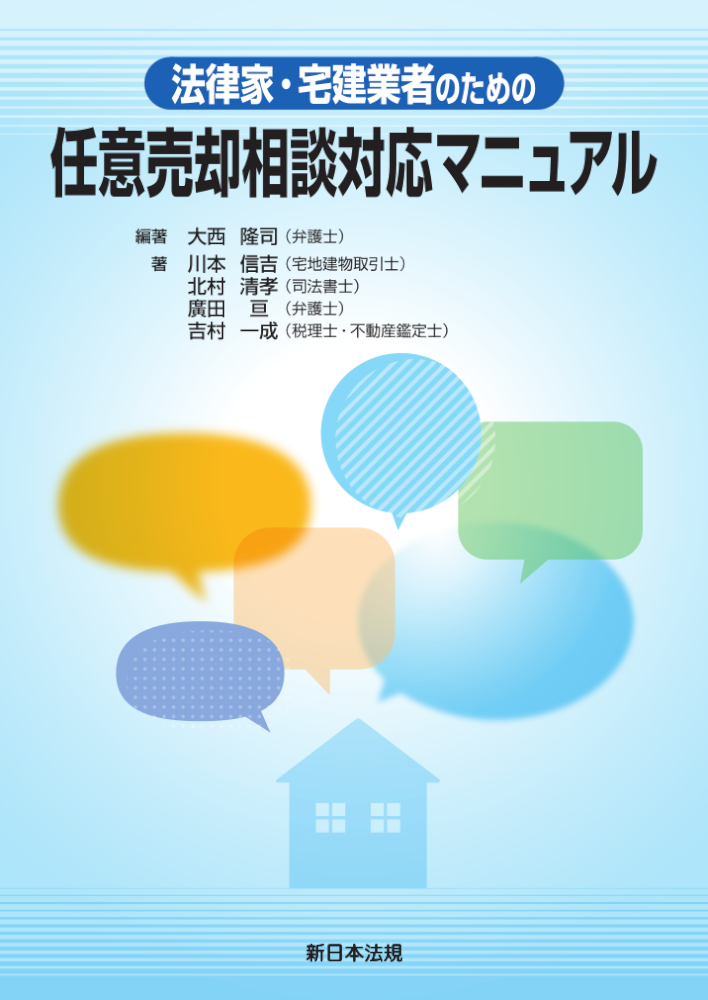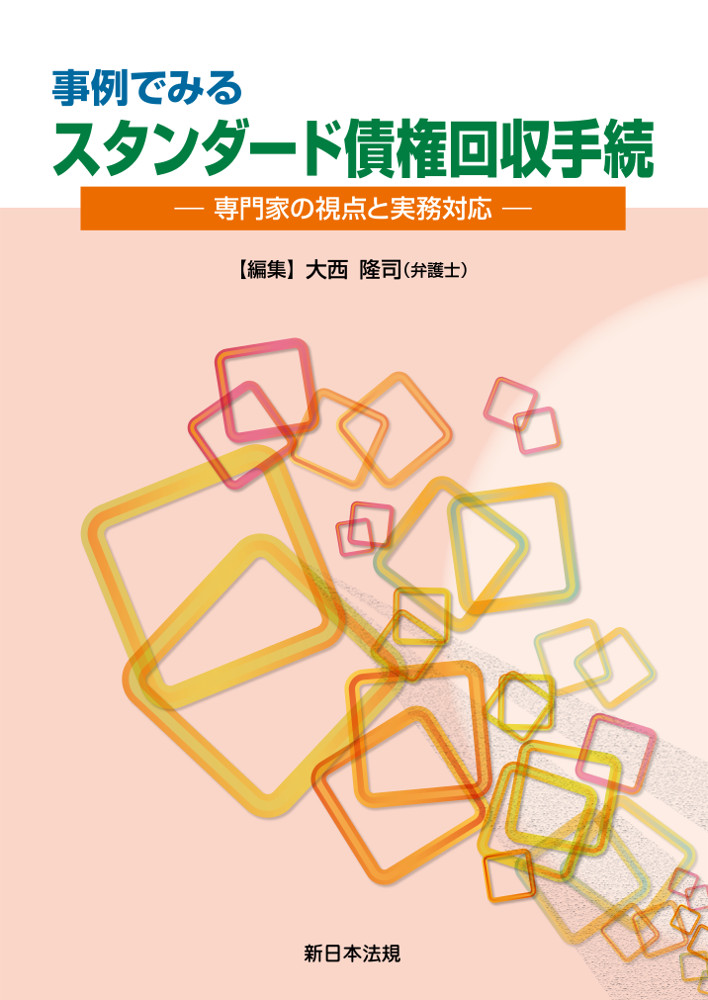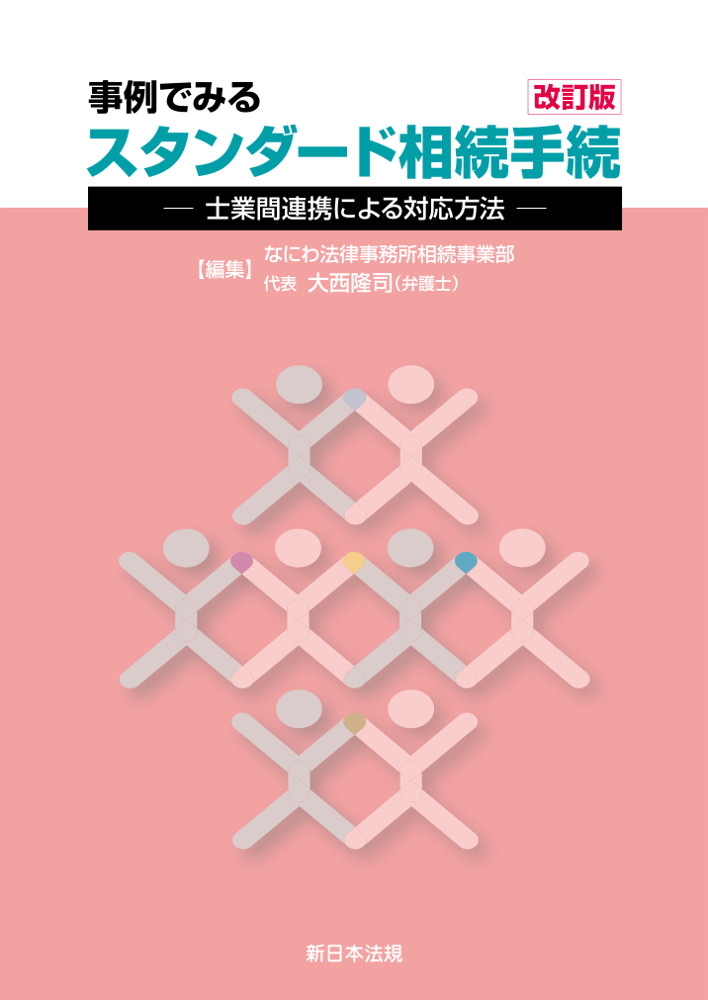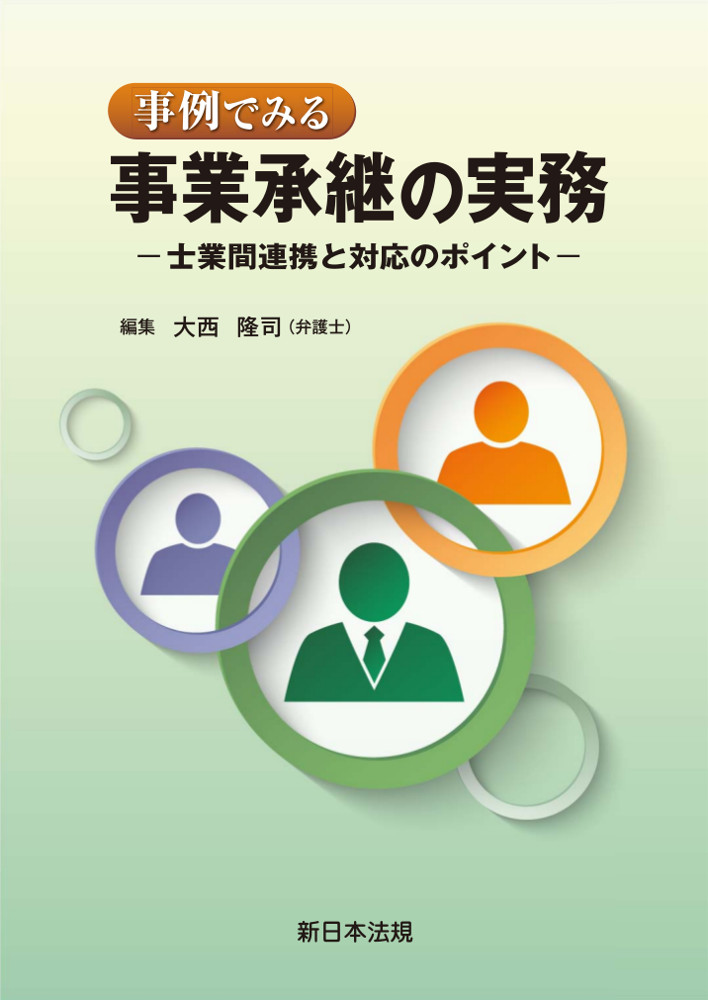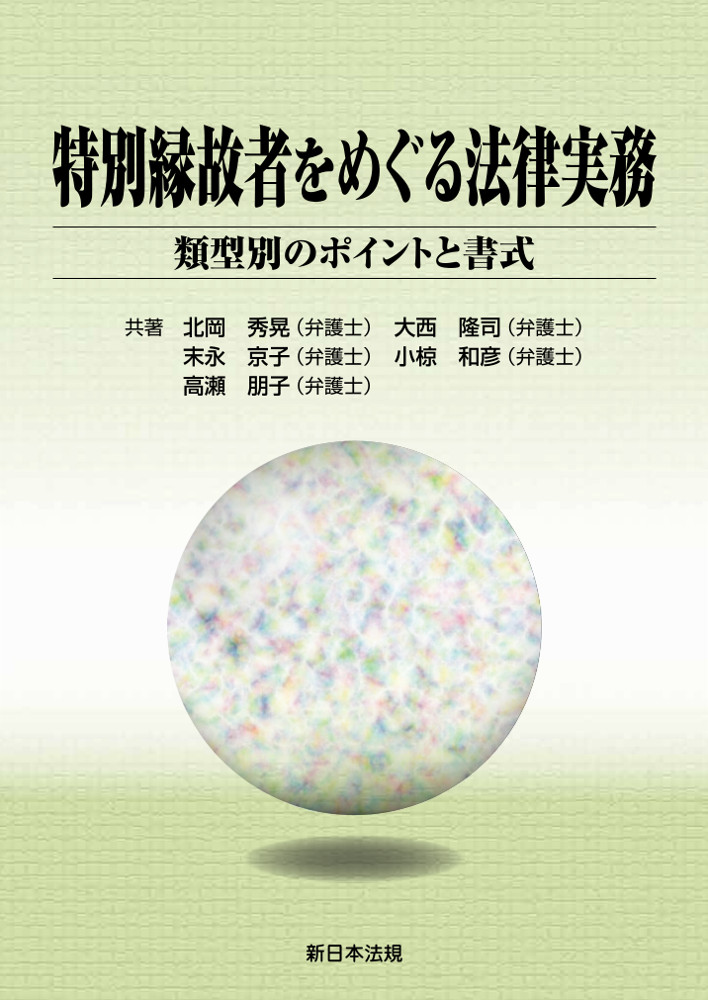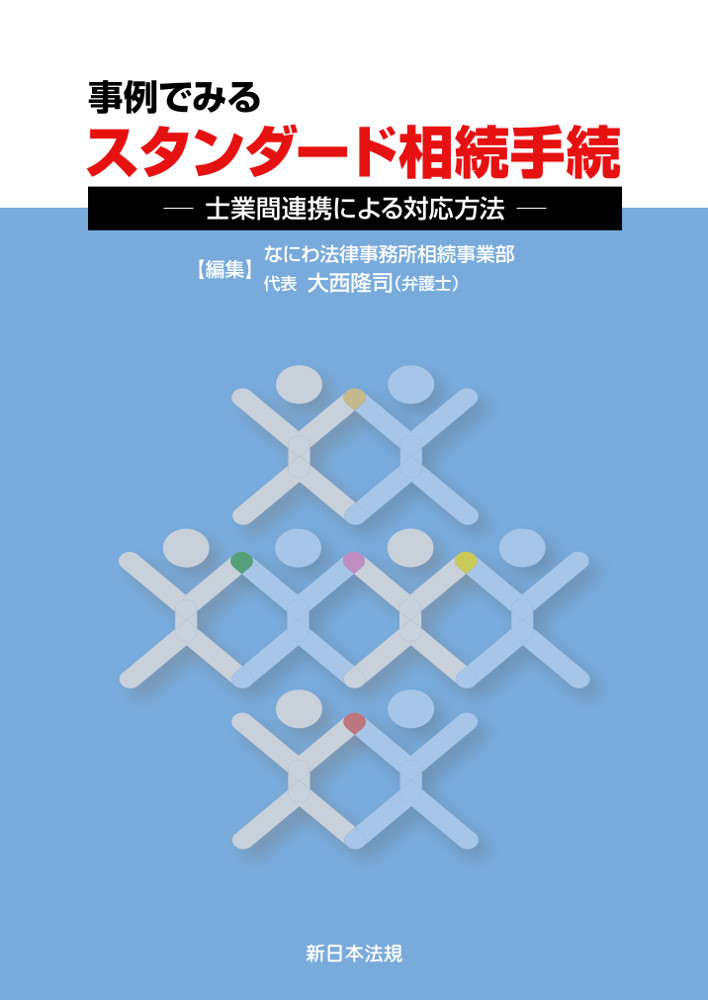人事労務2025年07月09日 社宅の明渡しをめぐる法律関係 執筆者:大西隆司

1 社宅使用契約の特徴
企業が従業員の福利厚生のため住まいを提供する社宅制度を設けている場合があります。多くの場合、企業が住居費の一部や賃貸契約の更新料などを負担することで従業員の負担が小さくなるよう運用されています。
このような社宅使用契約が一般の賃貸借であるとすれば、更新拒絶の場合の正当事由等、借地借家法の規程が適用され、使用者が退去を求める際の大きな制約となるところです。
この点、裁判例では、通常の賃料に相当する使用料の負担がない場合、借地借家法の適用が否定される傾向にあります。
会社が従業員の福利厚生施設の一つとして、一般の建物賃貸借における賃料より低廉な使用料で、その従業員に限って使用させている等の事情がある社宅について、入居願書の提出や社宅規則がなくても(判決当時の)借家法の適用はないと判示した例(最判S39.3.10)や雇傭している期間内にかぎり家屋を賃貸する約定について、当時の借家法の「賃借人ニ不利ナルモノ」とはいえないとしたものがあります(最判S35.5.19)。
以下、それ以降の社宅の終了関係が問題となった事例をみたいと思います。
2 労働関係継続中の社宅明渡
まず、独身寮の利用規程による居住制限年齢を超えているとして労働者に対し、会社が部屋の明渡しを求めた事例があります(東京地判H9.6.23)。
同事案では、会社が徴収した使用料等(使用料、光熱水料金、電話機等設備費)の徴収額が各寮の運営経費に比しても格別に低額であり、寮生の負担は一部のみであること、近辺の貸室の賃貸料との比較から、寮の利用関係は、従業員に対する福利厚生施策の一環として、社宅等利用規程によって規律される特殊な契約関係であって、借地借家法の適用はないと判断しています。
年齢制限が、同規程の改正により定められた点については、寮室の利用と使用料との間に対価性が認められないことも考慮すれば、特段の事情のない限り、会社が右規程の改正という方法で利用関係の内容を変更することができるとし、当初から居住期間について別に定めることが予定されていたこと、福利厚生費の効率的、公平な支弁を企図して本件改正を実施したこと、改正後の居住期間制限は「独身寮」の利用規定として不合理ではなく、改正に当たっては、手続的にも十分な経過措置がとられ、従業員への周知手続もなされていることを総合すると、本件改正が手続的に無効であるとか公序良俗に反し無効であると認める余地はないとしています。
労働契約の終了を伴わない社宅退去では、利用規定の定めが重要な判断要素となります。労働条件の一部となるため、労働契約法の就業規則の変更の要件を踏まえた規定の運用を心掛けましょう。
3 労働関係の終了と社宅明渡
労働契約関係の終了に伴う明渡では、タクシー会社から定年退職に伴う社宅契約の終了に基づき明渡等を求めた事案(東京地判H23.3.30)があります。
社宅の利用料が低額であり、その損失を会社が負担していたこと、敷金や礼金の徴収もしなかったこと、契約書に「当社を退職した場合は、この契約は無効となり、ただちに退去しなければならない」と定められていることから、本件社宅契約は、その法的性質が賃貸借であるか否かを問わず、雇用契約の終了と同時に終了するとして、明渡しを認容しています。
また、本件建物を賃借した上、従業員であった者に対し社宅として転貸したが、解雇に伴い転貸借契約は終了した等と主張して、建物部分の明渡し等を求めた事案があります(東京地判 R元.6.12)。
ここでも、転借料は賃借料と比較して月額1万5000円低額になっているところ、経緯等に鑑みると本件転貸借契約は福利厚生の一環として、専ら従業員たる身分を有する期間中の社宅を提供するために締結されたもので、従業員たる身分を失った場合には終了することが予定されており、契約が雇用契約の終了に伴い終了すると判断されています。
以上のように、労働関係終了を社宅契約の終了事由とするには、通常の賃料に相当する使用料の負担がないことを主張立証することが重要です。この点を意識して社宅制度の設計や運用をされるべきでしょう。
(2025年6月執筆)
(本記事の内容に関する個別のお問い合わせにはお答えすることはできません。)
人気記事
人気商品
関連商品
執筆者

大西 隆司おおにし たかし
弁護士(なにわ法律事務所)
略歴・経歴
なにわ法律事務所URL:http://naniwa-law.com/
「大阪産業創造館 経営相談室「あきないえーど」 経営サポーター(2012年~2015年3月、2016年~2019年3月、2020年4月~)」、関西大学非常勤講師(2014年度〜2016年度)、関西大学会計専門職大学院非常勤講師(2017年度〜)、滋賀県商工会連合会 エキスパート登録(2013年~)、大阪弁護士会遺言相続センター登録弁護士、大阪弁護士会高齢者・障害者支援センター「ひまわり」支援弁護士。
著書
『特別縁故者をめぐる法律実務―類型別のポイントと書式―』(新日本法規出版、2014年)共著
『法務・税務からみた相続対策の効果とリスク』(新日本法規出版、2015年)相続対策実務研究会代表大西隆司(なにわ法律事務所)編著
『事例でみる事業承継の実務―士業間連携と対応のポイント―』(新日本法規出版、2017年)編著
『〔改訂版〕事例でみるスタンダード相続手続―士業間連携による対応方法―』(新日本法規出版、2018年)編著等
『事例でみる スタンダード債権回収手続―専門家の視点と実務対応―』(新日本法規出版、2019年)編著
『相続対策別法務文例作成マニュアル―遺言書・契約書・合意書・議事録―』(新日本法規出版、2020年)著等
執筆者の記事
執筆者の書籍
関連カテゴリから探す
-

-

団体向け研修会開催を
ご検討の方へ弁護士会、税理士会、法人会ほか団体の研修会をご検討の際は、是非、新日本法規にご相談ください。講師をはじめ、事業に合わせて最適な研修会を企画・提案いたします。
研修会開催支援サービス -