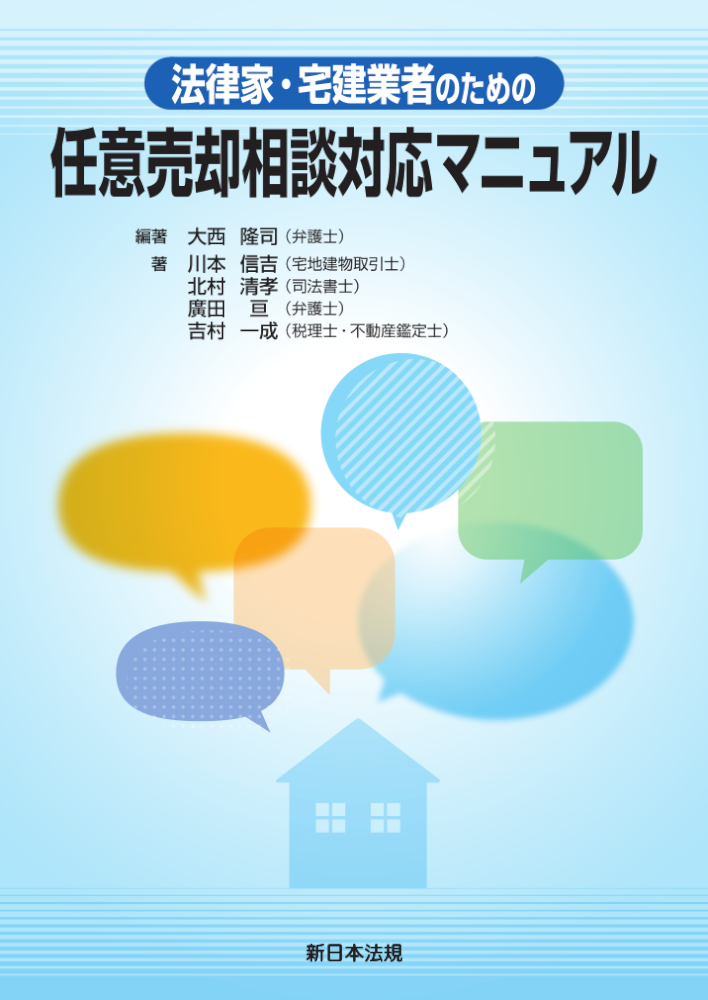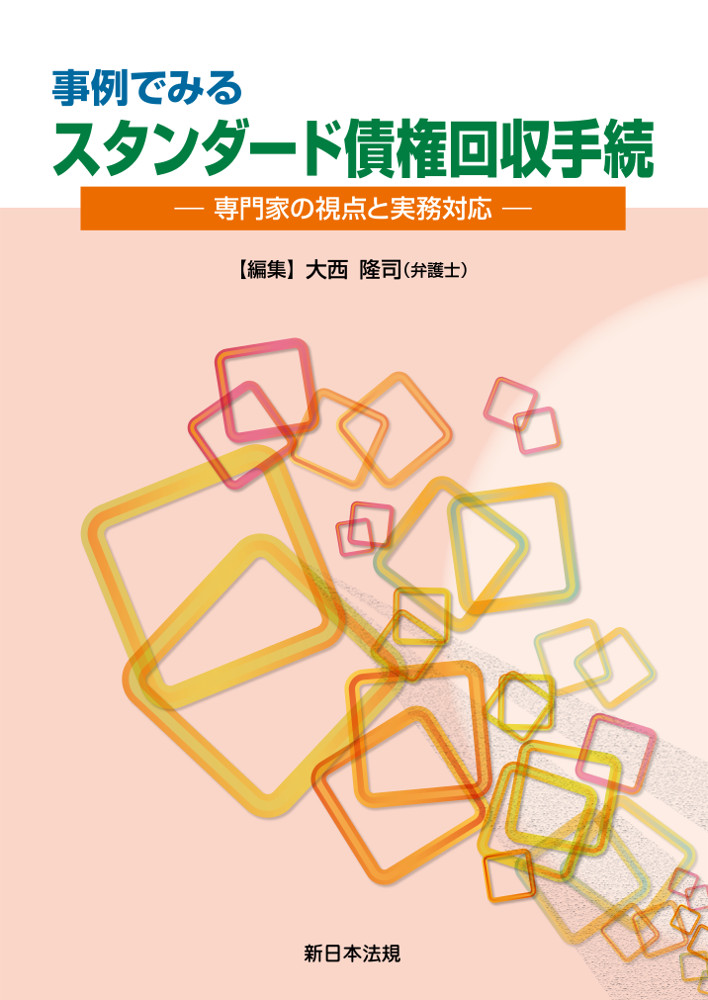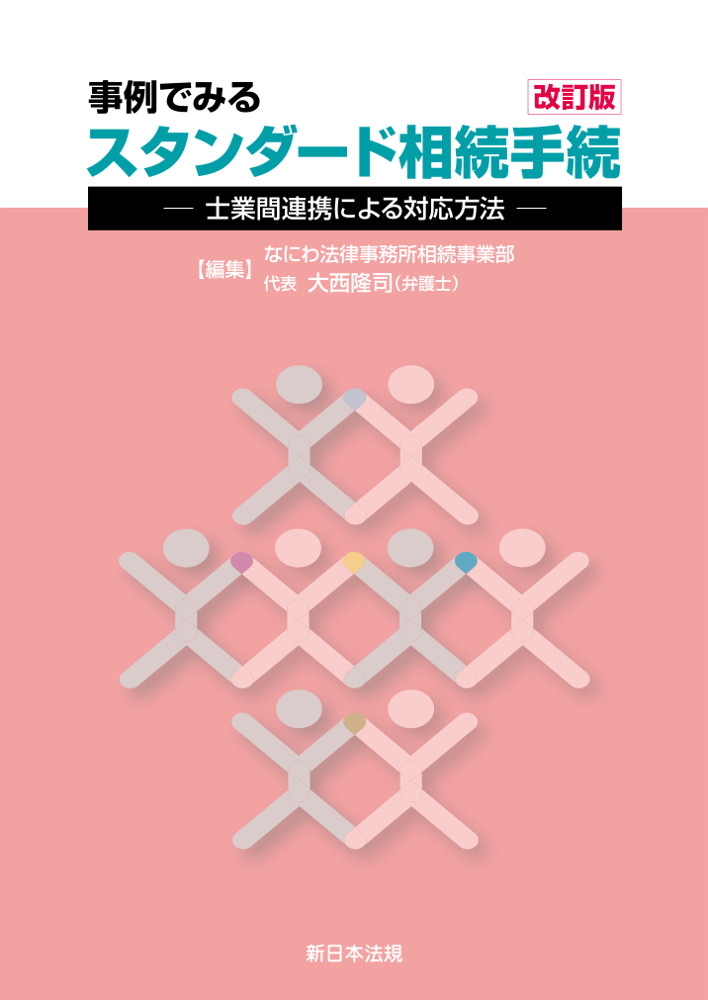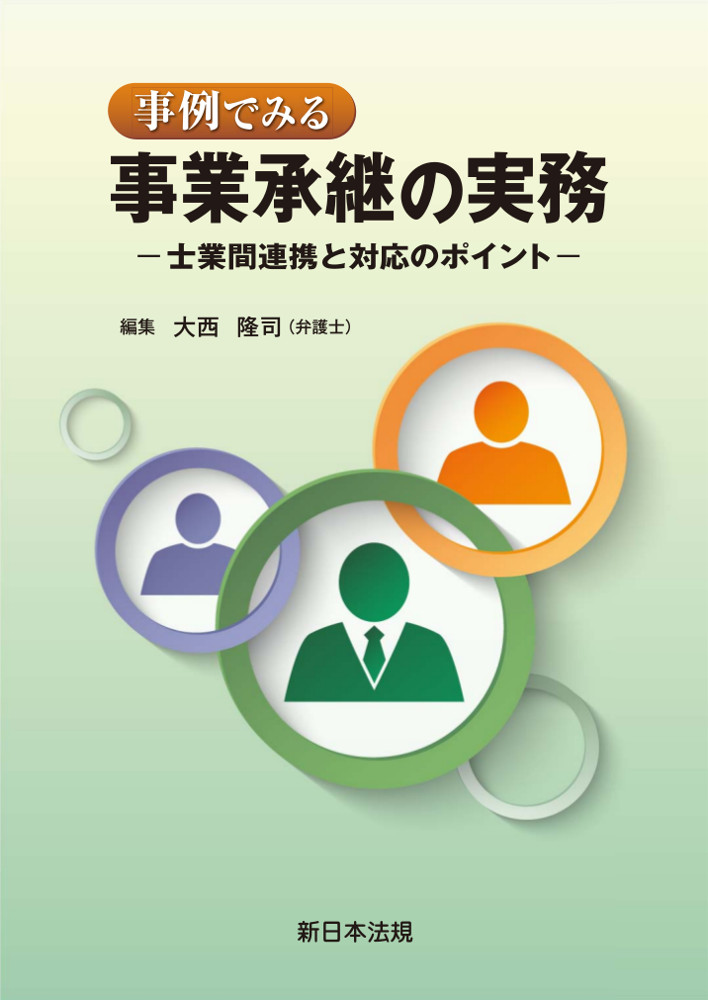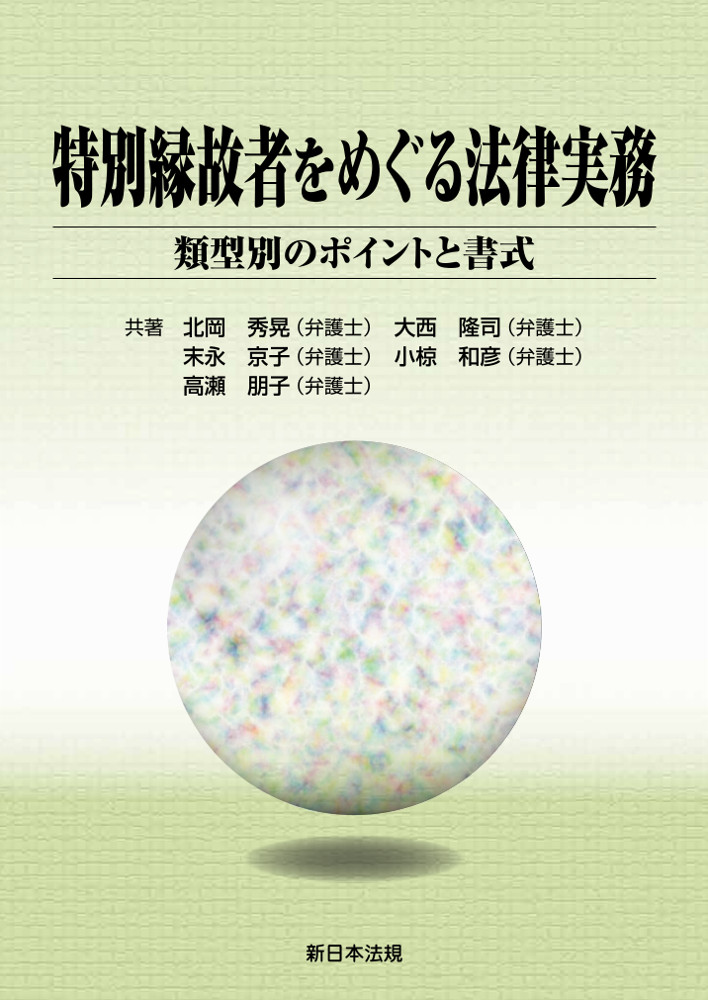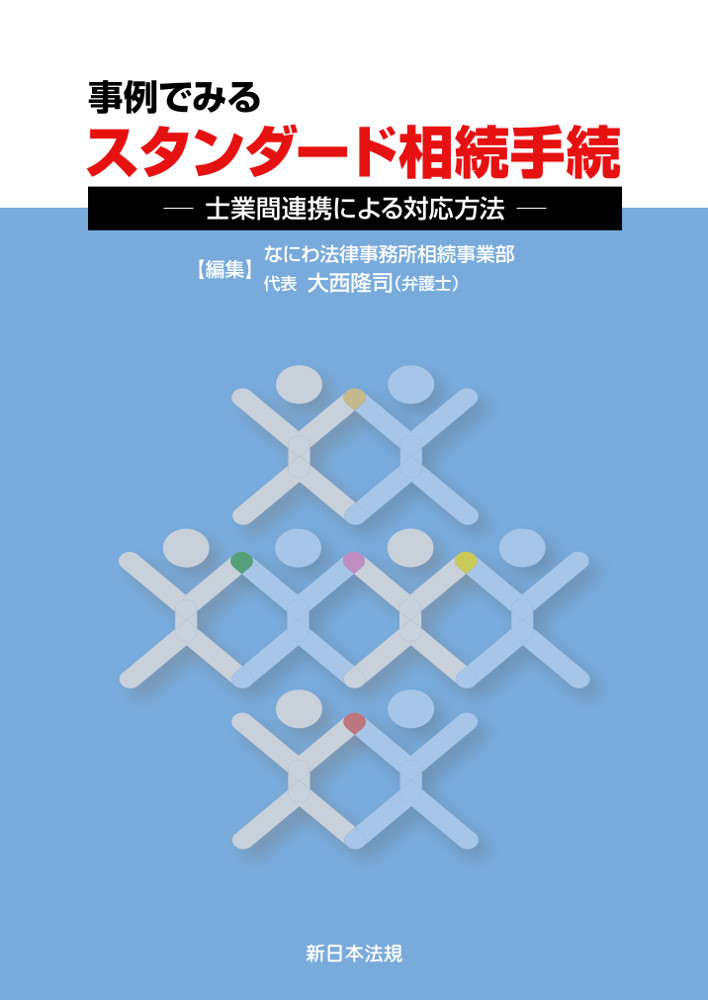労働基準2023年12月01日 始業時間前の準備作業が労働時間となるかどうか 執筆者:大西隆司

1、労働時間の把握
労働安全衛生法第66条の8の3は、事業者に厚生労働省令で定める方法により、労働者の労働時間の状況を把握しなければならないとし、事業者側に労働時間管理の法的義務を課しています。また、労働基準法では、労働時間の規制を置いて、所定の時間単価、割増率に割増の対象となる労働時間数を乗じて残業代が算出されるものとしており、使用者側に、労働時間を適正に管理する義務があると解釈されています。
労働安全衛生規則第52条の7の3は、厚生労働省令で定める方法は、タイムカードによる記録、パーソナルコンピュータ等の電子計算機の使用時間の記録等の客観的な方法その他の方法で行うとしつつ、やむを得ず、その他の方法として自己申告制とする場合、事業者は、「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン」に沿った措置(対象労働者及び管理者への十分な説明、必要に応じ実態調査と適宜補正、適正申告を阻害する措置の防止など)を全て講じる必要があるとして、客観的な記録を原則としています。
以上のように、使用者側で、労働時間を管理し、記録することが重要ですが、実労働以外の通勤時間、始業前の準備時間、更衣時間、終業前後の作業時間についてどの時点から労働時間として記録するか、始業時刻前の準備行為を労働時間とするか残業代請求との関係の訴訟で問題とされてきましたので、以下見ていきたいと思います。
2、労働時間について
判例は、労働時間を、労働者が使用者の指揮命令下に置かれている時間をいい、右の労働時間に該当するか否かは、労働者の行為が使用者の指揮命令下に置かれたものと評価することができるか否かにより客観的に定まるとしています(最判H12.3.9)。
なお、多くの裁判例では、指揮命令下に置かれたかどうかについて、使用者から義務付けられ、与儀なくされる状態にあるのかどうかという使用者の拘束性だけでなく、問題となる行為が業務性をもっているかどうかという視点も加味した上で、労働時間かどうかを判断しているところです。
3、移動時間について
労働者の自宅から職場までの通勤時間は、業務性がなく労働時間に該当しないとされています。
しかし、出張中の移動時間については、納品物の運搬を目的とする移動時間を労働時間として認める裁判例(東京地判H24.7.27)があります。その一方で、公共交通機関を利用した移動時間の裁判例(大阪地判H22.10.14)では、物品の届けが主要な目的等として出張時間中も物品の管理が要請される等の特段の事情のない限り、その自由度の程度からして労働時間とまで評価することはできないとされています。
移動時間は、業務性の強さと自由度があるかが労働時間と判断されるポイントとなります。
4、朝礼・更衣時間等の準備行為
早朝出勤しての掃除、着替えや朝礼、朝のラジオ体操の労働時間制が争われた裁判例(東京高判H25.11.21)では、体操や朝礼への参加は任意であり、着替えや掃除が義務付けられていたことを認めるに足りる証拠はないとして労働時間ではないとされています。
一方、造船所において、実作業に当たり、作業服及び防護具の装着を義務付けられ、装着を事業所内の所定の更衣室において行うとされていた事例(最判H12.3.9)において、作業服及び防護服の装着及び更衣所等からの移動、副資材等の受出し及び散水、作業場から更衣所への移動、作業服及び防護服の脱離を終えるまでの時間が労働時間であると認定しています。
また、制服を着用することが義務付けられ,朝礼の前に着替えを済ませることになっていた事案(東京高判R3.3.24)でも、その時間及び朝礼の時間以降について指揮命令下の労働時間であることが認定されています。
以上より、制服・作業着等の指定がない場合や制服・作業着を指定していても使用者があくまで労働者の便宜のため更衣場所を提供しているのみで義務付けがない場合は労働時間にあたらず、制服・作業着の着替え等に場所や時間を指定し、これを義務付けているとみれる場合であれば労働時間ととらえておく必要があるでしょう。
(2023年11月執筆)
人気記事
人気商品
執筆者

大西 隆司おおにし たかし
弁護士(なにわ法律事務所)
略歴・経歴
なにわ法律事務所URL:http://naniwa-law.com/
「大阪産業創造館 経営相談室「あきないえーど」 経営サポーター(2012年~2015年3月、2016年~2019年3月、2020年4月~)」、関西大学非常勤講師(2014年度〜2016年度)、関西大学会計専門職大学院非常勤講師(2017年度〜)、滋賀県商工会連合会 エキスパート登録(2013年~)、大阪弁護士会遺言相続センター登録弁護士、大阪弁護士会高齢者・障害者支援センター「ひまわり」支援弁護士。
著書
『特別縁故者をめぐる法律実務―類型別のポイントと書式―』(新日本法規出版、2014年)共著
『法務・税務からみた相続対策の効果とリスク』(新日本法規出版、2015年)相続対策実務研究会代表大西隆司(なにわ法律事務所)編著
『事例でみる事業承継の実務―士業間連携と対応のポイント―』(新日本法規出版、2017年)編著
『〔改訂版〕事例でみるスタンダード相続手続―士業間連携による対応方法―』(新日本法規出版、2018年)編著等
『事例でみる スタンダード債権回収手続―専門家の視点と実務対応―』(新日本法規出版、2019年)編著
『相続対策別法務文例作成マニュアル―遺言書・契約書・合意書・議事録―』(新日本法規出版、2020年)著等
執筆者の記事
執筆者の書籍
関連カテゴリから探す
最近閲覧した記事
-

-

団体向け研修会開催を
ご検討の方へ弁護士会、税理士会、法人会ほか団体の研修会をご検討の際は、是非、新日本法規にご相談ください。講師をはじめ、事業に合わせて最適な研修会を企画・提案いたします。
研修会開催支援サービス -

Copyright (C) 2019
SHINNIPPON-HOKI PUBLISHING CO.,LTD.