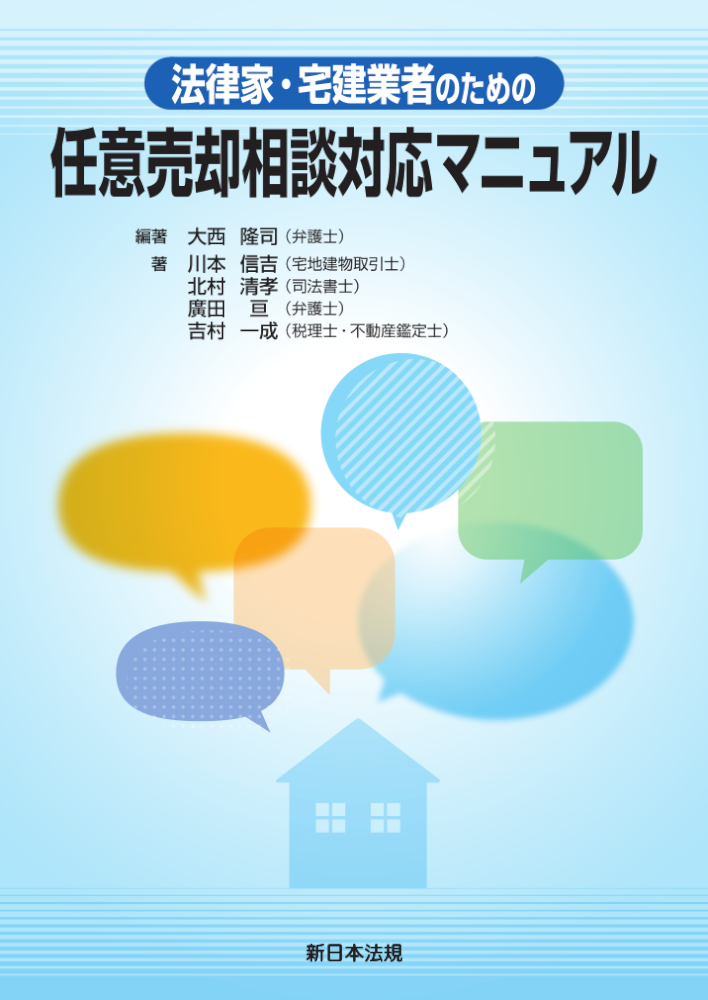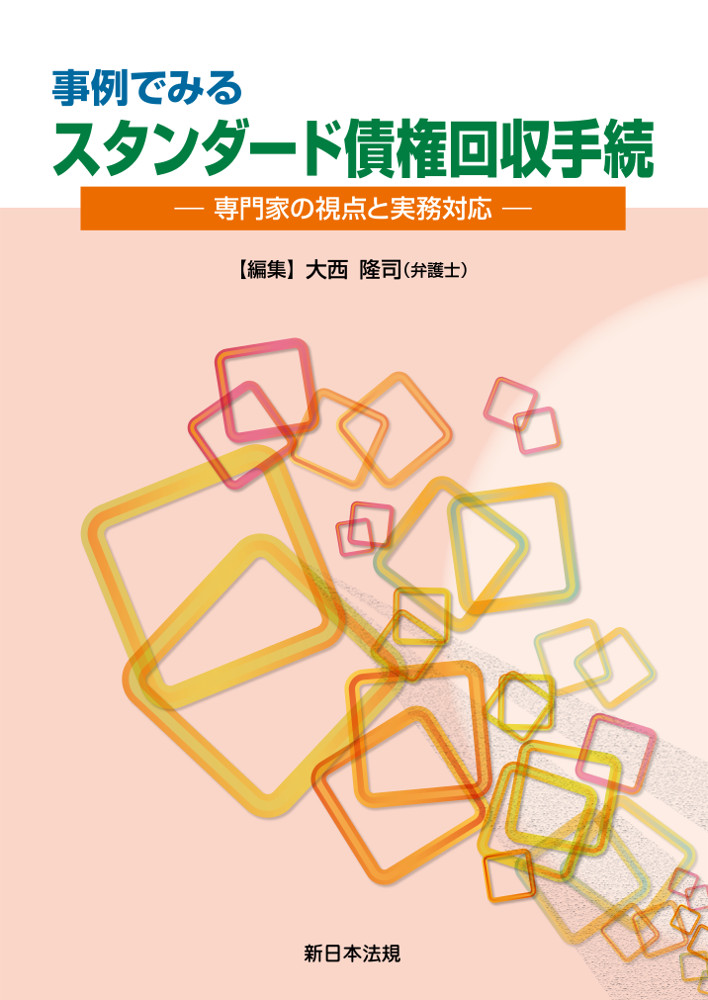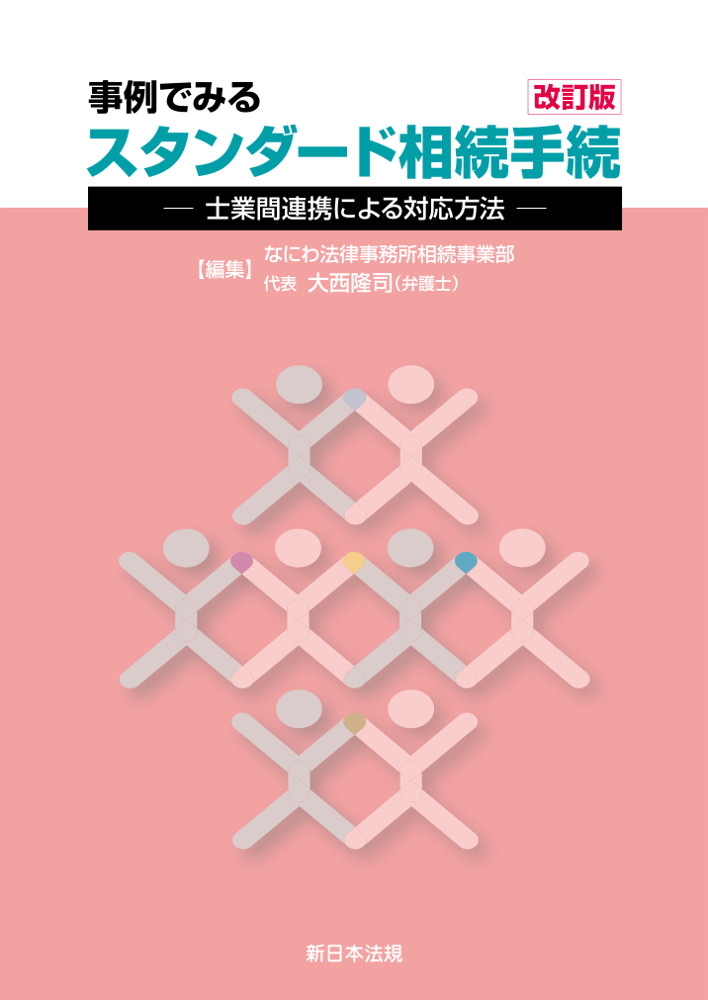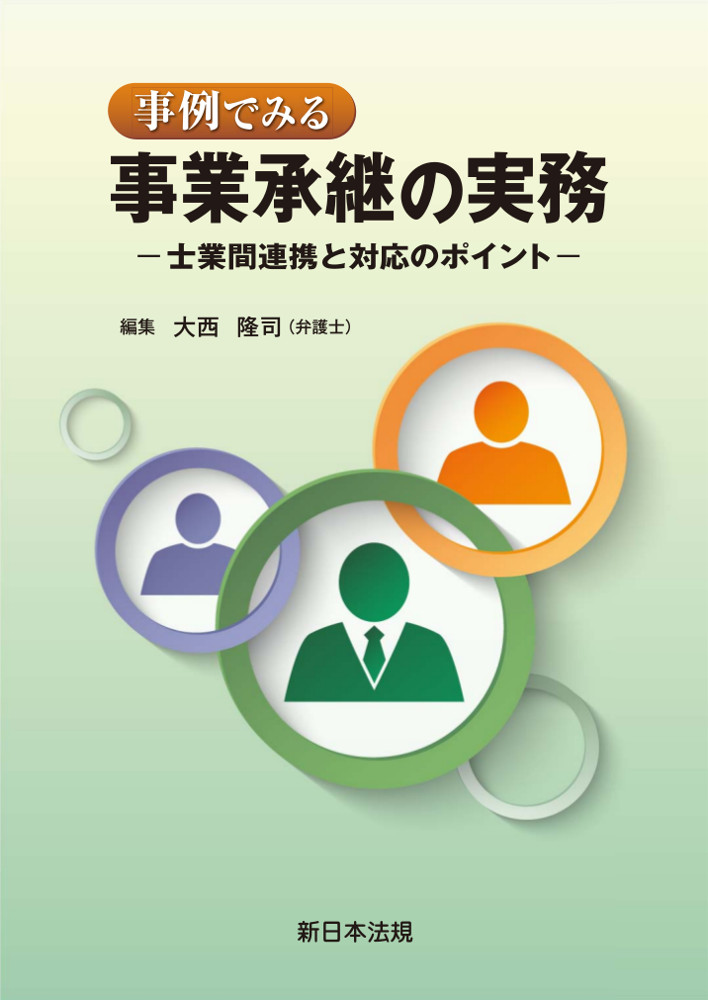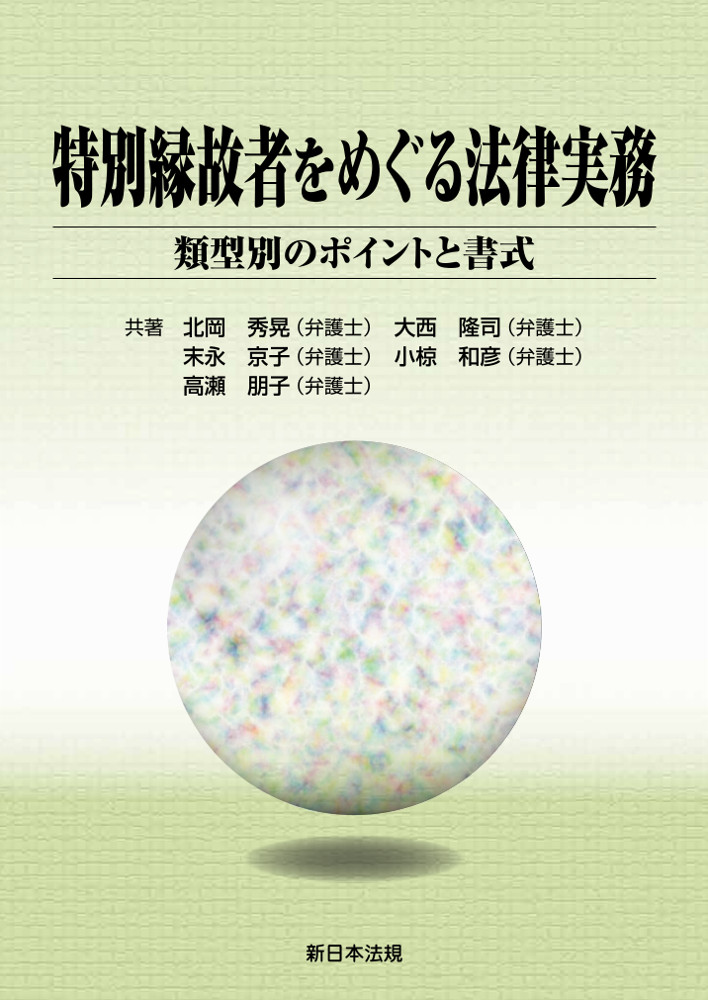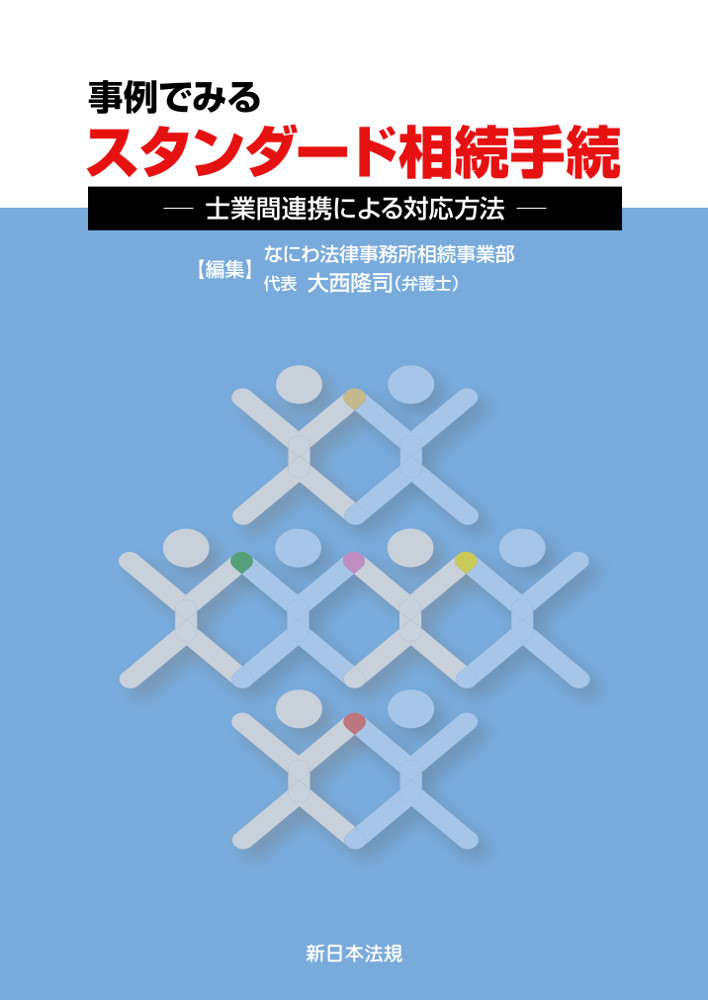労働基準2024年11月08日 ハラスメントによる精神障害について労災認定される基準 執筆者:大西隆司

1、ハラスメント事案と労災申請
企業において、従業員がパワハラやセクハラ等のハラスメント事案により精神疾患に罹患して、通院することになり、休業することになった場合、従業員から、使用者責任(民715条)や使用者自体の安全配慮義務違反を理由とする民事上の損害賠償請求がされる事例もめずらしくなくなりました。
また、ハラスメント事案による精神疾患が労災認定の対象となる精神疾患であった場合、「業務による心理的負荷評価表」(令和5年9月1日基発 0901 第2号の別表1)により、発病前のおおむね6か月間に業務による心理的負荷が「強」となる場合(かつ、業務以外の心理的負荷の評価や精神障害の既往症などの個体的要因の有無を検討し疾病がこれらの要因でない場合)は、業務上災害と認定されることになります。
認定されれば、従業員は、労災保険の療養給付や休業補償給付を受けることができ、症状固定に至った場合は障害補償の給付の対象となるため、ハラスメント事案における休業の際に、被害者の従業員からの労災申請を求める相談も増加していると感じています。
業務災害と認定された場合は、使用者は、労働者が業務上負傷し、または疾病にかかり休業する期間およびその後30日間は、解雇ができない(労基19条1項前段)とする解雇制限がかかり、使用者側が私傷病休職制度での契約終了などについて配慮することが必要となるため、どのような基準で労災認定されるかを知って対応することが重要です。
2、セクハラと労災基準
セクハラの場合では、強姦や本人の意思を抑圧して行われたわいせつ行為などのセクシュアルハラスメントを受けた場合が心理的負荷「強」とされています。
胸や腰などへの身体接触を含むセクハラであって継続して行われた場合、行為は継続していないが、会社に相談しても適切な対応がなく、改善されなかった、又は会社へ相談などをした後に職場の人間関係が悪化した場合が「強」になるとされています。
また、身体接触のない性的な発言のみのセクハラの場合も、発言の中に人格を否定するようなものを含み、かつ継続してなされた場合や性的な発言が継続してなされ、かつ会社がセクハラがあると把握していても適切な対応がなく、改善されなかった場合が「強」になる例とされています。
一方、胸や腰などへの身体接触を含むセクハラであっても、行為が継続しておらず、会社が適切かつ迅速に対応し発病前に解決した場合や身体接触のない性的な発言のみのセクハラであって、発言が継続していない場合・複数回行われたものの、会社が適切かつ迅速に対応し発病前にそれが終了した場合は、心理的負荷「中」程度とされ、(「中」の出来事が複数あり総合評価によって「強」とされる場合等を除いて)労災認定されない可能性が高くなります。
3、 パワハラと労災基準
パワハラの場合、上司等から、身体的攻撃、精神的攻撃等のパワーハラスメントを受けたという具体的出来事について、上司等から、治療を要する程度の暴行等の身体的攻撃を受けた場合や上司等から、暴行等の身体的攻撃を執拗に受けた場合が心理的負荷「強」とされています。
また、①人格や人間性を否定するような、業務上明らかに必要性がない又は業務の目的を大きく逸脱した精神的攻撃、②必要以上に長時間にわたる厳しい叱責、③他の労働者の面前における大声での威圧的な叱責、④人間関係からの切り離し、⑤過大な要求、⑥過少な要求、⑦私的なことに過度に立ち入る個の侵害などの精神的攻撃を執拗に受けた場合が「強」とされています。
一方、上司等による治療を要さない程度の暴行による身体的攻撃や精神的攻撃が行われ、行為が反復・継続していない場合は「中」とされていますが、心理的負荷としては「中」程度の身体的攻撃、精神的攻撃等を受けた場合であって、会社に相談しても適切な対応がなく、改善されなかった場合は「強」とされています。
(なお、優位性のない同僚等から暴行などを受けた場合は、別の対人関係の類型の暴行又は(ひどい)いじめ・嫌がらせを受けたという具体的出来事についての基準が適用されます。)
(2024年10月執筆)
(本記事の内容に関する個別のお問い合わせにはお答えすることはできません。)
人気記事
人気商品
執筆者

大西 隆司おおにし たかし
弁護士(なにわ法律事務所)
略歴・経歴
なにわ法律事務所URL:http://naniwa-law.com/
「大阪産業創造館 経営相談室「あきないえーど」 経営サポーター(2012年~2015年3月、2016年~2019年3月、2020年4月~)」、関西大学非常勤講師(2014年度〜2016年度)、関西大学会計専門職大学院非常勤講師(2017年度〜)、滋賀県商工会連合会 エキスパート登録(2013年~)、大阪弁護士会遺言相続センター登録弁護士、大阪弁護士会高齢者・障害者支援センター「ひまわり」支援弁護士。
著書
『特別縁故者をめぐる法律実務―類型別のポイントと書式―』(新日本法規出版、2014年)共著
『法務・税務からみた相続対策の効果とリスク』(新日本法規出版、2015年)相続対策実務研究会代表大西隆司(なにわ法律事務所)編著
『事例でみる事業承継の実務―士業間連携と対応のポイント―』(新日本法規出版、2017年)編著
『〔改訂版〕事例でみるスタンダード相続手続―士業間連携による対応方法―』(新日本法規出版、2018年)編著等
『事例でみる スタンダード債権回収手続―専門家の視点と実務対応―』(新日本法規出版、2019年)編著
『相続対策別法務文例作成マニュアル―遺言書・契約書・合意書・議事録―』(新日本法規出版、2020年)著等
執筆者の記事
執筆者の書籍
関連カテゴリから探す
-

-

団体向け研修会開催を
ご検討の方へ弁護士会、税理士会、法人会ほか団体の研修会をご検討の際は、是非、新日本法規にご相談ください。講師をはじめ、事業に合わせて最適な研修会を企画・提案いたします。
研修会開催支援サービス -

Copyright (C) 2019
SHINNIPPON-HOKI PUBLISHING CO.,LTD.