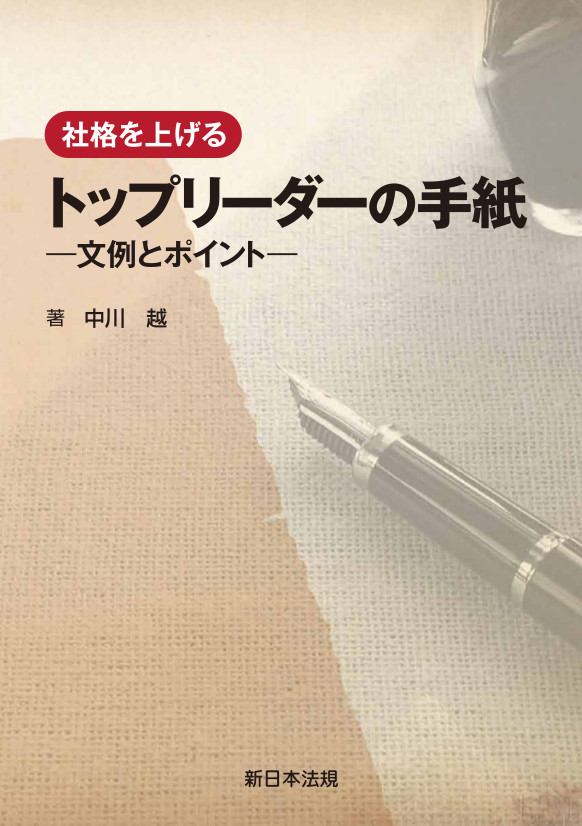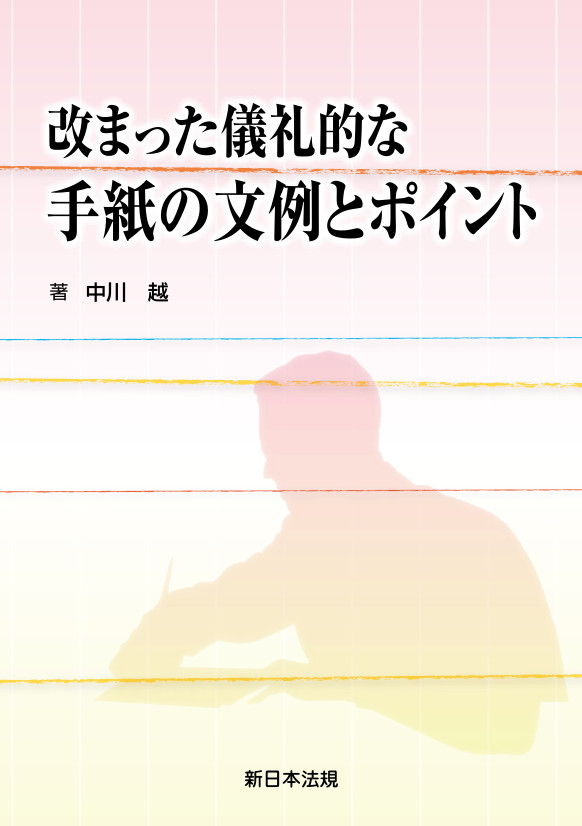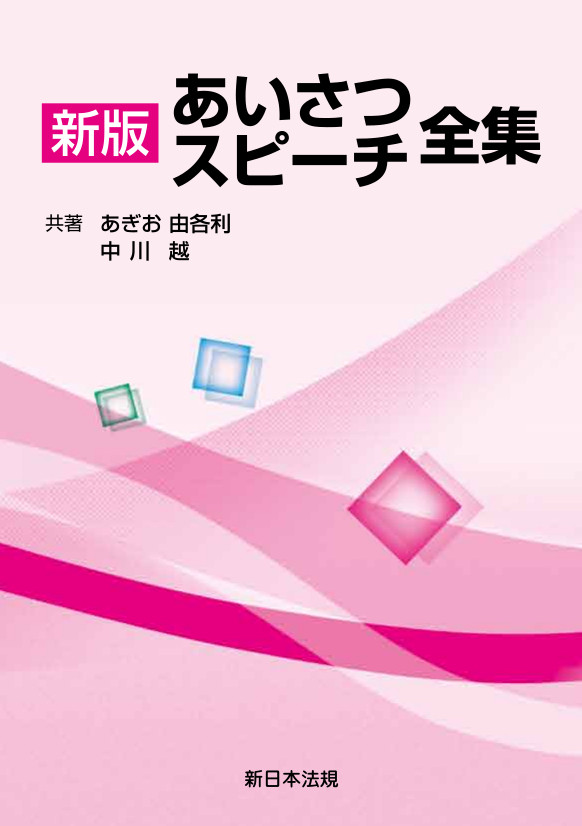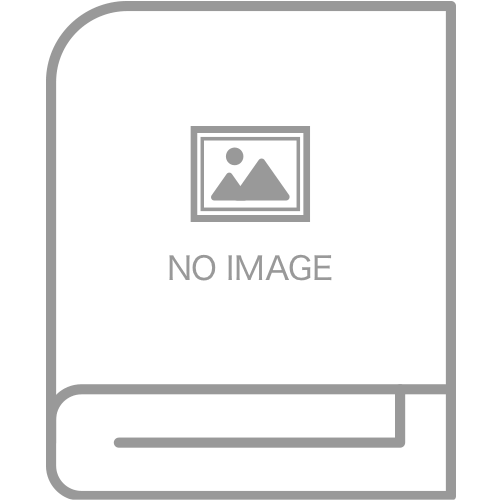一般2025年09月10日 契約に関わる文豪書簡(2)―離縁状できれいに婚姻関係を解消した永井荷風とその妻―(法苑WEB連載第17回)執筆者:中川越 法苑WEB

●三行半は離縁の意志を表明するための公式文書だった
さて、次の実線三本半は、何でしょうか。
答えは、明治13(1880)年に発行された司法省版『全国民事慣例類集』によって紹介された、神奈川県鎌倉郡の公文書の書式見本です。
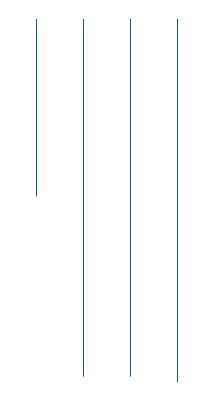
何の書式見本かというと、離縁状です。
同書には、次の説明書きがあります。
「離縁ノトキハ必ス離縁状アルモノトス其状ハ必ス夫タリシ者ヨリ婦タリシ者ノ名宛てニテ自筆ニ記シ爪印ヲ押スコトナリ若シ自書スルコト能ワサレハ三本半ノ竪線を画シ爪印ヲ押ス所謂三行半ノ旧例アルカ故ナリ」
つまり、こうです。
〈離婚するときには、離縁状を必要とする。その書状は夫だった者から妻だった者に宛て、自筆で書き爪印を押すこと。もし自分で書くことができなければ、三本半のタテ線を描き爪印を押す。こうするのは、いわゆる三下り半の古い習慣があるからだ〉
「爪印」とは、印章を持たない人が、爪の先に墨をつけてハンコ代わりに押したものです。「三下り半の旧例」とは、江戸時代の離縁状のことをさしています。
熱烈に愛し合って結ばれた夫婦が、たった三本半の線により袂を分かつのは、あまりにもあっけなく薄情ですが、キッパリと別れてサッパリするためには、この簡単な離縁状の方が、むしろ効果的かもしれません。
では、その内容は、どんなものだったかというと、ごく一般的な三下り半は、次の通りです。
離縁状之事
一此哥と申女 下三条村 源右衛門殿 世 話 ヲ
以貰請処、此度離別いたし候上は、重て
何方 え 縁付候共、 此 ニ お ゐ て 差構
無之候、仍て離縁状如レ件
天保十亥八月 伝四郎 (爪印)
うたとのへ
江戸時代の終わり頃の天保10年、1839年に書かれたこの離縁状の意味は。
〈このうたと言う女を、下三条村 源右衛門殿の世話によってもらいうけましたが、今回離縁しましたので、今後誰と再婚しようとも、この書状によって差しつかえないことを証明します。離縁状はこの通りです。〉
三本半の線よりはマシですが、実に事務的です。一切の感情表現を排除して、離婚の意志と再婚の許可だけを伝えています。
ついては、江戸時代の離縁状が、なぜ三下り半と呼ばれるようになったかということも気になりますが、これには多説あります。
必要なことだけ書いたら、だいたい三行半になったので、その書例が一般化して三下り半という書式ができ、離縁状の代名詞になったという説や、中国の離縁状の文書を参考にしたら三行半になったという説などがあります。
しかし離縁状は、三行半とは限らず、しかも、事務的なものばかりではなく、体温の感じられる次のような美文も存在しました。
一 偕老同穴之契既にたえ、会者
定離の浮世、愛別離苦の習ひ
今更不有可驚、よって離状如件
天保十年寅三月
摺 淵 村
蔦 吉
同村佐兵衛
志 ち 殿
夫婦の理想、偕老同穴に至らなかった無念を、会者定離の無常観により受け入れようと努めるようすに、冷めやらない夫婦愛の残滓が感じられます。
いずれにしても、多くの場合三行半には、離婚理由は書かれなかったようです。
「淫乱だから離婚」「やきもち焼きだから離婚」「おしゃべりだから離婚」「手癖が悪いから離婚」などと書かれた日には、せっかくの再婚の許可文言も、役に立たないものになってしまいます。
離婚理由を書かないことが、せめてもの最後の愛情表現だったということができそうです。
●永井荷風の妻は離婚理由をしっかり書きあっさり別れた
一方、文豪永井荷風の妻八重次は、離縁状の中で離婚理由をこのように明記しました。
一筆申残しまいらせ候。私事こちらへかたずき候事、よくにも見えにもあらず。
ただ捨てがたき恋のれきしがいとおしさに候。もとよりなれぬ手業、お針もおぼつかなく水仕の事は云うまでもなく候。さぞお気に入らぬ事だらけと、御きのどくに存じ上げ候も、私はそのくらいの事くんで下さる御方と、日々うれしくつとめ居り候処、あなた様にはまるで私を二足三文にふみくだし、どこのかぼちゃ娘か大根女郎でもひろって来たように、御飯さえたべさせておけばよい。夜の事は売色にかぎる。夫がいやなら三年でも四年でもがまんしているがよい。夫は勝手だ。女房は下女と同じでよい。「どれい」である。…つまりきらわれたがうんのつき、見下されて長居は却って御邪魔。…此手紙父に御見せ下されて、あなた様の御気のすむようどうとも御はからい下され度候。あらあらかしく
二月十日夜八時半 八重より 旦那様 御許 (大正4年2月10日付)
〈あなたのような地位ある方と私が結婚したのは、欲にかられたり見栄を張るためではありません〉と伝えたあとに続く、「ただ捨てがたき恋のれきしがいとおしさ」という表現は高雅で情感豊かです。一方、「二足三文」「かぼちゃ娘」「大根女郎」は、威勢のいい下町言葉で、真剣な訴えなのにユーモアさえ感じます。
雅俗織り交ぜた表現は、粋な八重次の艶やかな魅力をそのまま伝えているように思われます。
当時のある軟派な新聞コラムは、八重次の容姿をこう称えました。
「明眸皓歯、丹花の唇、流石は嘗て雪の越路に、月と唄われた名花丈に、捨て難い面影の男心をそそるものあるを否む訳には行かぬ。この美人こそ誰あろう、…巴家八重次」
そして、荷風と八重次の仲を次のように伝えました。
「渠(=荷風)の享楽主義は、文学の上ばかりでない。米国仏蘭西至る処浮き名を流して来たが、更に新橋柳橋の花街に於ては、その長く伸ばした髪その色白く輪郭の整うた顔、その典雅なる風采、その洗練されたる遊び振が一きわ目立って、『粋な人』『うれしい人』としてもてる事夥しい。嘗て、文学芸者として知られた、新橋の巴家の八重次と相思の中で、牛込に瀟洒たる妾宅を構えて、甘く悲しき享楽の夢に耽り…」
なお、八重次が「文学芸者」と呼ばれたのは、短歌を学び、漢籍の素養があったからです。
八重次と荷風が出会ったのは、明治43(1910)年、八重次30歳、荷風31歳のことでした。荷風はエリート官吏の父に従い、明治45(1912)年、気の進まない結婚をしますが、結婚後も八重次のところに通い、翌年離婚。その翌年の大正三年に親や親戚の猛反対を押し切って八重次と結婚。しかし、その結婚も長続きせず、翌年離婚。離婚理由は、八重次の手紙にもあるように、放埓に生きた荷風の浮気でした。
では、妻八重次からの離縁状に対して、荷風はどのように対応したのでしょうか。
荷風は2週間後に次の返事を書きました。
一筆申入候 さてさてこの度は思いもかけぬ事にて何事も只一朝にして水の泡と相成申候 一時の短慮二人が身にとり一生の不幸と相成候 今更未練がましきことは友達の手前一家の手前浮世の義理の是非もなし ただ涙を呑むより外致方無御座候 …これより先一生は男の一人世帯張り通すより外致方なく 朝夕の不自由は只途法に暮れ居り候 お前さまは定めし舞扇一本にて再びはればれしく世に出る御覚悟と存候 かげながら御成功の程神かけていのり居候 かえすがえこの度の事残念至極にてお互いに一生の大災難とあきらめるより詮方なく 私の胸の中もとくとお咄し致度存候えども …いずれここの処しばらく月日をへだて候はば再びお目にかかりしみじみお咄し致す折もあるべきかとそれのみ楽しみに致候 (大正4年2月24日付)
突然のことに驚き、涙を流し途方に暮れたとしています。そして、「舞扇一本」で芸妓として活躍する八重次の今後を励まし、離婚やむなし、未練がましいことは言うまいとも述べていますが、そもそも未練はあまりなかったのかもしれません。
というのは、荷風の口調が悠長で、どことなく余裕があり、それほど悲しそうではないからです。
三行半ではすみませんでしたが、ともあれ二人はこの2通のやり取りで、離婚問題に決着をつけたようです。
【中川 越 なかがわ・えつ プロフィール】
手紙文化研究家・コラムニスト。東京新聞「文人たちの日々好日」連載中/日本絵手紙協会の「月刊絵手紙」〈手紙のヒント〉」連載中/「月刊日本橋」〈発掘!日本橋逸聞逸事〉連載中/〇主な著書 『すごい言い訳!―漱石の冷や汗、太宰の大ウソ―』(新潮文庫)/『文豪たちの手紙の奥義 ―ラブレターから借金依頼まで―』(新潮文庫)/『夏目漱石の手紙に学ぶ 伝える工夫』(マガジンハウス)/『漱石からの手紙 人生に折り合いをつけるには』(CCCメディアハウス)/『文豪に学ぶ 手紙のことばの選びかた』(東京新聞)/『NHKラジオ深夜便 文豪通信』(河出書房新社)など。
(本記事の内容に関する個別のお問い合わせにはお答えすることはできません。)
法苑WEB 全22記事
- 「始皇帝モノ」は面白い。連載コラムその5 ─応用編⑵『コウラン伝 始皇帝の母』 (後半・39~62話)の紹介─(法苑WEB連載第22回)執筆者:坂和章平
- 私たちが負担した消費税は国に納められているか ~インボイス制度からみる消費税のしくみ(後編)(法苑WEB連載第21回)執筆者:深作智行
- 契約に関わる文豪書簡(3)―転職に際して条件闘争に勝利し、借金苦から脱出した漱石―(法苑WEB連載第20回)執筆者:中川越
- 「始皇帝モノ」は面白い。連載コラムその4 ─応用編⑵『コウラン伝 始皇帝の母』 (前半・1~38話)の紹介─(法苑WEB連載第19回)執筆者:坂和章平
- 私たちが負担した消費税は国に納められているか~インボイス制度からみる消費税のしくみ(前編)(法苑WEB連載第18回)執筆者:深作智行
- 契約に関わる文豪書簡(2)―離縁状できれいに婚姻関係を解消した永井荷風とその妻―(法苑WEB連載第17回)執筆者:中川越
- 契約に関わる文豪書簡(1)―法律の条文のような諭吉・らいてふの書簡―(法苑WEB連載第16回)執筆者:中川越
- 子どもの意見表明の支援は難しい(法苑WEB連載第15回)執筆者:角南和子
- 「始皇帝モノ」は面白い。連載コラムその3 ─応用編⑴『大秦帝国』シリーズ全4作の紹介─(法苑WEB連載第14回)執筆者:坂和章平
- コンダクト・リスクの考え方~他律から自律への転換点~(法苑WEB連載第13回)執筆者:吉森大輔
- 消防法の遡及制度(法苑WEB連載第12回)執筆者:鈴木和男
- 「始皇帝モノ」は面白い。連載コラムその2 ─入門編は『キングダム~戦国の七雄』から─(法苑WEB連載第11回)執筆者:坂和章平
- 株分けもの(法苑WEB連載第10回)執筆者:村上晴彦
- 「始皇帝モノ」は面白い。連載コラムその1 ─『キングダム』シリーズ全4作を楽しもう!─(法苑WEB連載第9回)執筆者:坂和章平
- 小文字の世界(法苑WEB連載第8回)執筆者:田中義幸
- 20年ぶりに「学問のすすめ」を再読して思うこと(法苑WEB連載第7回)執筆者:杉山直
- 今年の賃上げで、実質賃金マイナスを脱却できるか(令和6年の春季労使交渉を振り返る)(法苑WEB連載第6回)執筆者:佐藤純
- ESG法務(法苑WEB連載第5回)執筆者:枝吉経
- これからの交通事故訴訟(法苑WEB連載第4回)執筆者:大島眞一
- 第三の沈黙(法苑WEB連載第3回)執筆者:相場中行
- 憧れのハカランダ(法苑WEB連載第2回)執筆者:佐藤孝史
- 家庭裁判所とデジタル化(法苑WEB連載第1回)執筆者:永井尚子
執筆者

中川 越なかがわ えつ
略歴・経歴
コラムニスト、手紙文化研究家。東京都出身。書籍編集者を経て執筆活動に入る。
主な著書は以下の通り。
「改まった儀礼的な手紙の文例とポイント」(新日本法規出版)
「新版あいさつ・スピーチ全集(共著)」(新日本法規出版)
「気持ちがきちんと伝わる! 手紙の文例・マナー新事典」(朝日新聞出版)
「実例大人の基本手紙書き方大全」(講談社)
「文豪に学ぶ手紙のことばの選びかた」(東京新聞)
「文豪たちの手紙の奥義」(新潮文庫)
「すごい言い訳!―漱石の冷や汗、太宰の大ウソ―」(新潮文庫)
「高等学校国語表現Ⅱ」(第一学習社版)〈中川越「心に響く手紙」が3頁にわたり収載〉
執筆者の記事
執筆者の書籍
関連カテゴリから探す
-

-

団体向け研修会開催を
ご検討の方へ弁護士会、税理士会、法人会ほか団体の研修会をご検討の際は、是非、新日本法規にご相談ください。講師をはじめ、事業に合わせて最適な研修会を企画・提案いたします。
研修会開催支援サービス -