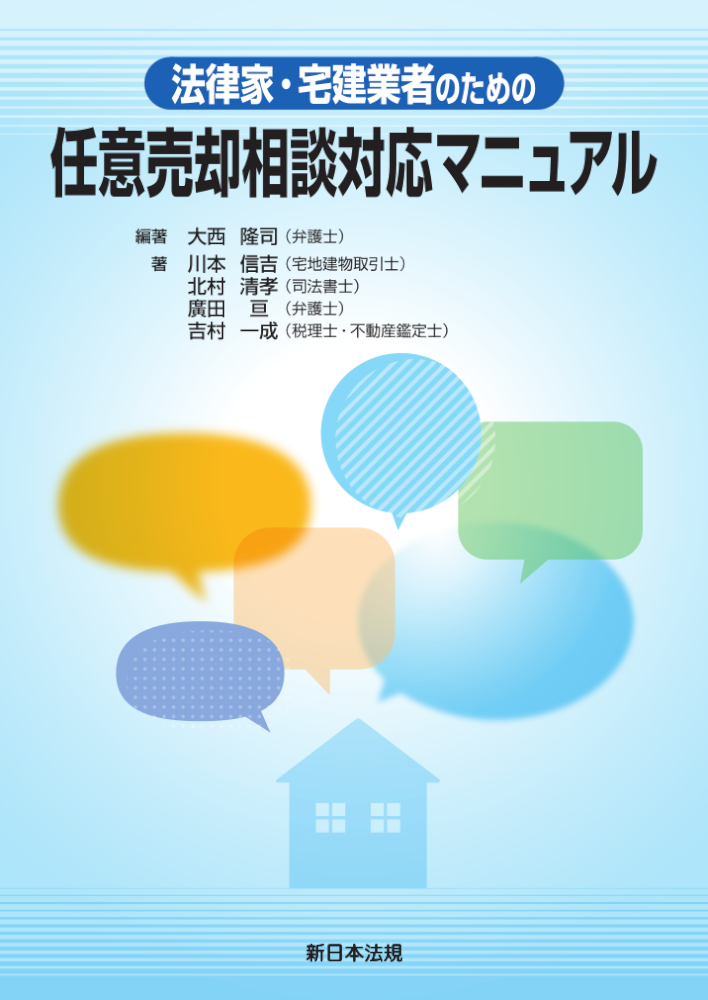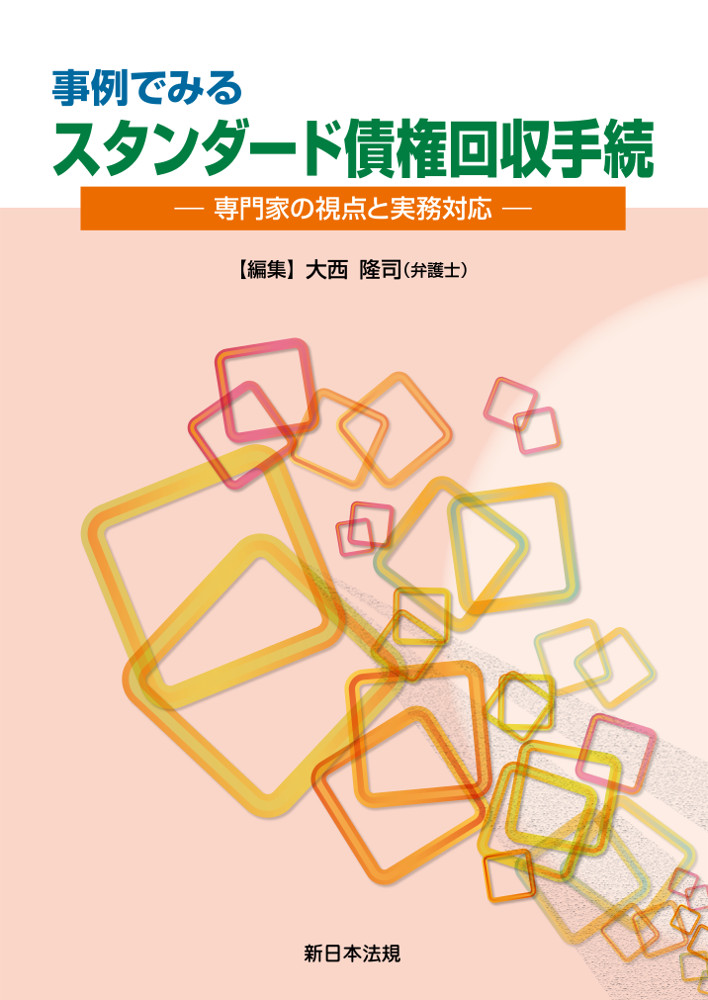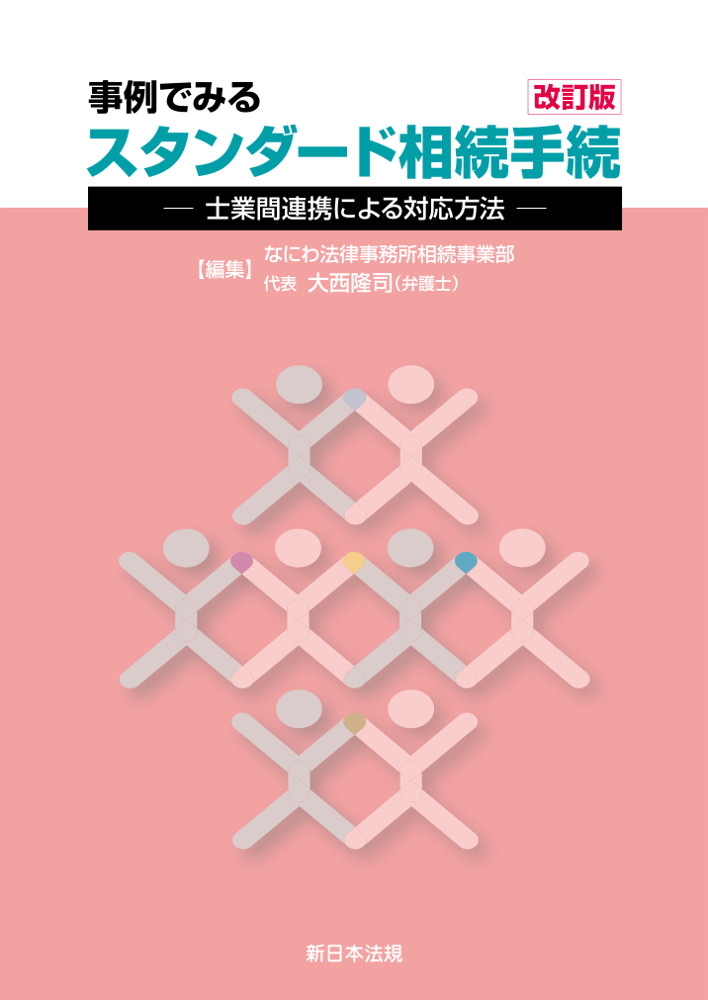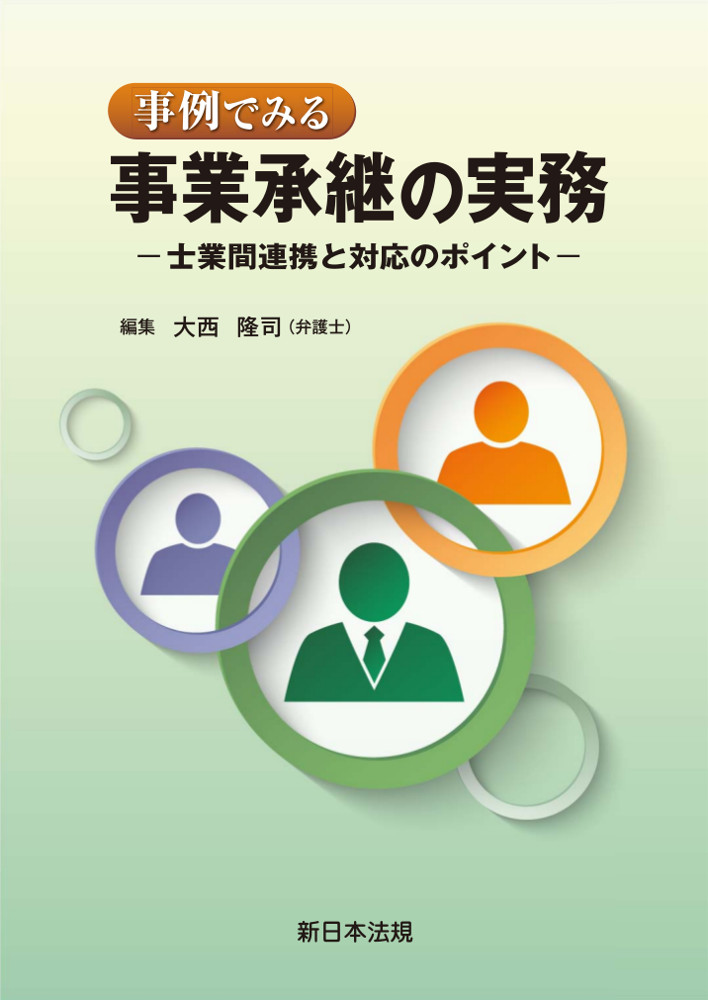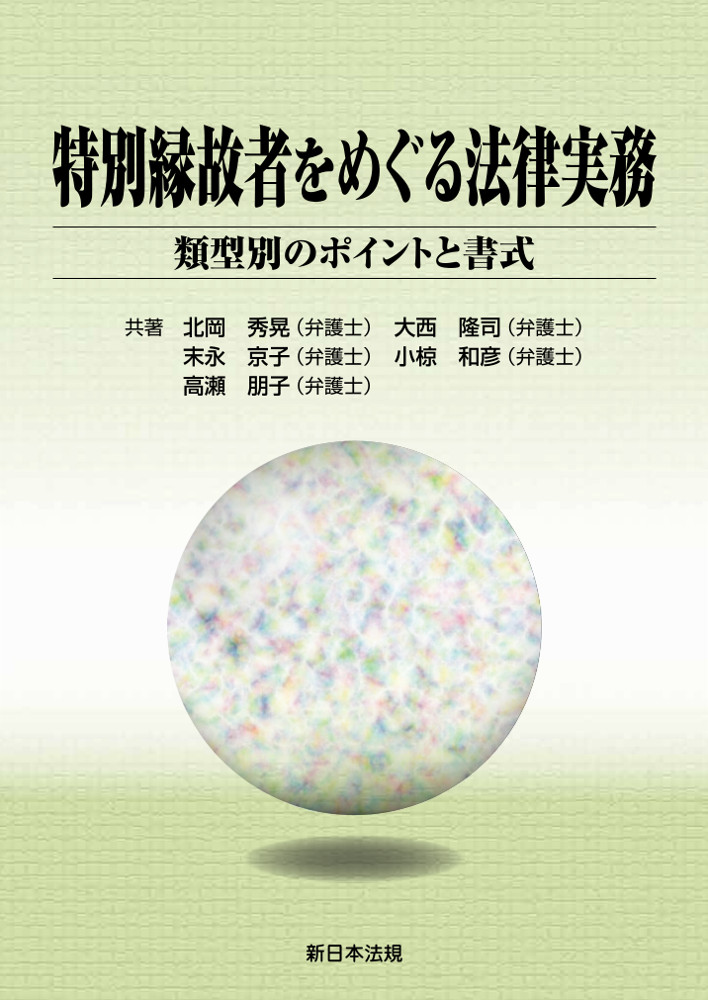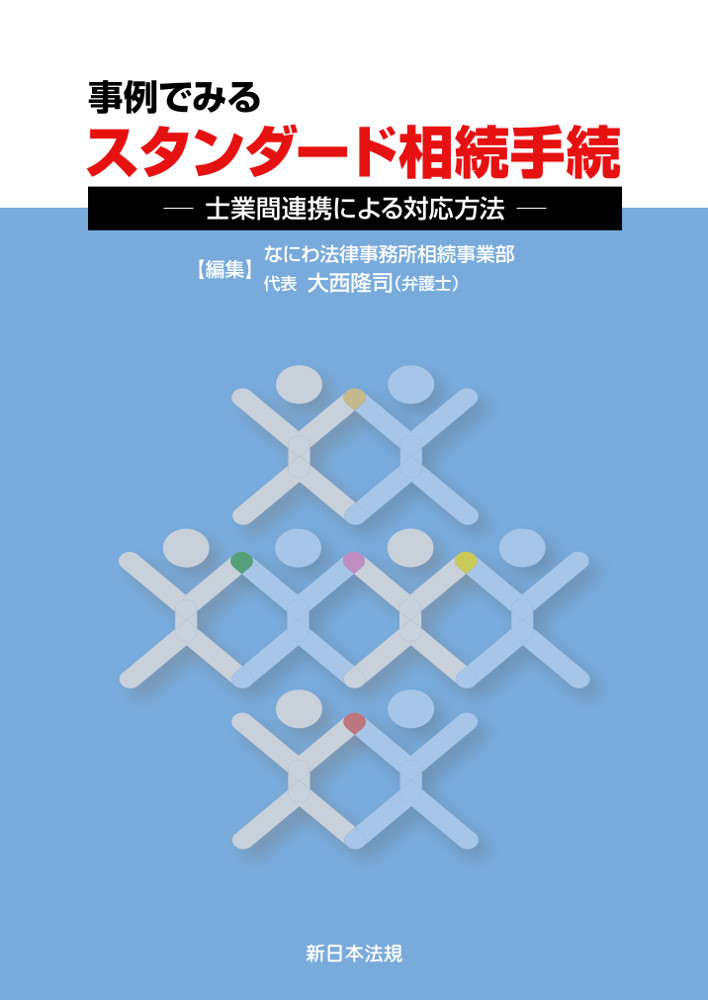労働基準2024年07月08日 カスタマーハラスメントと事業主の安全配慮義務 執筆者:大西隆司

1、カスタマーハラスメントと安全配慮義務
近時、顧客からの迷惑行為がカスタマーハラスメントとして話題となり、これに対する企業の対応が問題となっています。
令和元年6月に、労働施策総合推進法等が改正され、職場におけるパワーハラスメント防止のために雇用管理上必要な措置を講じることが事業主の義務となり、令和2年1月に、「事業主が職場における優越的な関係を背景とした言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置等についての指針」(令和2年厚生労働省告示第5号)が策定されています。
そこでは、顧客等からの暴行、脅迫、ひどい暴言、不当な要求等の著しい迷惑行為(カスタマーハラスメント)に関して、事業主は、相談に応じ、適切に対応するための体制の整備や被害者への配慮の取組を行うことが望ましく、被害を防止するための取組を行うことが有効であるとされています。
使用者は、労働契約に伴い、労働者がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働ができるよう、必要な配慮をする安全配慮義務があり(労働契約法5条)、顧客からの迷惑行為について適切な対応を行わなかった場合には、同義務違反となり、従業員から損害賠償請求がされる可能性があります。
近時の裁判例を通して、企業がとるべき対応のポイントについて記載します。
2、顧客への対応が問題となった裁判例
まず、食品スーパーのレジ担当従業員が、接客態度を不満に思った顧客と言い争いとなり、大声でなじられるなどの暴言等があったのに、正社員の配置や入店拒否措置を取らなかったことに義務違反があるとして損害賠償を求めた事案(東京地判H30.11.2)があります。
同裁判例は、誤解に基づく申出や苦情を述べる顧客への対応について、入社テキストを配布して初期対応を指導していた点、サポートデスクや近隣店舗・エリアのマネージャー等に連絡できる相談体制があった点、深夜時間においても店舗を2名体制にし、トラブルが生じた場合、他の店員により相談、通報等の対応ができる体制が整えられていた点等を評価し、安全配慮義務違反を否定しています。
また、事業主が、客からの退職要求に応じることなく、双方に関係修復を働きかけ、トラブル再発の際は、入店拒否措置の可能性を客に伝えて来店しなくなっていたこと等から、対応について穏便な措置から順次実施していたと評価し、早期に入店拒否措置をする義務違反はないとしています。
次に、NHKの委託先のコールセンターで、頻繁にわいせつ電話や暴言等を受けていた従業員が、雇用主に、刑事や民事上の法的措置をとり、視聴者からのわいせつ発言や暴言等に触れさせないようにすべき義務違反があったとして損害賠償を求めた事案(横浜地川崎支判R3.11.30)があります。
同裁判例は、一定の割合でCC、CL、SVを配置して通話をモニタリングし、対応困難な通話を常にチェックしていた点、ルールを策定・周知し、わいせつ電話のSVへの転送、同一人物からの2回目以降の電話の即切断、電話を保留やミュートにしての直接転送の依頼、大声を出すような場合ヘッドセットを外し転送対応・自動音声への切り替えを認めていた点、SVから今後架電しないよう抗議や注意をしていた点等から、事業主の安全配慮義務違反を否定しました。
また、刑事告訴や民事上の損害賠償請求の措置については、事業主が、業務委託を受けている立場にあり、事業主の判断のみでは、強硬な手段をとることは困難であること、問題ある発言すべてに強硬な手段をとることは不可能であり、かえって視聴者の反感を買ってクレームが増加することのおそれなどから、直ちに法的措置をとる義務があるとまでは認められないと判断しています。
いずれの裁判例も、カスタマーハラスメントとなりうる問題の状況について、ルールが整備・周知され、相談・対応の体制があったこと、実際に、責任ある者から顧客への抗議や不当な要求の拒否等の対応が行われていたことが重視されています。
想定される状況について、従業員の安全に配慮するという観点から対応の指針を見直し、ルールを整備しておくことが重要です。
(2024年6月執筆)
(本記事の内容に関する個別のお問い合わせにはお答えすることはできません。)
人気記事
人気商品
執筆者

大西 隆司おおにし たかし
弁護士(なにわ法律事務所)
略歴・経歴
なにわ法律事務所URL:http://naniwa-law.com/
「大阪産業創造館 経営相談室「あきないえーど」 経営サポーター(2012年~2015年3月、2016年~2019年3月、2020年4月~)」、関西大学非常勤講師(2014年度〜2016年度)、関西大学会計専門職大学院非常勤講師(2017年度〜)、滋賀県商工会連合会 エキスパート登録(2013年~)、大阪弁護士会遺言相続センター登録弁護士、大阪弁護士会高齢者・障害者支援センター「ひまわり」支援弁護士。
著書
『特別縁故者をめぐる法律実務―類型別のポイントと書式―』(新日本法規出版、2014年)共著
『法務・税務からみた相続対策の効果とリスク』(新日本法規出版、2015年)相続対策実務研究会代表大西隆司(なにわ法律事務所)編著
『事例でみる事業承継の実務―士業間連携と対応のポイント―』(新日本法規出版、2017年)編著
『〔改訂版〕事例でみるスタンダード相続手続―士業間連携による対応方法―』(新日本法規出版、2018年)編著等
『事例でみる スタンダード債権回収手続―専門家の視点と実務対応―』(新日本法規出版、2019年)編著
『相続対策別法務文例作成マニュアル―遺言書・契約書・合意書・議事録―』(新日本法規出版、2020年)著等
執筆者の記事
執筆者の書籍
関連カテゴリから探す
-

-

団体向け研修会開催を
ご検討の方へ弁護士会、税理士会、法人会ほか団体の研修会をご検討の際は、是非、新日本法規にご相談ください。講師をはじめ、事業に合わせて最適な研修会を企画・提案いたします。
研修会開催支援サービス -