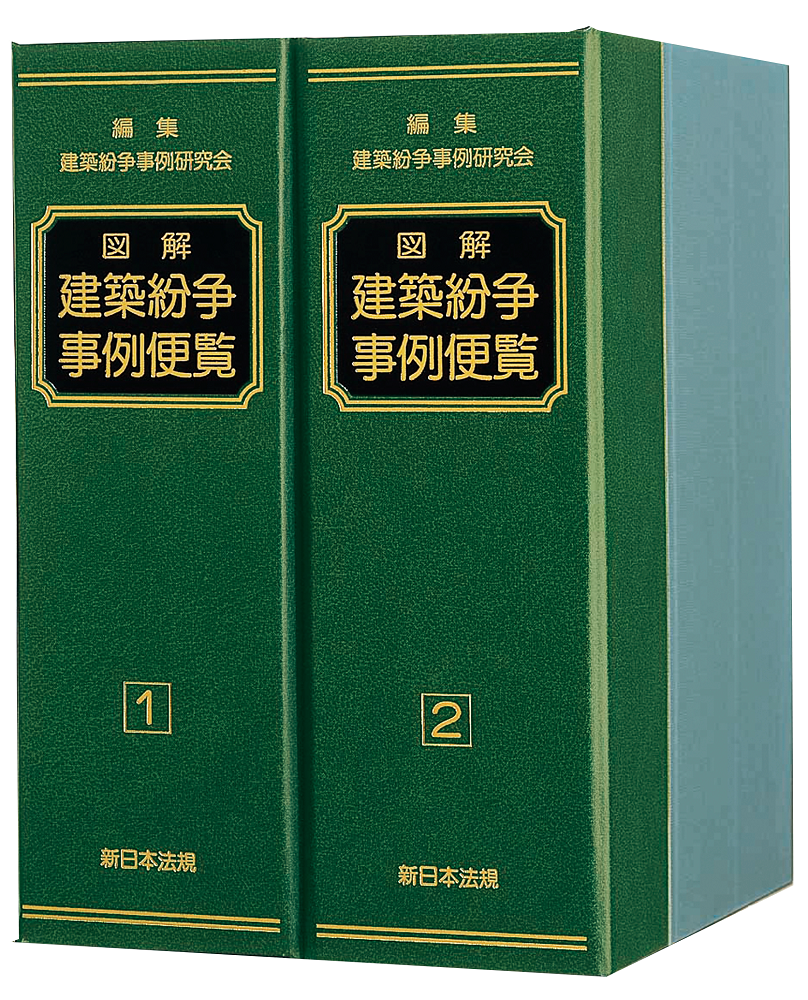建設・土木2022年07月25日 ようやく始まる全国的な盛土規制 執筆者:日置雅晴

1年前に発生した熱海の土石流災害は記憶に新しい災害ですが、その原因とされたのが上流部への盛土と称する土砂や廃棄物等の堆積が放置されていたことでした。
原因とされた山中には高さ数十メートルもの土砂の堆積がなされており、その危険性は以前から指摘されていたと言われていますが、行政や土地所有者などが積極的に対処することはなく、長年危険性が解消されてこなかった結果があのような悲惨な被害につながったと言われています。
以前から都市計画法の中の開発許可という制度により、盛土などの土地の造成行為は一定の範囲では規制されていましたが、都市計画法では、許可対象の面積要件(地域により異なるが、都市計画区域外では1ha以上が対象)が定められており、規制対象面積以下には規制が及ばないことや、開発対象区域をいくつかに区分して許可を回避するなどの脱法的な手法が問題になったりしてきました。
しかし、そもそも都市計画法上の開発許可は、原則として建築物の建築を目的とする造成行為が対象とされていたことから、建築行為を目的としない造成行為、例えば残土をただ処分するためであるとか、資材置き場として使うような場合には規制対象にならないといういわば法規制の空白地帯という問題がありました。
ほかにも森林法や廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃掃法)による規制などもありましたが、いずれもただの盛土に対しては十分な規制が出来ない状態でした。
これまでもこのような法の空白領域の問題について、問題が集中して生じていた自治体では、建設残土に着目してその投棄を規制したり、建築行為に該当しないトレーラーハウスの設置を規制したりするなど、様々な保護法益を工夫して一定の規制をしたりするなどの対応はしてきました。静岡県でも、静岡県土採取等規制条例の届出の対象にはなっていたようです。
しかし条例で規制している限りでは、全国一律規制ではなく、どうしても規制の甘い地域が生じるとそこに問題が集中したりしてきました。
またどうしても条例では、法律ほどの強力な規制や罰則を定めることについて抑制的な規制がほとんどです。
静岡の条例でも規制は単なる届け出にとどまり、実効性のある規制はなされていませんでした。条例でも罰則を定めることは可能ですが、そもそも地方自治法14条第3項の規定により、条例で規定できる罰則は2年以下の懲役・禁錮、100万円以下の罰金、拘留、科料もしくは没収(以上刑罰)又は5万円以下の過料に限定されており、また単なる届け出違反程度にあまり重い罰則を科することも困難であり、法規制ほど厳しい規制が出来ていなかったのが現実で、結果的に災害を防げませんでした。
このような問題をふまえて、令和4年5月に宅地造成等規制法の改正として全国的、包括的な盛土規制が定められました。(施行は1年以内)
改正法は、土地の用途にかかわらず危険性のある盛土行為を規制対象とするもので、都道府県知事が市町村の意見を聞いた上で規制区域を定め、その区域内での盛土行為を許可行為とするものです。
許可に際しては、災害防止のための技術基準を定め、実際の安全性確保のための検査制度なども定めています。また合わせて土地所有者の管理責任を明確にするとともに、原因行為者に対しても行政命令を出せる規定が定められています。
また罰則としては懲役3年、罰金1000万円、法人には罰金3億円と条例で定めることが出来る上限より厳しい罰則が定められました。法人に重い罰金が定められたことも、盛土行為が実質的に残土や廃棄物の不適切な処分という企業の営利行為として行われてきたことへの対処と言えます。
すでに全国的には問題のある盛土が相当存在しているようですが、熱海のような悲劇を繰り返さないためにも、早急に規制対象区域を定め規制の実効性を確保するとともに、すでに存在している盛土についても危険性を厳しくチェックし、速やかに必要な安全対策を取るべきことが求められます。
(2022年7月執筆)
関連法令(PICK UP! 法令改正情報)
宅地造成及び特定盛土等規制法の一部改正(令和4年5月27日法律第55号 公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行)
人気記事
人気商品
関連商品
執筆者

日置 雅晴ひおき まさはる
弁護士
略歴・経歴
略歴
1956年6月 三重県生まれ
1980年3月 東京大学法学部卒業
1982年4月 司法習修終了34期、弁護士登録
1992年5月 日置雅晴法律事務所開設
2002年4月 キーストーン法律事務所開設
2005年4月 立教大学法科大学院講師
2008年1月 神楽坂キーストーン法律事務所開設
2009年4月 早稲田大学大学院法務研究科教授
著書その他
借地・借家の裁判例(有斐閣)
臨床スポーツ医学(文光堂) 連載:スポーツ事故の法律問題
パドマガ(建築知識) 連載:パドマガ法律相談室
日経アーキテクチャー(日経BP社) 連載:法務
市民参加のまちづくり(学芸出版 共著)
インターネット護身術(毎日コミュニケーションズ 共著)
市民のためのまちづくりガイド(学芸出版 共著)
スポーツの法律相談(青林書院 共著)
ケースブック環境法(日本評論社 共著・2005年)
日本の風景計画(学芸出版社 共著・2003年)
自治体都市計画の最前線(学芸出版社 共著・2007年)
設計監理トラブル判例50選、契約敷地トラブル判例50選(日経BP社 共著・2007年)
新・環境法入門(法律文化社・2008年)
成熟社会における開発・建築規制のあり方(日本建築学会 共著・2013年)
建築生産と法制度(日本建築学会 共著・2018年)
行政不服審査法の実務と書式(日本弁護士連合会行政訴訟センター 共著・2020年)
執筆者の記事
-

-

団体向け研修会開催を
ご検討の方へ弁護士会、税理士会、法人会ほか団体の研修会をご検討の際は、是非、新日本法規にご相談ください。講師をはじめ、事業に合わせて最適な研修会を企画・提案いたします。
研修会開催支援サービス -

Copyright (C) 2019
SHINNIPPON-HOKI PUBLISHING CO.,LTD.