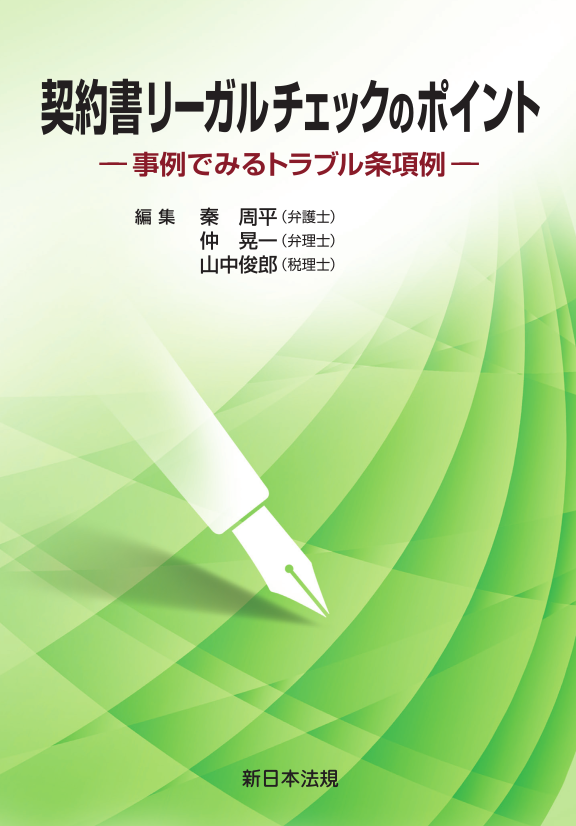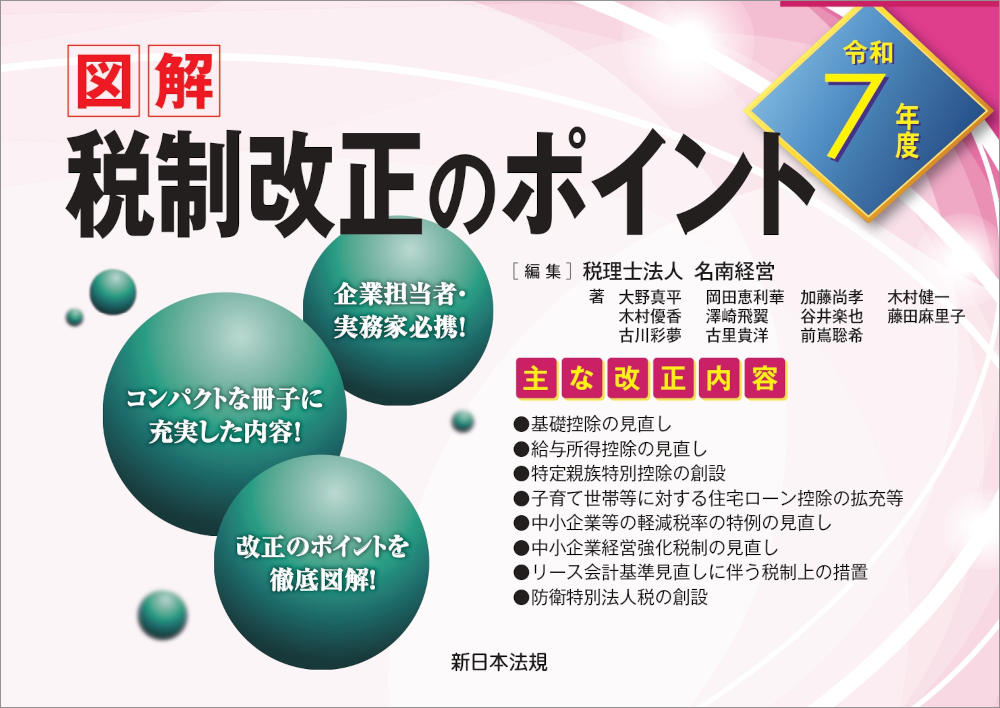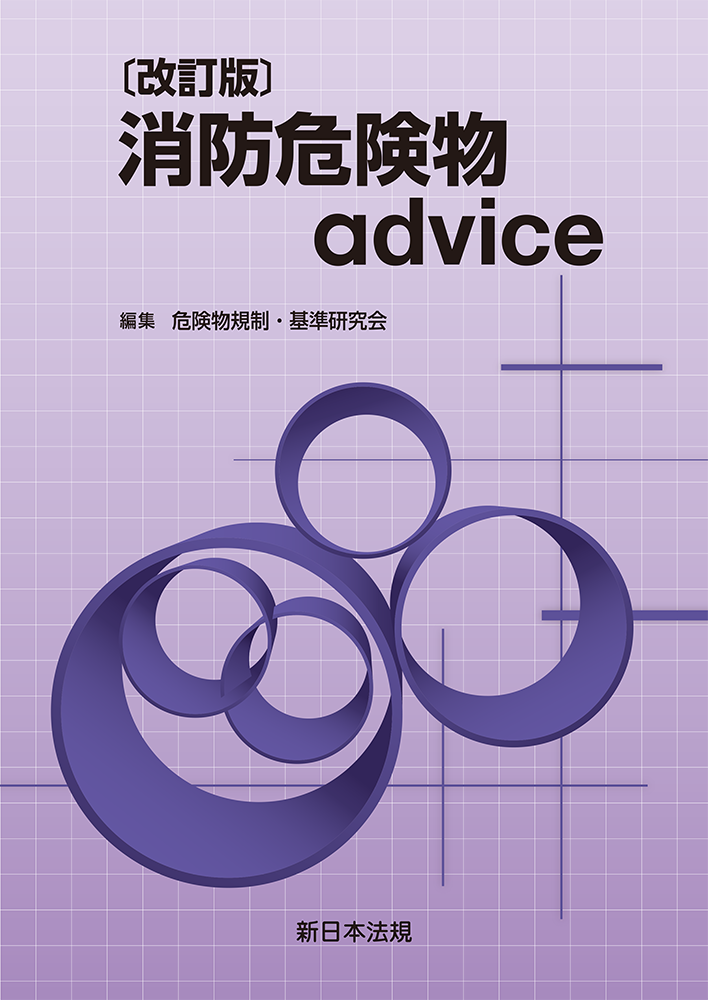民事2020年04月01日
清算条項は、会社と退職者との間の債権債務関係が存在しないことを確認する内容に留まり、原告会社の役員及び従業員との清算を包括する清算条項が合意されたことを認めるに足りないとした事例 (東京地判平29・3・7(平27(ワ)26518)
契約書リーガルチェックのポイント-事例でみるトラブル条項例-
編集者:秦周平 仲晃一 山中俊郎
執筆者:奥山隆輔 北野了考 田尾賢太 塚元健 秦周平 髭野淳平 吉田将樹 田中勲 仲晃一 山中俊郎
原告会社と元従業員である被告間の労働審判で成立した調停で、被告は、解雇に係る紛争解決のため、原告会社の役員や従業員と接触しないことを約して解決金の支払を受けたにもかかわらず、原告代表者らに対する損害賠償請求訴訟を提起したとし、原告会社とその代表者である原告が被告は清算条項に違反するとして、不法行為等に基づく賠償請求をした。
裁判所は、被告の訴訟提起などが、前件調停の清算条項、口外禁止条項、接触禁止条項のいずれにも違反したことにはならないとして、不法行為を否定した。
<問題となった条項>
接触禁止条項(前記問題となった条項の4項)は設けられていたものの、清算条項(前記問題となった条項の8項)は、原告会社と被告との間の債権債務関係が存在しないことを確認する内容となっており、原告らが主張する完全清算条項が合意されたことを認めるに足りる的確な証拠はない。
この点につき、原告らは、前件調停において、原告会社が被告に対して労働審判において支払われる解決金の平均額(139.7万円)を大きく超える1,350万円の解決金を支払ったのは、原告会社との関係のみならず、同社の役員及び従業員と被告との間の一切の紛争を解決する趣旨であった旨主張する。
しかし、前件調停において原告会社が被告に支払った金額は、被告の1年分の年俸(約760万円)に被告が主張した割増賃金(約600万円)を加えた金額を基準に算定されたものであることに照らせば、上記解決金を原告会社が被告に支払ったことをもって、直ちに、原告らの主張する完全清算条項が合意されたことを認めるのは困難である。そうすると、原告らが主張する上記事情は、あくまで原告会社が上記解決金の支払を受け入れた主観的な意図又は動機にすぎないから、前件調停において、明文で規定されている接触禁止条項を超えて、原告会社と被告との間で、原告会社の役員及び従業員との間の一切の紛争が解決したことを内容とする完全清算条項が合意されたものとは認められない。
1 清算条項の射程範囲
紛争解決を目的とした示談書、和解契約書、調停条項などを作成するときに、後日、当事者間で紛争が蒸し返されることを防止するため、清算条項を設けることが一般的です。
しかし、本Caseのように、会社との関係で和解が成立しても、その清算条項の効果は、当該会社の役員や従業員に当然に及ぶものではありません。
本Caseでは、原告会社は、前件調停において、原告会社と被告との間に限らず、原告会社の役員及び従業員と被告との間についても、前件労働審判の審判対象とされた紛争(被告の解雇)に関する債権債務関係が存在しないことが確認されて、完全清算条項が合意されたと主張しましたが、裁判所は、原告会社と被告との間の清算に留まるとしています。
本Caseのように和解後、和解した当事者以外に紛争が飛び火するおそれが予想される場合、清算条項の効果が及ぶ対象者を追記することで、後日の紛争を抑止することにつながります。もっとも、そのような清算条項を設けたとしても、理論的には、締結当事者間(本Caseでは原告会社と被告)にしか効力が及ばないため、後日、役員や従業員を相手方とする紛争が再燃するおそれが高い場合は、当該役員や従業員を利害関係人として手続に関与させることを検討する必要があります。
2 「本件に関し」「本件紛争に関し」
清算条項を設ける場合、一般的には「本件に関し」、「本件紛争に関し」といった文言を付して清算条項の効力が及ぶ権利義務関係の範囲を特定しますが、この文言をあえて記載しない形で、和解以前に生じた当該当事者間における債権債務関係の一切を清算する、といった方法(「完全清算条項」と呼ぶ場合があります。)は有用とされます。裁判所も、特段の事情がない限り、このような完全清算条項も有効としています。
もっとも、「本件に関し」や「本件紛争に関し」との文言を付さない完全清算条項で和解をした場合でも、和解の合理的解釈として、完全清算条項の対象となるのは、当該和解の時点で通常予測できる範囲の紛争に限定される余地があると判断した判例もあるので注意が必要でしょう(東京地判平16・11・18(平14(ワ)20279・平15(ワ)946))。
3 口外禁止条項、接触禁止条項
清算条項と同じく、後日の紛争予防を目的として、先に起こった紛争の内容や和解内容を他に口外することを禁じる条項(口外禁止条項)や、当事者間の接触を禁じる条項(接触禁止条項)を規定することがあります。
口外禁止や接触禁止を明記することは、当事者に対する抑止力として一定の効果はありますが、限界があることにも注意が必要です。
本Caseでは、口外禁止については、「一般に、調停又は裁判上の和解の内容として、当事者間で一定の事項について第三者に口外しない旨の条項が設けられたときは、その例外を許容する条項が明文で定められていなくても、自己の正当な権利行使のために当該事項を第三者に示す必要が生じたり、公法上の義務に基づいて当該事項を第三者に開示する必要がある場合には、正当行為として、当該事項を開示する必要性が認められる範囲の者に対して当該事項を開示することが許容されるものと解される。」としています。
また、接触禁止についても、「一般に、調停又は裁判上の和解の内容として、当事者が、今後直接又は第三者を介して、一切の連絡や接触をしないことを合意した場合であっても、当事者の合理的意思として、特段の事情のない限り、裁判や調停等の公の手続を利用する場合や、弁護士等の公正な第三者を通じて連絡することは、条項によって禁止されていないと解するのが相当である。」としています。なお、接触禁止条項や口外禁止条項に違反した事実を立証することができたとしても、次に、義務違反によって蒙った実損害を立証することは実務上難しいことから、違約金条項を定めておくことも検討すべきでしょう(設問13参照)。
記事の元となった書籍
人気記事
人気商品
-

-

団体向け研修会開催を
ご検討の方へ弁護士会、税理士会、法人会ほか団体の研修会をご検討の際は、是非、新日本法規にご相談ください。講師をはじめ、事業に合わせて最適な研修会を企画・提案いたします。
研修会開催支援サービス -

Copyright (C) 2019
SHINNIPPON-HOKI PUBLISHING CO.,LTD.