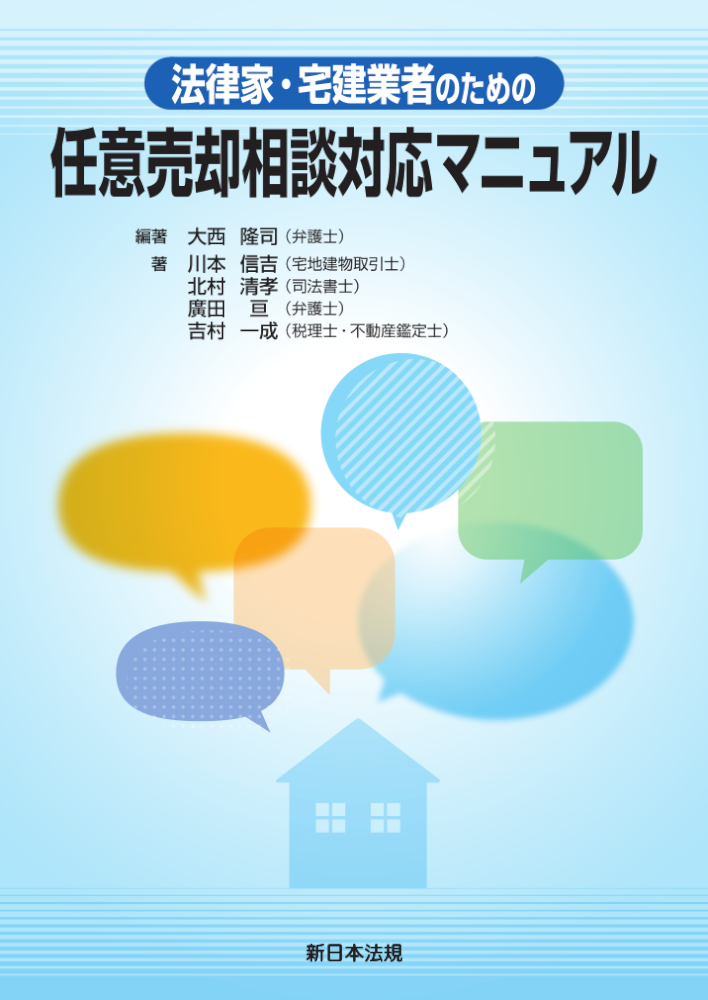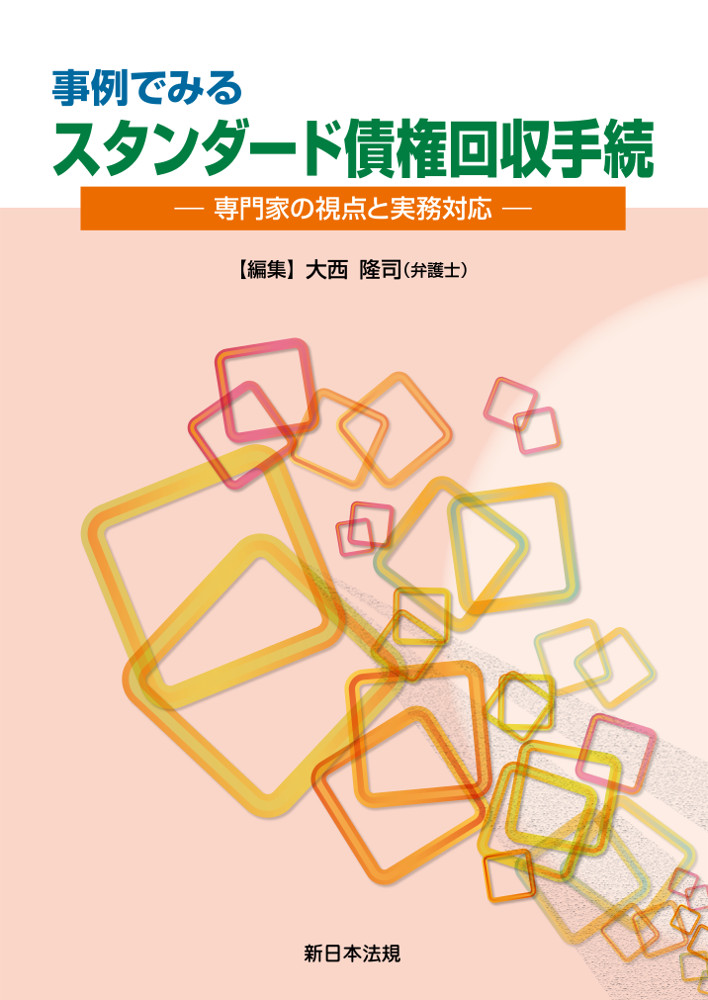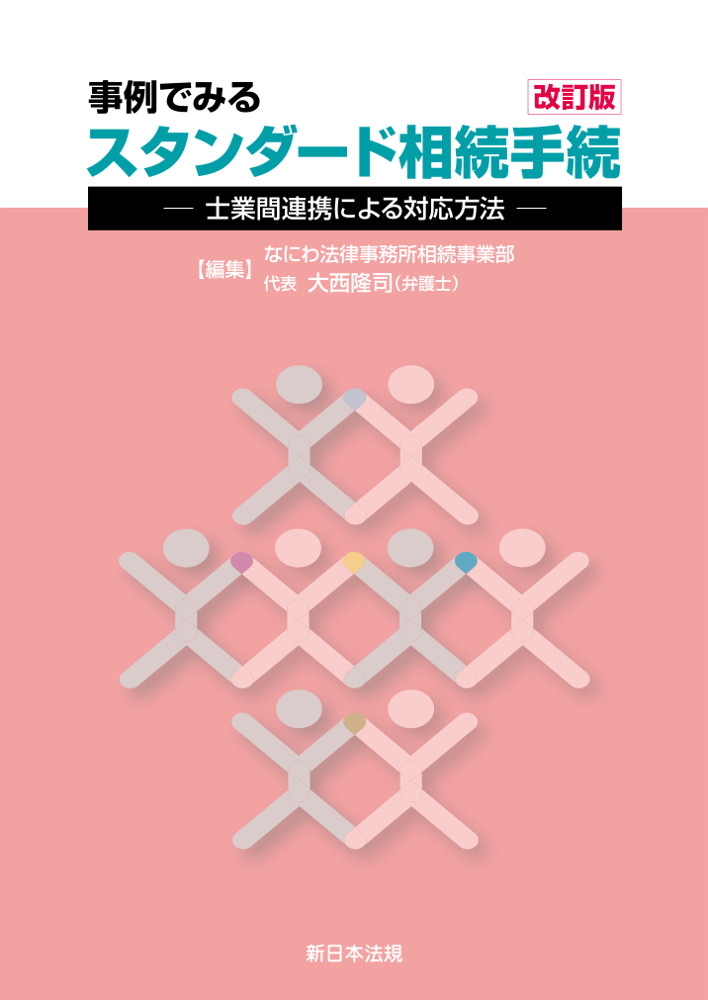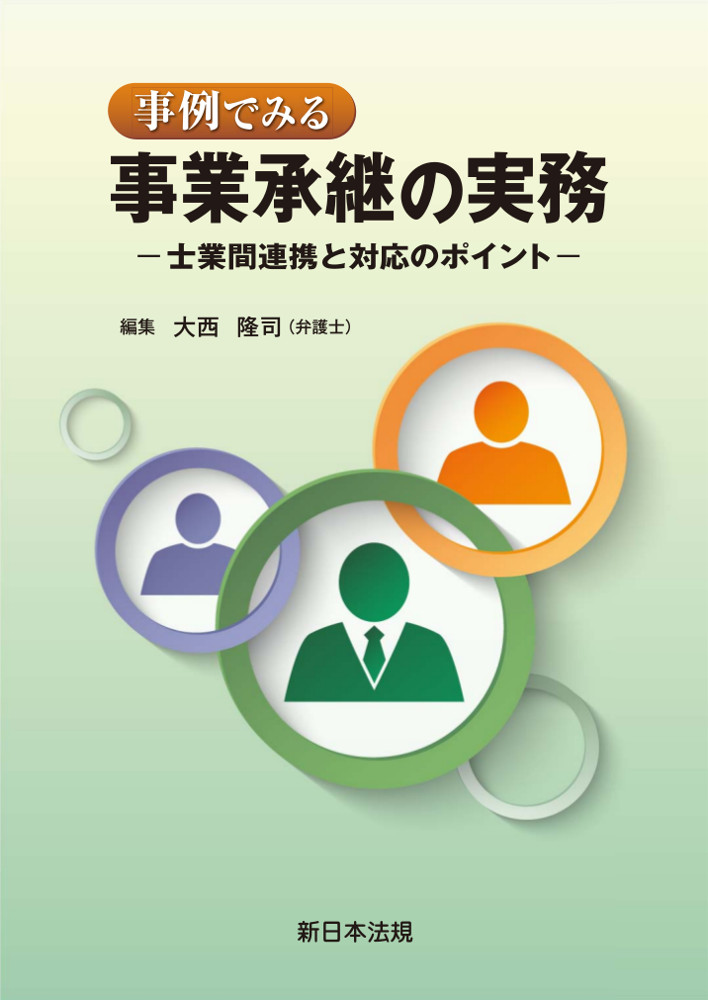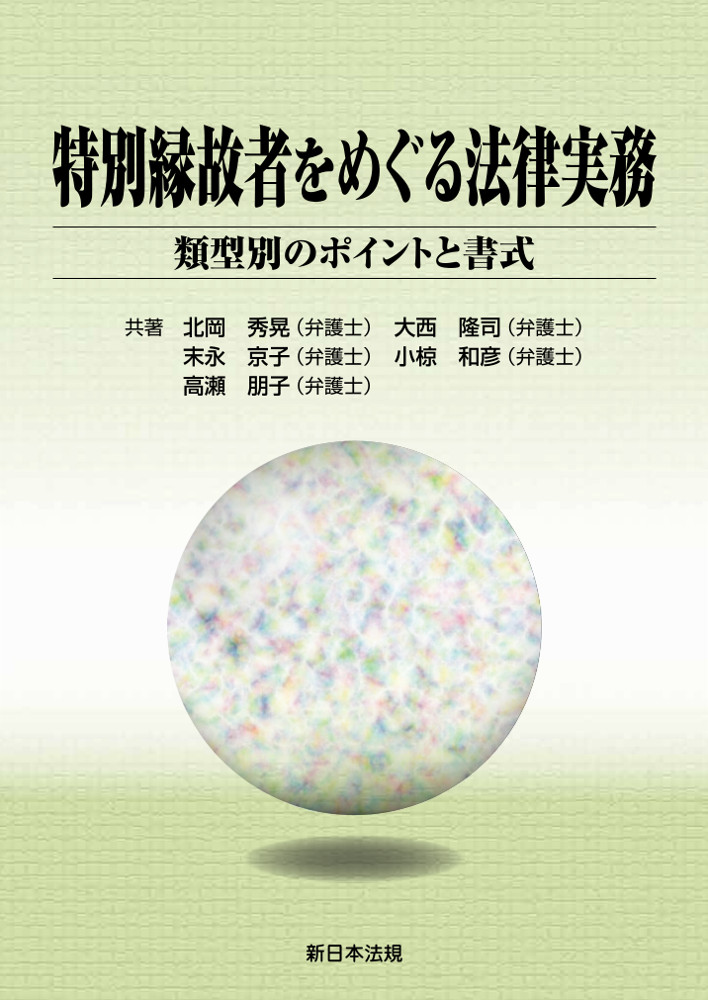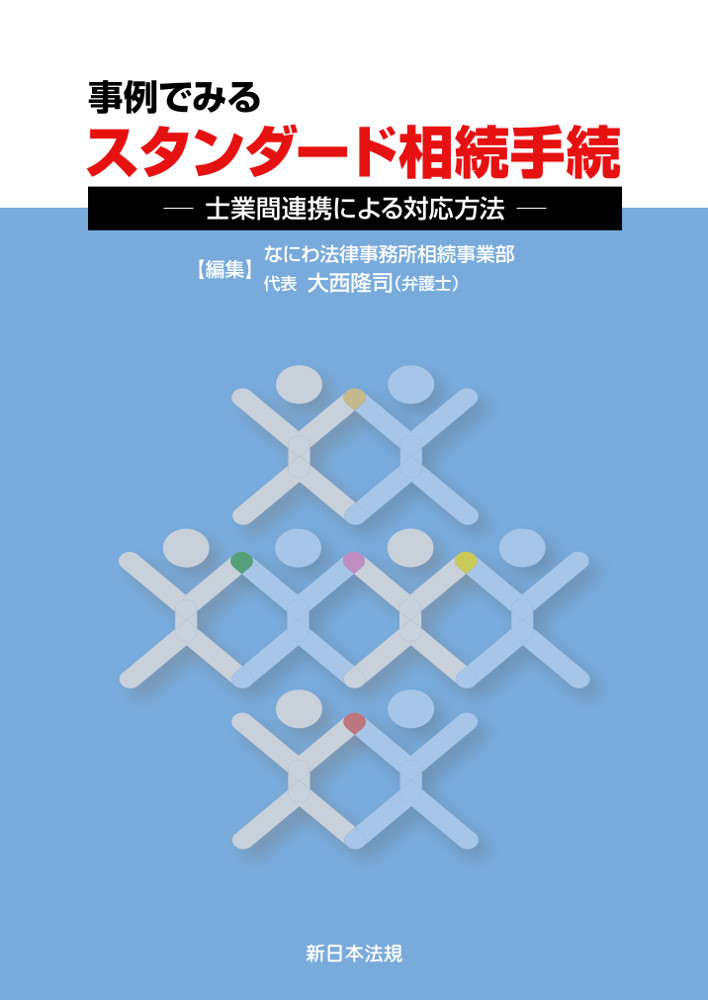企業法務2025年10月23日 昇進・昇格を訴訟で請求することができるか 執筆者:大西隆司

1 昇進・昇格をめぐる争いの救済方法
昇進は、企業組織の指揮命令系統上の役職の引き上げ(下の職位から上位の職位に移動させること)をいい、昇格は職能資格制度などにおける職務資格の引き上げをいいます。
一般的に、昇進・昇格については、使用者の決定によってはじめて起こる制度で、労働者の能力や適性を総合的に判断する人事事項として使用者の裁量に服するとされています。
降格の場合は、その処分等の違法性を争うことで、元の役職や元の職務資格の確認請求の形がとりやすいのですが、昇進・昇格の決定のないことについて争う場合、昇進や昇格した地位の確認請求までできるでしょうか。
2 差額賃金等の支払請求にとどまる事例
この点、生命保険会社が既婚者である者を昇給・昇格において違法に差別するなどしたとして、労働契約又は労働基準法(以下「労基法」という。)13条後段に基づき差別がなければ到達していた資格、地位にあることの確認と、差額賃金ないしは差額賃金相当損害金等の金員の支払を求めた事案があります(大阪地判H13.6.27)。
同裁判例は、既婚者であることを理由として、一律に低査定を行うことは、個々の労働者の業績、執務、能力に基づき人事考課を行うという人事権の範囲を逸脱するもので不法行為となり、標準者との差額賃金相当の損害賠償を認めています。
しかし、昇格した地位にあることの確認請求についてはこれを否定しています。
その理由は、会社の昇格が各年の人事考課によるもので、会社の裁量権の行使によって決せられ、原則として会社による昇格決定が必要であるとする点と会社による昇格決定は、既婚者差別に基づく違法(憲法14条、労基法3条、民法90条)なものであるとの主張によったとしても、同法の中に無効となった部分を補充しうる具体的な昇格の基準を求めることはできないとする点にあります。
同裁判例から、昇格した地位にあることの確認請求を行うためには、単に人事考課等の違法性を主張するだけでなく、就業規則や労働慣行などにより、昇格する基準を明らかにすることや、基準を満たす者が機械的に昇格をしていることなどの事情について、主張立証する必要があることがわかります。
3 昇格請求まで認めた事例
信用金庫の女子職員の昇格について、評定者の幹部職員が同期同給与年齢の男性職員を特に人事考課において優遇していたとし差別的取扱いを認め、昇格したことを理由に月額差額賃金及び差額退職金のほか、不法行為に基づく慰謝料、弁護士費用等の損害賠償請求を認めた事例(東京高判H12.12.22)があります。(なお、昇進請求については、職務能力と役職(職位)への配置の問題であるとして、否定されています。)
同裁判例は、当該企業における資格の付与が賃金額に連動しており、かつ、資格を付与することと職位につけることとが分離されている場合には、資格の付与における差別は、賃金の差別と同様に観念することができるとして、特定の資格を付与すべき基準が定められていない場合であっても、資格の付与につき差別があったと判断される程度に、一定の限度を超えて資格の付与がなされないときには、労働基準法13条ないし93条の類推適用により、その限度を基準として資格を付与されたものとして扱うことができるとしています。
具体的には、女性職員に対しても男性職員と同様な措置を講じられたことにより、同期同給与年齢の男性職員と同様な時期に副参事昇格試験に合格していると認められる事情にあるとき、副参事試験を受験しながら不合格となり、従前の主事資格に据え置かれるというその後の行為は無効となって、副参事の地位に昇格したのと同一の法的効果を求める権利を有すると判断されました。
以上のように、これまでの裁判例では、昇進請求までは認められていませんが、昇格請求については、差別的取り扱いを具体的に立証することにより、昇格の基準までが立証できる場合に認められる可能性があることがわかります。
(2025年10月執筆)
(本記事の内容に関する個別のお問い合わせにはお答えすることはできません。)
人気記事
人気商品
執筆者

大西 隆司おおにし たかし
弁護士(なにわ法律事務所)
略歴・経歴
なにわ法律事務所URL:http://naniwa-law.com/
「大阪産業創造館 経営相談室「あきないえーど」 経営サポーター(2012年~2015年3月、2016年~2019年3月、2020年4月~)」、関西大学非常勤講師(2014年度〜2016年度)、関西大学会計専門職大学院非常勤講師(2017年度〜)、滋賀県商工会連合会 エキスパート登録(2013年~)、大阪弁護士会遺言相続センター登録弁護士、大阪弁護士会高齢者・障害者支援センター「ひまわり」支援弁護士。
著書
『特別縁故者をめぐる法律実務―類型別のポイントと書式―』(新日本法規出版、2014年)共著
『法務・税務からみた相続対策の効果とリスク』(新日本法規出版、2015年)相続対策実務研究会代表大西隆司(なにわ法律事務所)編著
『事例でみる事業承継の実務―士業間連携と対応のポイント―』(新日本法規出版、2017年)編著
『〔改訂版〕事例でみるスタンダード相続手続―士業間連携による対応方法―』(新日本法規出版、2018年)編著等
『事例でみる スタンダード債権回収手続―専門家の視点と実務対応―』(新日本法規出版、2019年)編著
『相続対策別法務文例作成マニュアル―遺言書・契約書・合意書・議事録―』(新日本法規出版、2020年)著等
執筆者の記事
執筆者の書籍
-

-

団体向け研修会開催を
ご検討の方へ弁護士会、税理士会、法人会ほか団体の研修会をご検討の際は、是非、新日本法規にご相談ください。講師をはじめ、事業に合わせて最適な研修会を企画・提案いたします。
研修会開催支援サービス -