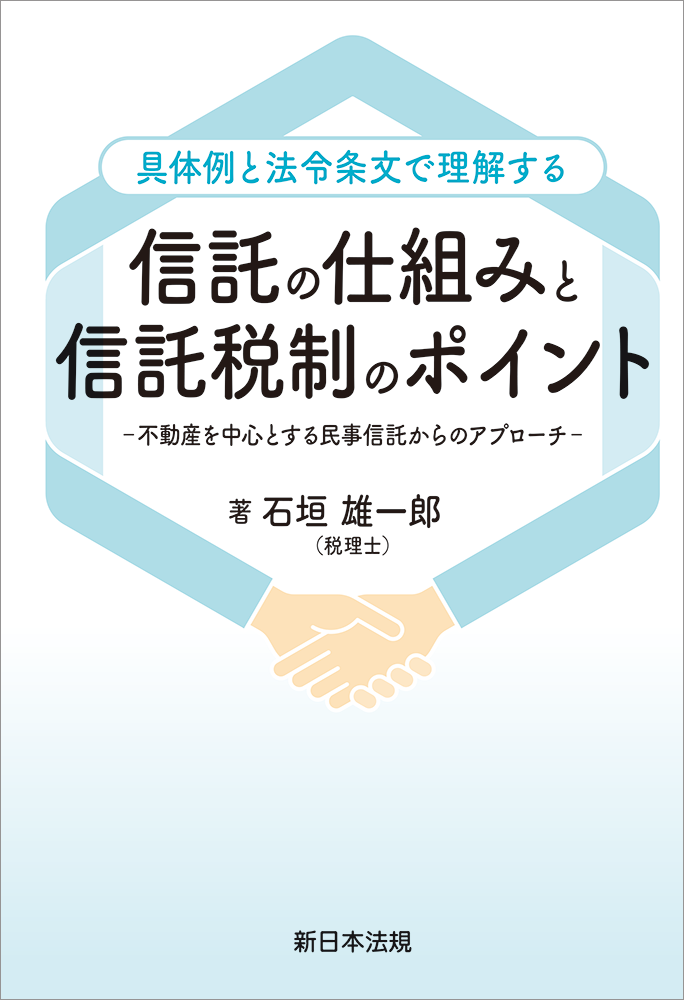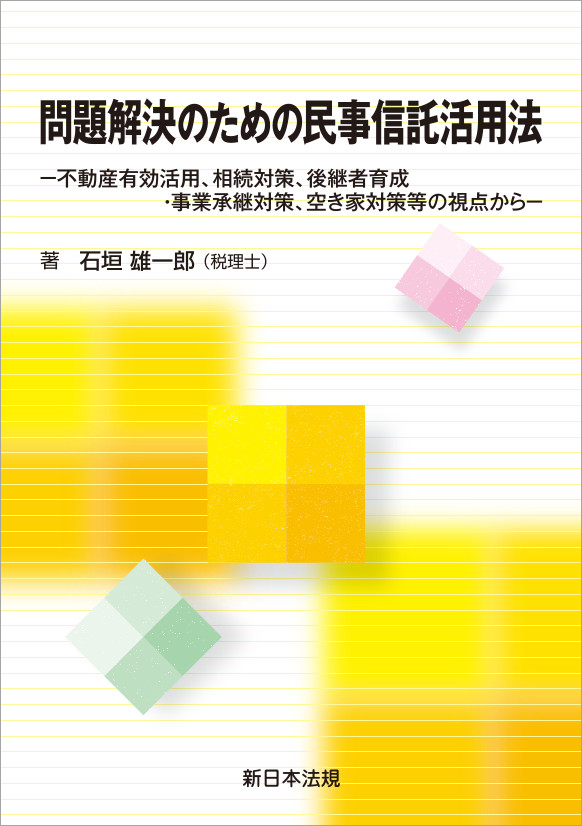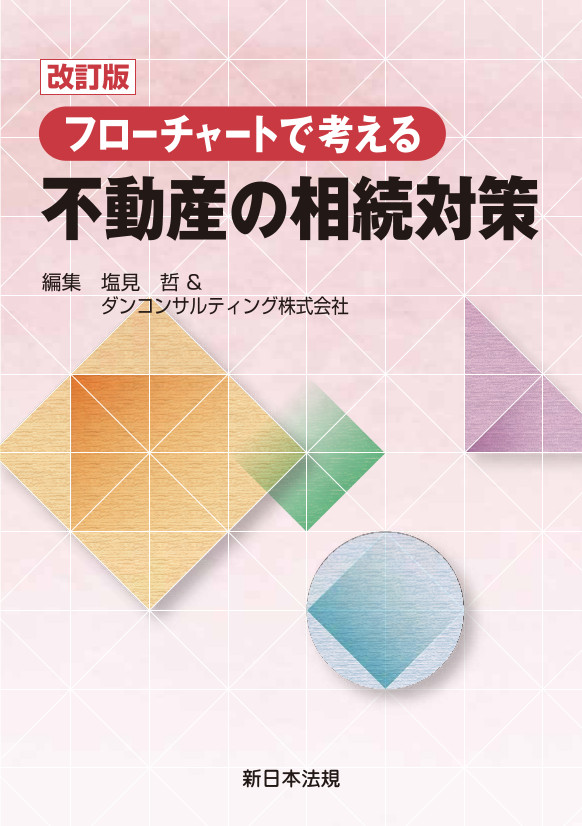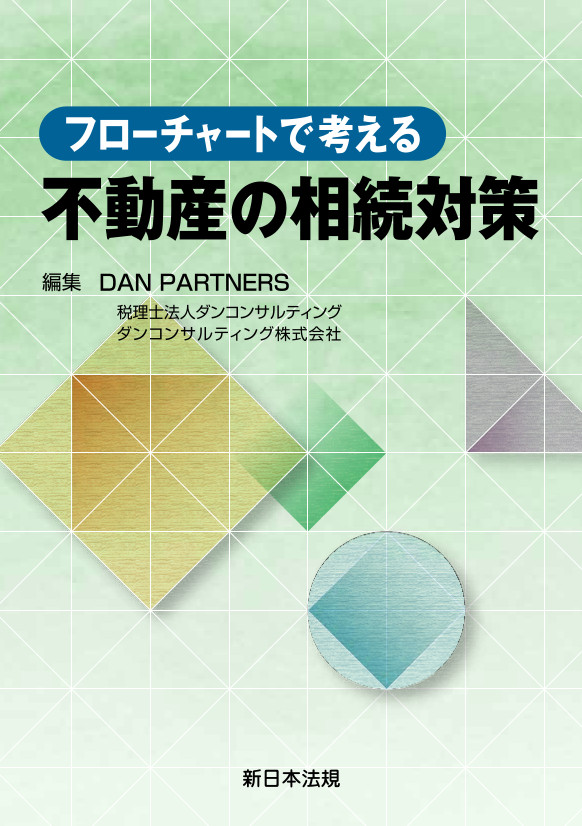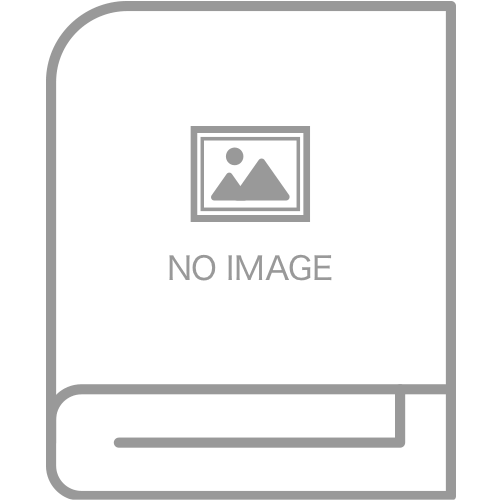民事2025年11月18日
特別対談企画 生活の知恵としての信託
新刊書『具体例と法令条文で理解する 信託の仕組みと信託税制のポイント -不動産を中心とする民事信託からのアプローチ-』の発行にあたってー 生活の知恵としての信託
対談者:石垣雄一郎 渡辺資之

信託ナビゲーター・税理士 石垣 雄一郎
新日本法規出版株式会社 営業第一局 渡辺 資之
<本書の執筆動機>
渡辺 この度、弊社から石垣先生ご執筆の3作目となる『具体例と法令条文で理解する 信託の仕組みと信託税制のポイント-不動産を中心とする民事信託からのアプローチ-』(以下本書といいます。)は、企画から3年を経てようやく発行の運びとなりました。企画段階からご一緒させていただいて、私としてはひとまず肩の荷がおりました(笑)。先生の今のお気持ちをお聞かせください。
石垣 思いのほか時間がかかってしまい、ご心配をおかけしました。そうした状況にもかかわらず、関係者の皆様方には、粘り強くご尽力を頂き、上梓できましたこと、そして、渡辺さんと共に今日を迎えることができたこと、心から感謝しております。ありがとうございます。
渡辺 では、先ず、先生から、本書の執筆動機から教えていただけますか?
石垣 はい。この3年間、私自身、民事信託(本対談では親族など信頼できる人を受託者とする信託で、信託を業としない人に託するものをいいます。以下同じです。)を含む専門家向けの研修やセミナーを積極的に受講してきました。これらの研修・セミナーでは根拠法令を省略して解説がされることはめずらしくありませんでした。そのため民事信託に詳しくない方が、拠り所となる根拠法令が示されていない研修・セミナーを受講しても、結局、具体的な実践は何もできないと感じました。そもそも、これらの研修・セミナーのねらいは、受講者の実践に手を貸すことを想定したものではなく、一般教養としての信託を広めるためのものだったのかもしれません。私にとっては、専門家向け研修の実態を知る良い機会となりました。こうした経緯の中で、昨年、私は、御社から司法書士向けの民事信託の研修講師のご依頼をいただきました。そのとき受講者が少しでも実務で再現できるように、根拠法令を示した解説を意識するようにしました。お陰様で、受講者の反響が講師の私に気づきを与えてくれました。
渡辺 受講者の反響はどのようなものでしたか?
石垣 ある方は、その方自身、それまで根拠法令を示しながら解説をする研修を受講したことがなかったとのことで、私と似た経験をお持ちでしたが、研修内容には、納得感をもっていただけたようです。また、別の民事信託の実践経験豊富な方は、特に相続税法9条の2(贈与又は遺贈により取得したものとみなす信託に関する権利)各項と、信託法の用語と考え方の違いをご理解していただけたようです(本書第3章参照)。本書が出来上がった際には、また講演に来てください、とありがたいお言葉を頂きました。
渡辺 そうした反響はその研修以外にもありましたか?
石垣 はい、その後、講師を務めさせていただいた不動産関係の専門家向けの研修でも同様の反応がありました。これは終日にわたる研修であるため、受講者はかなりお疲れだったはずですが、主催者の方の受講者全般に対する印象として「皆さん、長時間でしたがとても熱心に聴講されていましたね。」というコメントをいただきました。確かに受講者の質問も多く、私にもその熱が伝わってくる研修でした。
渡辺 研修が、直接、市場の声を聴くマーケティングの場となったわけですね。
石垣 はい。お陰様で、そうなりました。当然の事かもしれませんが、専門家の方々の中には、やはり、根拠となる法令条文を自ら確認しながら専門知識を深めていくことに喜びを感じる方がおられることを実感しました。こうした反響は私が本書を書き上げるモチベーションとして大きな力となりました。
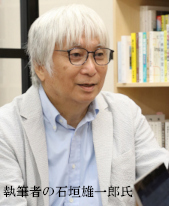
<本書の特徴的なポイント>
渡辺 本書の特徴を教えていただけますか?
石垣 本書タイトルのとおり、特徴は、具体例を提示して、それに当てはまる根拠法令に基づき信託の仕組みと信託税制を解説したことです。これは信託実務に透明性をもたせるためです。また、本書を全て読み終えなければ信託の全体像がつかめない構成にしたくありませんでした。そこで、本書では2つの方法をとりました。1つめは、第1章末尾では、信託の発効から信託の終了、清算結了までの信託の存続期間を時間軸で意識し、信託の全体像を、大づかみで把握できるようにしたことです。2つめは、第2章【ケース1】では、より具体的に全体像を把握できるようにするため、具体例に適用される信託法と信託税制の根拠法令をその利用法とともに解説したことです。同章【ケース2】では、読者の皆様方が信託セミナーの講師を務められることを想定し、信託法に基づく信託の仕組みの全体像を示しました。同章【ケース3】では、第3章・信託税制の相続税法につながる受益者が連続する信託にも言及しています。第3章・信託税制では、信託法を学習しただけではわかりにくい信託税制特有の用語と考え方に言及し、理解の手助けとなるよう努めました。また、信託に対する理解を補完するため、全編を通し、所々に【信託メモ①】から【信託メモ⑭】を記載しました。
渡辺 個別のお話になりますが、本書には、例えば、信託契約をするときに融資を受ける場合の金融機関との関係に配慮された記述もありましたね。
石垣 はい。金融機関の抵当権が付された不動産を信託する場合やこれから信託財産に属する不動産に抵当権を設定する場合については、パートナーともいうべき金融機関との折衝を円滑にしていただくために必要と思われることを記載しました(本書第2章【ケース2】参照)。
<本書が利用される局面>
渡辺 本書はどのような局面で利用されることを想定されていますか?
石垣 信託が高齢者や障碍者の利益を守ることや、財産または事業承継を円滑にするために利用されることは、今更言うまでもありません。
渡辺 いわゆる福祉型信託であるとか財産・事業承継型信託(または後継者育成型信託)と呼ばれているものですね。
石垣 そうです。その点は類書と大きく変わりませんが、本書は不動産信託を中心に解説しています。読者の皆様方が独学で信託実践の基礎を学び、自ら応用へと進めていく過程において本書を利用していただければと考えています。

<信託法改正後に注目され始めた民事信託>
石垣 多くの方にとって、民事信託の利用法とともに、信託を知る機会が増えたため、一般的には、良い傾向だと思っています。
渡辺 これまでに何か民事信託の研修またはセミナーで、エピソードがあればご紹介していただけますか?
石垣 そうですね。忘れられない思い出が1つあります。私が初めて民事信託セミナーの講師をさせていただいたのが2012年、場所は大宮市でした。当時、一般的には、民事信託は、まだ認知されていませんでした。そのセミナーの受講者は、埼玉県を中心に、北関東、長野県の各不動産オーナーでした。セミナー終了後のアンケートでは受講者全員(35名)が民事信託に対して高い関心を示されました。うち2名の方は、すぐに検討したいとのことでその場で面談日が決まりました。ところが、いずれの方も実際にはご相談に来られませんでした。
渡辺 え?どうされたんですか?
石垣 お2人は、それぞれ直前になって、顧問税理士からそうした相談には行くべきではないと、止められたとのことでした。そのうちの1人の不動産オーナーは私からその方の顧問税理士の方に連絡して、話をしてほしいと言われました。
渡辺 その方は民事信託を検討するために説得してほしかったのでしょうか?
石垣 はい、そういうニュアンスでした。そこで、私から電話を入れたところ、その顧問税理士には、信託の知識はないようで、そのようなものは必要ないと取りつく島がなく、説明の機会すら与えていただけませんでした。せっかく信託の基礎知識を身につけた不動産オーナーが民事信託を検討したいと興味をもち、まだ信託を利用することを決めていないにもかかわらず、信託の知識を有しないとおぼしき顧問税理士がその検討機会を阻んだわけです。私は、不動産オーナーのお2人に対し、予め「この相談をきっかけに、顧問税理士の座を獲得しようとするものではない。」と伝えていただくよう言っていただけに残念でした。
渡辺 そのお2人は、信託を検討しようとされていたのにお気の毒でしたね。
石垣 私もそう思いました。これに対し、私は、たとえ結果的に民事信託を利用しないとしても、信託への理解を深めた上で、利用する、しないの判断を、信託の当事者となるべき者、特に委託者となるべき者(本人/a person who creates a trust)がすべきではないかという思いを強くもつようになりました。今、これは私の教訓となっています。
渡辺 その教訓が本書にも反映されているのでしょうか?
石垣 はい、その思いで書かせていただきました。信託を知らずに利用しないことと、知った上で利用しないというのでは意味が全く異なります。信託を知っていれば利用できたかもしれない人が、知らずに利用しなかったことにより、より良い人生を送れたにもかかわらず、その実現がかなわずに、人生を終えてしまうという事態だけは避けなければなりません。また、商事信託(本対談では信託会社、信託業を営む金融機関が受託者となる信託をいいます。以下同じです。)、後見制度といった他の方法を検討するきっかけにもしていただきたいのです。
渡辺 なるほど、先生が「信託の民主化」を提唱されるのには、そうした思いが根底にあるんですね。
<民事信託に起因して生じる様々な問題に対して>
渡辺 ところで、最近、信託に関する訴訟を含む様々な問題が露呈してきたと感じておりますが、先生の所見はいかがですか?
石垣 確かに、民事信託を利用するケースが増えるにつれて、問題が発生しています(本書第1章参照)。民事信託に関するトラブルの多くは、信託の当事者がその内容を把握せずに、人から勧められるままに、信託契約を締結している実態が一部にあることです。通常、どのような契約の当事者であっても、その契約内容を把握した上で契約を締結すべきですが、民事信託に関する信託契約の締結については、残念ながら、必ずしもそうなっていない現実があるようです。この現実があることは、ご指摘の問題発生と無縁ではありません。この状況を放置することは、これまで先達が脈々と築いてきた信託制度全体に対する信頼性を損うことになります。私たちは、そうならないよう努める責任があります。
渡辺 そうした背景を踏まえて、本書は、信託の全体像を学ぶことで問題やトラブルをできる限り回避して、信託の認知度を健全に高めていこうとする思いによって出来上がっているわけですね。
石垣 はい、そうなるよう努めました。
<筆者が民事信託の実践で得られた教訓>
渡辺 以前、石垣先生ご自身も実際に民事信託を活用されておられるとお聞きしておりましたが、信託が難しいと思われる要因は何だとお考えですか?
石垣 10数年前になりますが、私は、民事信託が私にとって必要なものなのか、私にとって必要でなくても、どのような方にとって必要なものなのかを理解するため、書籍を限定して初めて信託を学びました。そして、私と家内にとっては、民事信託は有用であるとその必要性を感じたため、時期は異なりますが、それぞれ別の不動産信託の受託者に就きました。いずれも、親を委託者兼受益者とし、子を受託者とする、いわゆる福祉型信託です。お陰様で、受益者(親)生存中に大きな問題が生じることも、受益者(親)が亡くなった後も親族間の争いごとが生じることもなく、信託の終了と清算結了を迎えることができました。そのため、幸いにも、受託者である私は、民事信託が難しいものと感じたことはありません。改めて家内にも確認しましたが、同じ感想でした。
渡辺 そのご経験から得られた教訓はありますか?
石垣 はい、あります。信託を学び始めてわかったことですが、民事信託は、富裕層でない、一般の方にとっても大いに役立つものだということでした。その上で、大切なことの1つめは、信託の当事者である委託者と受託者との間に信頼関係が欠かせないこと、2つめは、委託者兼受益者(本人)に判断能力があるときは、受託者は、その意向を尊重すること、そして、本人への報告・相談を怠らないこと、3つめは、本人の判断能力が低下、または、なくなれば、信託契約で決めた信託の目的を達成するために、本人であればどのような意向を持つかに配慮して「必要な行為」をすること、4つめは、相続人に対する財産分割に配慮すること、これらの大切さを信託の実践によって教えられた気がします。
渡辺 なるほど。つまり、その前提があれば、信託は決して難しいものではいというわけですね?
石垣 はい、そうです。民事信託をするときに欠かせない前提としてこれらの条件を整えて、実践することができれば、先ほどお話しました民事信託に起因して生じる様々な問題は、おそらく大幅に減少するのではないでしょうか。これらの条件を整えずにスタートすれば、民事信託はきっと難しいものとなって、問題が発生する可能性が高まるのではないでしょうか。
渡辺 確かに、その部分は信託の専門的な知識や経験がなくても、大切なことであるとわかります。しっかり胸に刻んでおく必要がありそうですね。
石垣 そう思います。信託をするときは、まず信託の専門知識以前のことが必要であり、かつ、重要だと思います。
<民事信託に取り組む専門家への訴求ポイント>
渡辺 多くの税理士は業務として信託に取り組むことを、その高い専門性と税務リスクから、手を出しにくいと感じているように思います。信託に手を出せないでいる税理士にとって、本書の訴求ポイントは何でしょうか?
石垣 まず、訴求ポイント以前の問題ですが、継続的に信託を修得する熱意のある他の専門職との連携が不可欠です。
渡辺 その連携はコンプライアンス上の問題を考慮されてのことと理解してよろしいですか?
石垣 そういうことです。ただし、顧客のことを考えると、連携先の他の専門職に対し、民事信託の業務を「丸投げ」をすべきではありません。別の言い方をしますと、民事信託をするときは、一時的であっても顧客が信頼を寄せる税理士から顧客自身が切り離されたと感じることがないようにする配慮、すなわち、顧客に寄り添う配慮が必要だと感じます。信託法と信託税制に関する根拠法令は、専門職同士、専門職と利用者、また、利用者(信託の当事者)同士をつなぐ共通言語であり、コミュニケーション・ツールとなって、「丸投げ」を防ぐことにつながります。質と量を勘案して他の専門職の対価を正当に見積もることもできます。専門職は、民事信託の当事者、特に初期段階では委託者となるべき者(本人)が信託の内容を理解し、民事信託を利用すべきかどうかを判断し、利用するとしても、その内容をどうするかを自ら決められるよう顧客をサポートする大切な役割を担っています。この役割を果たすことは、顧客の大きな助けとなるはずです。本書で顧客向けの個別の民事信託セミナーの開催・提供を想定しているのはそのためです(本書第2章【ケース2】参照)。
<信託税制について留意すべきこと>
渡辺 信託税制について、税理士が特に留意すべきことがあればお話していただけますか?
石垣 はい。信託税制は、基本的には、信託法に基づく信託の仕組みを学ぶことによって理解できる制度だということです。信託税制だけを学んでも意味がわかりにくいだけでなく、信託の全体像はつかめません。
渡辺 そうした背景があっても、最近は賃貸不動産に関する信託契約の利用が増加するにつれて、信託行為に基づく所得税や相続税の確定申告をする税理士も増えていき、信託の実践は着実に進んでいるのではないでしょうか?
石垣 おっしゃるとおりです。その一方で、確定申告を行っている税理士の全てが、必ずしも信託法の仕組みを十分に理解しているとは限りません。税理士に限らず、どの専門家や利用者(信託の当事者)であっても、信託法と信託税制を根拠法令に基づき全体像を理解していなければ、実際のところ、不安が残るはずです。しかも信託法の根拠法規を理解しても、信託税制とは用語と考え方に異なる点があり、その点を理解する必要があります(本書第2章、3章参照)。現状では、この点は、民事信託の実務において、相続税法の解釈に、一部、混乱が生じているように思われるため、本書では私なりの解釈を示しました(第3章参照)。
<不動産取引の安全性確保のために>
渡辺 不動産信託が増加している現状を考えると、信託が設定された不動産の取引も増えているということですか?
石垣 はい、そのとおりです。不動産仲介にかかわる宅建士は、自らが顧客に民事信託の提案をしなくても、取引対象の不動産に信託が設定されていることは、今やめずらしくない時代となりました。好むと好まざるにかかわらず、こちらから顧客に対し信託の提案をしなくても、信託は向こうからやって来るというイメージです。信託目録を含む信託の登記の登記事項を理解し、人にわかりやすく説明するには、かかる事項について、信託法と信託税制の根拠法令がどのように適用されるかを、あらかじめ知っておく必要があります。そうすることによって、不動産取引の安全性が確保され、顧客からの信頼獲得につながります(ただし、信託業法の適用を受け、金融庁の管轄下にある信託会社、信託銀行が受託者となる商事信託の受益権取引には既にこうした取引の安全性が確保されています。)。
<信託契約書の定めについて>
渡辺 ところで、以前、営業現場では、信託契約書の作成方法を記載した本をお探しのお客様が数多くおられました。本書ではこの点についてどのように言及されたのでしょうか?
石垣 各分野の領域で、生成AIの利用は、日進月歩で進んでいます。法律行為を文書化する場合の生成AIを使いこなすことは今後の課題として受け止めています。その上で、本書では、信託法に規定のある事項について、信託契約にその定めを設けた場合の根拠条文だけでなく、定めを設けなかった場合にも注目し、その一部ですが、信託法の規定はどのように適用されるのかについても、主な条文を取り上げて言及しました(本書第2章参照)。
<むすびに代えて>
渡辺 最後に、民事信託について先生ご自身が何か感じられていることがありましたら教えていただけますか?
石垣 はい。私は、以前から民事信託において不動産信託を利用するときは、社会に停滞を起こさないという責任感や社会に対する一定の配慮が問題意識として必要と感じています。信託の当事者(委託者と受託者)とその支援をする専門職は、この意識をしっかり持つことが求められていると考えています。
渡辺 今後、信託制度に対応する専門職が果たすべき役割についてお聞かせください。
石垣 はい。多少異論はあるかもしれませんが、民事信託は特定の専門家だけに知識、経験、ノウハウが集中するものであってはならないと思っています。今は、それぞれの立場で、力を合わせて、誰もが信託を知ることができる環境を作り出す必要があるのではないかと考えています。
渡辺 まさに「信託の民主化」ですね。
石垣 そうです。誰もが信託を知ることによって社会全般への普及が進めば、民事信託、商事信託、いずれの信託にかかわらず、利用法にも、さらなる創意工夫が生まれ、より一層の理解者と利用者が増えてくるように思われます。専門職はそれぞれの立場でそうした動きを手助けする重要な役割を担っています。本書がその一助となることを願いながら執筆しました。ですから、1人でも多くの方にお読みいただければありがたいです。そして、最後に、今回、執筆の機会をいただきましたこと、重ねて感謝しております。ありがとうございます。
渡辺 私たちも、誰もが選択肢の1つとして信託を検討いただけるよう1人でも多くの皆様に本書をお届けして参ります。本書が社会に貢献できる1冊となれば、これに勝る喜びはありません。本日はありがとうございました。

(本記事の内容に関する個別のお問い合わせにはお答えすることはできません。)
(2025年11月 対談)
人気記事
人気商品
生活の知恵としての信託 全12記事
- 特別対談企画 生活の知恵としての信託
新刊書『具体例と法令条文で理解する 信託の仕組みと信託税制のポイント -不動産を中心とする民事信託からのアプローチ-』の発行にあたってー - 不動産投資ファンドとは何か?
-会社の資産として保有される信託受益権- - 特別対談企画 生活の知恵としての信託
「信託をしてもしなくても大切で必要な事」とは-不動産管理・仲介会社のあり方を通して考える(後編)- - 特別対談企画 生活の知恵としての信託
「信託をしてもしなくても大切で必要な事」とは-不動産管理・仲介会社のあり方を通して考える(中編)- - 特別対談企画 生活の知恵としての信託
「信託をしてもしなくても大切で必要な事」とは-不動産管理・仲介会社のあり方を通して考える(前編)- - 特別対談企画 生活の知恵としての信託
第二種金融商品取引業の登録をした不動産会社と信託(後編) - 特別対談企画 生活の知恵としての信託
第二種金融商品取引業の登録をした不動産会社と信託(前編) - 特別対談企画 生活の知恵としての信託
~信託契約代理店のコンサルティング業務~ - 特別対談企画 生活の知恵としての信託 ~不動産信託(後編)~
- 特別対談企画 生活の知恵としての信託 ~不動産信託(中編)~
- 特別対談企画 生活の知恵としての信託 ~不動産信託(前編)~
- 特別対談企画 生活の知恵としての信託 ~生命保険信託~
執筆者

石垣 雄一郎いしがき ゆういちろう
税理士、信託ナビゲーター
略歴・経歴
税理士資格取得後、不動産会社で17年間上場企業の新規開拓や中小企業、個人不動産オーナー向けの営業や新規プロジェクトの立ち上げ支援業務を担当。ダンコンサルティング(株)の取締役を経て、現在は、不動産や株式を主とした民事信託等の浸透に関するコンサルティング業務に従事しながら全国各地からの依頼で信託の実践や活用に関する講演活動も行っている。民事信託のスキームの提案を実施し、不動産会社等にも顧問として信託の活用法を具体化する支援を行っている。
執筆者の記事
執筆者の書籍
-

-

団体向け研修会開催を
ご検討の方へ弁護士会、税理士会、法人会ほか団体の研修会をご検討の際は、是非、新日本法規にご相談ください。講師をはじめ、事業に合わせて最適な研修会を企画・提案いたします。
研修会開催支援サービス -