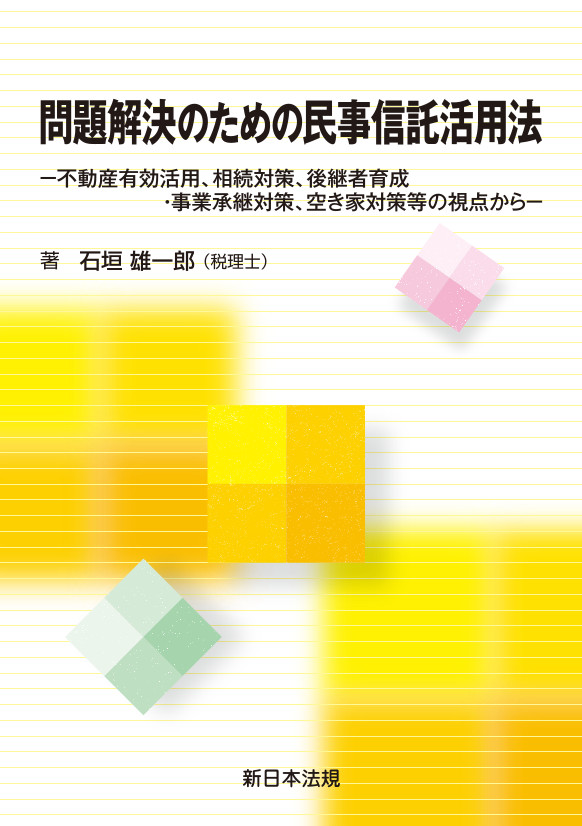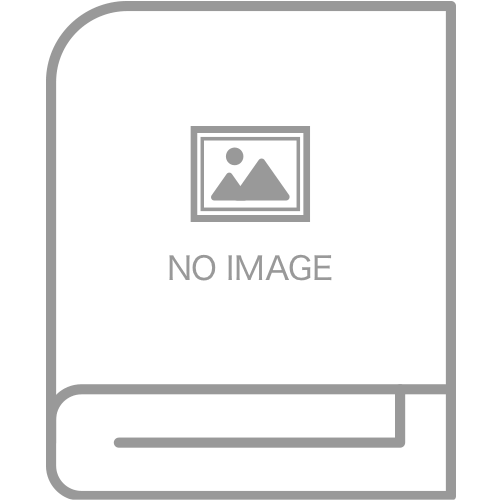民事2019年09月04日 税理士業務の中の民事信託(第1回) 意思能力の有無/前の法律行為が後の法律行為と抵触する場合 民事信託特集 執筆者:石垣雄一郎

あつものに懲りてなますを吹く? そうならないために
裁判年月日:平成30年9月12日
裁判所名:東京地裁 裁判区分 裁判
事件番号:平27(ワ)24934号
事件名:共有権確認等請求事件
裁判結果:一部認容 上訴等 控訴
Ⅰ はじめに
日本では、1922年(大正11年)に信託法が制定されて以来、2006年(平成18年)12月に、初めての改正がありました。そして、2007年(平成19年)9月に改正信託法が施行された後、2018年(平成30年)9月12日、東京地裁によって初の民事信託(関連法規・信託法91条)に関する判決が下されました。
さて、民事信託に取り組む専門家は、年々、増加傾向にあります。特に、税理士は、顧客との関係がスポットよりも継続的にかかわることの方が多いため、信託前の段階から、信託後、そして、その終了にわたって顧客の状況を中長期的に見通せる立場で関わる機会に恵まれています。その機会を生かすかどうかは、顧客の利益に大きく関わってきます。そう考えると、私たちは、信託法、信託税制への理解を深め、その使い方(※1)を知り、顧客のニーズ(潜在的なニーズを含みます。)に応えていかなければならない環境下に置かれていることになります。人工知能(AI)の登場した社会で、私たちが顧客から必要とされる存在になるには、税理士業務をより一層コンサルティング化していく取組みが求められます。信託は、個人的関心の有無にかかわらず、今後、税理士業務の中に入り込んできますので、信託を遠巻きに眺めている状況ではなくなっています。
こうした状況の中で出された標記東京地裁判決は、私たちが民事信託をより良く活用する上でいくつかの大切な教訓を提供してくれました。決して「よくわからない信託をすると、もめごとが起きて、裁判になってしまうことだってあるのだから、信託はやめた方がいい。」と考えるべきものではありません。この考え方が広がると、信託を本当に必要とする人に伝わらなくなってしまうからです。
そこで、本稿では、標記東京地裁判決の民事信託に関する部分に対象を絞り、何が起きてしまったのか、何が問題となってしまったのかを知り、信託への適切なかかわり方を考えるきっかけにしたいと思います。
※1 拙著「問題解決のための民事信託活用法ー不動産有効活用、相続対策、後継者育成・事業承継対策、空き家対策等の視点からー(新日本法規刊)」第1章の各ケースを参照
Ⅱ 問題意識
私たちは、以下、標記東京地裁判決を検討するにあたり、次の2つの問題意識を共有したいと思います。
1 当事者は信託契約の内容をよく把握すること
「委託者となるべき者」と「受託者となるべき者」が信託契約を締結することによって、その効力が生じます(信託法4条1項)。
たとえ、専門家からの助言を受けながら民事信託契約の内容を固めるとしても、「委託者となるべき者」と「受託者となるべき者」は、その内容を十分に理解した上で、その契約を締結しなければなりません。これはどのような契約を締結する場合でも同じです。契約当事者は、いわばこの基本動作を実践することによって、契約内容の適正化とリスクの低減化を図ることができるからです。私たちはこの判決から何を学び、顧客をどうサポートするか、その果たすべき役割を各自で考えてみることにしましょう。
2 本件被相続人が以前から自分の顧客であったとしたなら
標記東京地裁判決の認定事実で示されたこと以外、裁判の関係者でない限り、そこに登場する親子間、兄弟間等の人間関係に何が起きていたのかを知る由もありません。その人間関係のありようがどうであったかは読者の皆様方にお任せします。これから先、しばらくの間、私たちは、登場人物の甲山Bさん(被相続人)がお元気だった頃から、自分の顧客だったとしたなら、どうかかわりをもち、どうサポートすべきであったかを各自で想像してみることにしましょう。
第1回の今回は、甲山Bさん(被相続人)が死因贈与契約書と信託契約書を締結した時にその意思能力があったのかどうかと、平成10年から存在する被相続人の公正証書遺言とこれら2つの契約書の抵触を東京地裁がどう考え、判断したのかを根拠条文に照らして見ていくことにします。
なお、今回からの連載における標記東京地裁判決の出典は、すべてウエストロー・ジャパン(株)による判決のサマリー(文献番号:2018WLJPCA09128002)に基づくものです。
Ⅲ 相続開始に至るまでのあらまし
1 登場人物
標記東京地裁判決の認定事実によると、原告(長男)は、被告に対し、被相続人(父親・委託者兼当初受益者)と被告(二男・受託者)の間で締結された民事信託契約(東京地裁の認定事実は「本件信託」としています。)の無効を主張し、遺留分減殺請求をしました(※2)。
本件の被相続人は、甲山Bさん(父)、相続人は、原告(長男)、被告(二男)、Aさん(二女)の3名です。また、同認定事実では、亡くなったBさんの妻Cさん、信託銀行の担当者、D司法書士、D司法書士を紹介したAさん(二女)の夫の存在を確認できます。
※2 令和元年(2019年)7月1日以後に開始される相続は、「遺留分減殺額」ではなく、「遺留分侵害額」となり、遺留分を侵害された者は、受贈者または受遺者に対し、「遺留分侵害額」に相当する金銭の支払を請求することができるようになりました(民法1046条)。すなわち、「遺留分減殺請求権の行使によって当然に物権的効果が生ずるとされている現行の規律を見直し、遺留分権の行使によって遺留分侵害額に相当する金銭債権が生ずるものとしつつ、受遺者等の請求により、金銭債務の全部又は一部の支払いにつき裁判所が期限を許与することができるようにする。」ことになったのです。
法務省 http://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00236.htmlより
2 Bさんの相続開始まで
標記東京地裁判決の認定事実に基づく本件の事実関係を、以下、日付を意識しながら概観していきましょう。
甲山Bさん(被相続人)は、平成27年1月25日、腰痛で動けなくなり、病院に精査目的で入院しました。
同年1月31日、医師より原告(長男)、被告(二男)、およびAさん(二女)に対し、Bさんが胃がんの末期状態であり数日中にも死亡する可能性があるとの説明がされ、以後は疼痛を緩和する医療方針とされました。
この説明を受けたAさんは、夫を通じD司法書士に相続の対応を依頼し、翌2月1日、D司法書士が原告の病室を訪れました。
同日、Bさん、二男、およびAさんは、D司法書士が持参した死因贈与契約書に署名をし、本件死因贈与契約(東京地裁の認定事実では、「本件死因贈与」としています。)が締結されました。1つは、贈与者をBさん、受贈者をAさんとし、Bさんの全財産の3分の1に相当する財産の贈与に関する死因贈与契約、もう1つは、同日に締結された贈与者をBさん、受贈者を二男とし、Bさんの全財産の3分の2に相当する財産の贈与に関する死因贈与契約でした。
翌2月2日、Bさんは、以前から相続について相談をしていた信託銀行の担当者を病室に呼び、遺産の分割案等について説明を受けました。
なお、Bさんは、遅くとも同年1月7日の時点では信託銀行に相続に関する相談をしていました(信託銀行はBさんの「財産目録」を作成し、分割案の試算をしています。)。
同日、D司法書士もBさんの病室を訪れ、信託に関する説明を行いました。D司法書士と信託銀行双方の説明を聞いたBさんは、D司法書士が説明した信託の方法により自身の死後の財産の処遇を決めることとしました。
同月5日(Bさんの死亡13日前)、Bさんおよび二男は、D司法書士が持参した「民事信託契約書」(東京地裁の認定事実では、「本件信託」としています。)に署名をし、本件信託が締結されました。受益権割合は、原告(長男)6分の1(下記4参照)、被告(二男)6分の4、Aさん(二女)6分の1です。形式的には遺留分に配慮された受益権割合となっています。
同日、公証人がBさんの病室を訪れ、Bさんは、公証人の面前において、自身の意思で本件死因贈与および本件信託をしたことを宣誓し、公証人は、これを認証しました(宣誓認証制度・公証人法58条ノ2)。
その後、平成27年2月18日にBさんは死亡しました(Bさんの妻は既に死亡しています。)。
3 Bさんの意思能力の有無について
(1)標記東京地裁判決の判断
標記東京地裁判決は、「Bは、平成27年1月25日に入院した時点において、意思能力に欠ける点はなく、その後も同年2月2日には、自ら呼んだ信託銀行の担当者からも遺言について説明を聞くなどして自発的に検討をしており、他方、本件死因贈与及び本件信託を行うまで、意識障害が生じるなどして意思能力を欠く状態になったことをうかがわせる事情は見当たらない。したがって、本件死因贈与及び本件信託の時点において、Bが意思能力を欠く常況になったとは認められない。」としました。つまり、Bさんの意思能力を認めています。
(2)意思能力に関する民法の改正
これまでは、意思能力がない者がした法律行為は、判例を根拠に無効とされてきました(大審院明治38年5月11日判決)。この点について2020年(令和2年)4月1日より施行される改正民法は、「法律行為の当事者が意思表示をした時に意思能力を有しなかったときは、その法律行為は、無効とする。」(改正民法3条の2)と規定し、判例は明文化されることになりました。
4 遺留分割合
本件は、被相続人の公正証書遺言(下記5(1)参照)の存在を前提としています。その上で、その後の本件死因贈与と本件信託があります。ここで本件の相続人の遺留分について確認しておきましょう。
遺留分とは、兄弟姉妹以外の下記①と②の相続人(本件は下記②に該当)のために、相続に際して、遺言、本件死因贈与および本件信託の定めにかかわらず、民法1042条(遺留分の帰属及びその割合)の規定を根拠に、取得することを保障されている相続財産のそれぞれの割合のことをいいます。
さて、本件の相続人である長男、二男および二女は、遺留分として、「遺留分を算定するための財産の価額」(※3)に、次の②に掲げる区分の定める割合を乗じた額を受けることができます(民法1042条1項)。
① 直系尊属のみが相続人である場合 3分の1
② 上記①に掲げる場合以外の場合 2分の1
遺留分は「遺留分を算定するための財産の価額」に上記①または②の割合を乗じて計算します。本件は、上記②の2分の1に該当します。この2分の1に、3人の相続人(長男、二男、二女)各自の法定相続割合3分の1を乗じた割合・6分の1が原告(長男)の遺留分割合となります(民法1042条2項)。
※3 民法1043条1項は、「遺留分を算定するための財産の価額は、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与した財産の価額を加えた額から債務の全額を控除した額とする。」と定めています。
5 日付順に並べた公正証書遺言、死因贈与契約および民事信託契約
Bさんは以前から公正証書遺言をしています。上記2と一部重複しますが、この公正証書遺言に抵触する法律行為(本件では公正証書遺言、死因贈与契約および民事信託契約)を確認するため、下記のように日付順に整理し並べてみました。
(1)平成10年1月23日
・Bさんの公正証書遺言(以下、平成10年遺言といいます。)は、自宅およびその敷地、3つのアパートをBさんの妻Cさんに相続させ、CさんがBさんより先に死亡したときは、その不動産を二男に相続させる内容です。
・Cさんは平成15年9月23日、死亡しました。
(2)平成27年2月1日
・Bさん(贈与者)と二女・Aさん(受贈者)が死因贈与契約を締結
(Bさんの全財産の3分の1に相当する財産の贈与)
・Bさん(贈与者)と二男(受贈者)が死因贈与契約を締結
(Bさんの全財産の3分の2に相当する財産の贈与)
・平成27年2月5日 公証人は上記2つの死因贈与契約書を認証
(3)平成27年2月5日
・Bさん(委託者兼当初受益者)と二男(受託者)が民事信託契約を締結
・平成27年2月5日 公証人は上記民事信託契約書を認証
この判決は、上記3(1)に記載したように本件信託および本件死因贈与当時、Bさんは意思能力があったことを認めています。
6 遺言と遺言後の法律行為と抵触する場合の取扱い
前と後の法律行為の抵触については、税理士業務の中で、それほど意識されることはないかもしれませんが、相続対策に必要な知識ですので、この判決を利用して、基本的な考え方を整理しておきましょう。
(1)標記東京地裁判決
本件では、平成10年遺言の後、平成27年2月1日、死因贈与契約、その後、平成27年2月5日、信託契約といった法律行為がなされています(上記5参照)。前と後の法律行為が抵触するときの取扱いについて、標記東京地裁判決は、次のような判断をしています。
・本件信託または本件死因贈与と抵触する部分の平成10年遺言は、撤回されたものとみなす(民法1023条)(下記①参照)。
・本件信託が無効とされれば本件死因贈与がそのまま有効であり、本件信託が有効であれば、本件死因贈与のうち本件信託と抵触する部分は
撤回されたとみなす(民法554条・1023条)(下記②参照)。
いずれにしろ、平成10年遺言は本件信託または本件死因贈与と抵触するとしています。
以下、上記東京地裁の判断を根拠条文を見ながら、確かめておきましょう。
① 遺言後の法律行為
標記東京地裁判決の認定事実によると、本件のBさんは、平成10年遺言後の本件死因贈与(死因贈与契約という法律行為)について、民法1023条2項の規定(※4)が適用されています。したがって、同遺言が後の本件死因贈与と抵触する場合は、その抵触する部分については、後の本件死因贈与で撤回したものとみなすことになります。
※4 民法(前の遺言と後の遺言との抵触等)
1023条1項 前の遺言が後の遺言と抵触するときは、その抵触する部分については、後の遺言で前の遺言を撤回したものとみなす。
1023条2項 前項の規定は、遺言が遺言後の生前処分その他の法律行為と抵触する場合について準用する。
② 本件死因贈与と本件信託の抵触する部分について
本件死因贈与は、民法554条の規定(※5)が適用され、遺言に関する規定が準用されますので、本件死因贈与は、同条の規定の適用により同法1023条の規定(※4)の適用を受けます。したがって、本件死因贈与がその死因贈与後の本件信託(信託契約という法律行為)と抵触する部分については、本件信託で前の本件死因贈与を撤回したものとみなすことになります。(参考【信託メモ】)
※5 民法(死因贈与)
554条 贈与者の死亡によって効力を生ずる贈与については、その性質に反しない限り、遺贈に関する規定を準用する。
(2)税理士の相続対策業務における留意点
この裁判は、税理士が顧客に対し相続対策業務を行うときに、まず、顧客が遺言をしているかどうか、その遺言と抵触する遺言や死因贈与契約といった法律行為の有無の確認を業務手続の手順とすべきことを示唆しています。
上記2、5の認定事実から、D司法書士は、Bさんに対し、この点をふまえた上で、死因贈与契約と民事信託契約の説明をしていると理解されます。
以上、本件の入口部分を見てきました。Bさんは意思能を喪失していたか、あるいは、意思能力はあっても死因贈与契約と民事信託契約を締結していなければ、平成10年遺言に基づき、遺留分減殺請求が行われたことになります(※6)。
※6 民法(遺留分侵害額請求権の期間の制限)
1048条 遺留分侵害額の請求権は、遺留分権利者が、相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った時から1年間行使しないときは、時効によって消滅する。相続開始の時から10年を経過したときも、同様とする。
今回を含めこの連載の中で、読者の皆様方は、「Bさんは、信託などしなければよかったのに。」という感想を抱かれることと思います。その感想は、もっともなことですが、それは、ひとまず横に置くことにしましょう。繰り返しになりますが、この裁判からは大切な教訓を学び取ることができるからです。
民事信託は、信託法の同じ仕組みを使っても、使う人(委託者)の意図が何か、信託に携わる人(特に受託者)がどのような人か、どのタイミングで、どの財産を使って信託を始めるのか、どのような管理運用体制とするかなどで全く違う状況や結果が生まれます。この点を意識しながら、次回以後、信託のあるべき姿をご一緒に考えていくことにしましょう。
第2回の次回は、信託契約に関する原告と被告の主張に対し、第一審である東京地裁が原告の遺留分を確保するためにどのような判断を示したのか、その判決内容に焦点を当て、見ていくことにします。
【信託メモ】 「本件とは逆の順番」で信託契約の後に遺言がなされたとき
本件とは逆の順番で、最初に信託契約が締結され、その効力が生じ、その後、遺言がなされることがあります。このとき、その遺言で信託契約の受益者(受益権を有する者)を変更することができるかどうかという問題があります。この問題は信託法90条(委託者の死亡の時に受益権を取得する旨のある信託等の特例)1項本文の規定を原則的に適用する場合と、同項ただし書を根拠に別段の定めを設け、例外的な取扱いをする場合の2つに分けて考えます。
前者の場合は、信託契約に別段の定めを設けませんので、委託者は遺言で「受益者を変更する権利」(信託法89条2項)を行使することができます(信託法90条1項本文)。後者の場合は、信託契約に別段の定めとして遺言による「受益者を変更する権利」の行使を禁止する定めを設けることができます(同項ただし書)。どちらにするかは、ケース・バイ・ケースで十分に考慮して選択します。
なお、信託契約における信託法90条1項の使い方について、ご関心のある方は、拙著「問題解決のための民事信託活用法」(新日本法規刊)第1章・ケース4(信託契約書(案)添付)をご参照ください。
※この記載内容は、著者の個人的見解によるものであり、その内容について読者の皆様方に対し、責任を負うものではありませんので、あらかじめご了承ください。
(2019年8月執筆)
人気記事
人気商品
民事信託特集 全22記事
- 民事信託こぼれ話 第10話
- 民事信託こぼれ話 第9話
- 民事信託こぼれ話 第8話(後編)
- 民事信託こぼれ話 第8話(前編)
- 民事信託こぼれ話 第7話
- 民事信託こぼれ話 第6話(後編)
- 民事信託こぼれ話 第6話(前編)
- 民事信託こぼれ話 第5話
- 消滅する受益権(信託法91条)の時価評価~平成30年9月12日東京地裁判決を前提に~
- 民事信託こぼれ話 第4話(後編)
- 民事信託こぼれ話 第4話(前編)
- 税理士業務の中の民事信託(第4回)
- 民事信託こぼれ話 第3話(後編)
- 民事信託こぼれ話 第3話(前編)
- 民事信託こぼれ話 第2話(後編)
- 民事信託こぼれ話 第2話(前編)
- 民事信託こぼれ話 第1話(後編)
- 民事信託こぼれ話 第1話(前編)
- 税理士業務の中の民事信託(第3回)
- 税理士業務の中の民事信託(第2回)
- 税理士業務の中の民事信託(第1回)
- 後見と民事信託
執筆者

石垣 雄一郎いしがき ゆういちろう
税理士、信託ナビゲーター
略歴・経歴
税理士資格取得後、不動産会社で17年間上場企業の新規開拓や中小企業、個人不動産オーナー向けの営業や新規プロジェクトの立ち上げ支援業務を担当。ダンコンサルティング(株)の取締役を経て、現在は、不動産や株式を主とした民事信託等の浸透に関するコンサルティング業務に従事しながら全国各地からの依頼で信託の実践や活用に関する講演活動も行っている。民事信託のスキームの提案を実施し、不動産会社等にも顧問として信託の活用法を具体化する支援を行っている。
執筆者の記事
執筆者の書籍
-

-

団体向け研修会開催を
ご検討の方へ弁護士会、税理士会、法人会ほか団体の研修会をご検討の際は、是非、新日本法規にご相談ください。講師をはじめ、事業に合わせて最適な研修会を企画・提案いたします。
研修会開催支援サービス -

Copyright (C) 2019
SHINNIPPON-HOKI PUBLISHING CO.,LTD.