一般2024年12月17日 SNS上のアスリートに対する誹謗中傷への法的対応について(誹謗中傷問題連載③) 一般社団法人日本スポーツ法支援・研究センターからの便り 執筆者:冨士川健
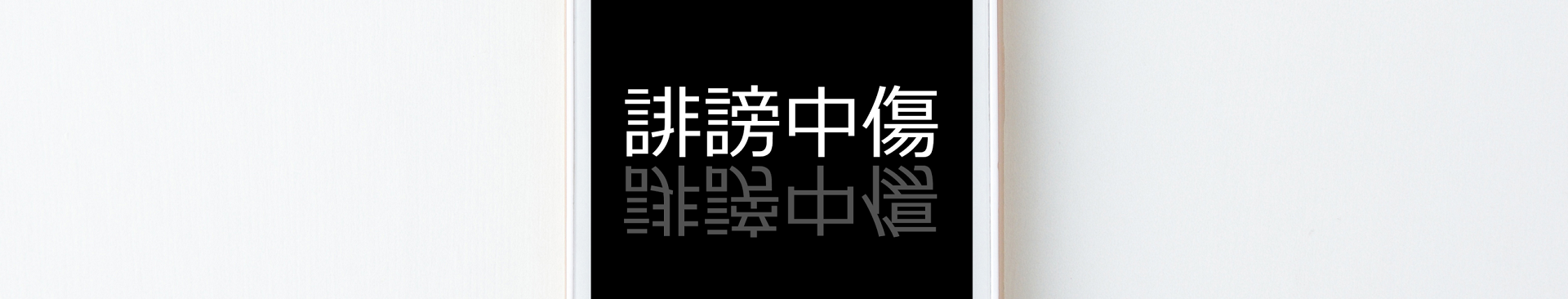
第1 はじめに
SNS上におけるアスリートへの誹謗中傷は、その即時性と拡散性から、被害者の人格権に対する重大な侵害をもたらす現代的な法的課題である。その法的救済手段として、発信者情報開示請求、損害賠償請求、刑事告訴といった法的手段が存在するところ、本稿では、被害回復の出発点となる発信者情報開示請求の構造と実務上の留意点について検討する。
第2 発信者情報開示請求の構造と実務上の留意点
1 二段階開示の必要性
発信者情報開示請求は、第一段階として、コンテンツプロバイダ(「X Corp.」等のSNSプラットフォーム運営会社等)に対してIPアドレス等の開示を求め、第二段階として、アクセスプロバイダ(「株式会社NTTドコモ」等の通信事業者等)に対して発信者の氏名・住所等の開示を求めることとなるのが一般的である。
近時、コンテンツプロバイダの情報開示が遅延傾向にあることとの関係で、アクセスプロバイダにおける通信ログ保存期間(概ね3~6ヵ月程度1)が経過し、発信者特定に必要な通信ログが消去され、第一段階の開示請求が認められても発信者の特定ができなくなるケースが散見される。発信者特定のためには、誹謗中傷投稿がされてからすぐに専門家に相談し、早期に法的手続きを進める必要があることに留意すべきである2。
2 発信者情報開示請求手続きにおける主張立証
アスリートへの誹謗中傷に対して発信者情報開示をする場合、同定可能性3及び権利侵害の明白性が争点となるが、本稿では、主たる争点となりやすい権利侵害の明白性にかかる留意点について論じることとする。
誹謗中傷の投稿について、権利侵害の明白性が認められるためには、当該投稿が社会通念上許容される限度を超える侮辱行為に該当することが必要である。
アスリートに対する誹謗中傷投稿は、その多くが試合中の特定のプレーやそれに付随する言動を契機として発生するという特徴を有する。裁判実務においては、この文脈を重視し、権利侵害の明白性判断に際して、投稿内容の悪質性だけでなく、①投稿の契機となった具体的場面や②当該場面におけるアスリートの行為態様も総合的に考慮する傾向にある。
例えば、死球を受けた野球選手に対して誹謗中傷の投稿がなされた場合(①の要素)には、死球を受けた選手はあくまで被害者であるという事実関係(②の要素)を前提として、そのような状況下で人格攻撃的投稿を甘受すべき合理的理由が存在するかという観点での検討がなされる4。このように、アスリートといえども、その競技上の行為と無関係な人格攻撃をされた場合には権利侵害の明白性が肯定されるということに異論はないであろう。
以上のような裁判実務を前提に、発信者情報開示請求を実効的なものとするためには、投稿内容のスクリーンショット等の証拠保全に加え、試合映像や報道内容等、投稿の背景事情を明らかにする証拠の収集・確認を行うことも非常に重要である5。
第3 まとめ
アスリートに対する誹謗中傷への法的対応において、発信者情報開示請求は被害回復の端緒として極めて重要な意義を有する。そして、その実効性を確保するためには、迅速な法的手続きの実施とアスリートの特殊性を踏まえた説得的な主張立証が求められる。
次回の連載④では、発信者情報開示請求を含む、アスリートに対する誹謗中傷にかかる法的対応の現状を明らかにするため、アスリートに対する誹謗中傷が問題となった事件や裁判例の法的分析を行うこととする。
1 神田知宏,「インターネット削除請求・発信者情報開示請求の実務と書式 第2版」,日本加除出版株式会社 2023,170頁。
2 筆者の経験上、現在のプロバイダの対応を前提にすると、投稿から2週間以内に法的手続きをするのが望ましい。
3 同定可能性は、当該表現が誰に対するものであるかを第三者が認識できる場合に肯定される。すなわち、一般人の読み方を基準にすれば、対象の誹謗中傷投稿が被害者に向けられたものであること読むのが普通であるといえる場合であれば同定可能性は肯定されることとなる。なお、同定可能性は、対象の投稿に記載された内容だけでなく、例えば同一の投稿者の過去の投稿等も加味して、全体的に観察して判断するというのが裁判実務の趨勢である(中澤佑一,「インターネットにおける誹謗中傷法的対策マニュアル 第4版」,中央経済社,2022,68頁以下参照)。
4 逆に死球を当てた選手に対する誹謗中傷投稿についての権利侵害の明白性の判断は、死球を当てた選手がある意味で加害者的な立場にあるものとの前提で判断がなされることになるものと推察される。
5 紙幅の関係上、本文では記載を省略したが、証拠の収集方法についても留意点があるため、的確な証拠収集の観点からも早期に専門家に相談することが重要である。証拠収集方法に係る留意点についてはCOASのサイトで説明されている。
(2024年12月執筆)
(本コラムは執筆者個人の意見であり、所属団体等を代表するものではありません。)
(本記事の内容に関する個別のお問い合わせにはお答えすることはできません。)
人気記事
人気商品
一般社団法人日本スポーツ法支援・研究センターからの便り 全26記事
- 武道と法規範~合気道を例に
- スポーツ団体による事実認定と立証の程度
- アスリートに対する誹謗中傷の問題点と今後求められる取組み(誹謗中傷問題連載⑤)
- SNS上のアスリートに対する誹謗中傷の具体的事案及び法的分析(誹謗中傷問題連載④)
- SNS上のアスリートに対する誹謗中傷への法的対応について(誹謗中傷問題連載③)
- 国内におけるアスリートに対する誹謗中傷問題への対応(誹謗中傷問題連載②)
- 国際大会におけるアスリートへの誹謗中傷とその対策(誹謗中傷問題連載①)
- 部活動の地域移行、地域連携に伴うスポーツ活動中の事故をめぐる法律問題
- スポーツにおけるセーフガーディング
- スポーツ仲裁における障害者に対する合理的配慮
- スポーツ施設・スポーツ用具の事故と法的責任
- オーバーユースの法的問題
- スポーツ事故の実効的な被害救済、補償等について
- 日本プロ野球界におけるパブリシティ権問題の概観
- パルクール等、若いスポーツの発展と社会規範との調和
- ロシア選手の国際大会出場に関する問題の概観
- スタッツデータを取り巻く法的議論
- スポーツ事故における刑事責任
- スポーツに関する通報手続及び懲罰手続に関する留意点
- スポーツ界におけるフェイクニュース・誹謗中傷
- スポーツと地域振興
- アンチ・ドーピング規程における「要保護者」の特殊性
- スポーツにおけるパワーハラスメントについて考える
- アスリート盗撮の実情とその課題
- アンチ・ドーピングについてJADA規程に準拠しない競技団体とその課題
- スポーツチームにおけるクラブトークンの発行と八百長規制の必要性
執筆者

冨士川 健ふじかわ たける
弁護士(ヴァスコ・ダ・ガマ法律会計事務所)
略歴・経歴
2018年3月 早稲田大学法学部卒業
2020年3月 早稲田大学大学院法務研究科修了
2021年3月 司法研修所入所
2022年4月 弁護士登録(東京弁護士会)
2024年1月 ヴァスコ・ダ・ガマ法律会計事務所入所
業務領域
・エンターテインメント法務
・スポーツ法務
・メディア法務
・インターネット法務
・ライセンス関連法務
・一般企業法務
・一般民事法務
・訴訟全般
主な役職
・東京弁護士会人権擁護委員会
執筆者の記事
関連カテゴリから探す
-

-

団体向け研修会開催を
ご検討の方へ弁護士会、税理士会、法人会ほか団体の研修会をご検討の際は、是非、新日本法規にご相談ください。講師をはじめ、事業に合わせて最適な研修会を企画・提案いたします。
研修会開催支援サービス -

Copyright (C) 2019
SHINNIPPON-HOKI PUBLISHING CO.,LTD.





















