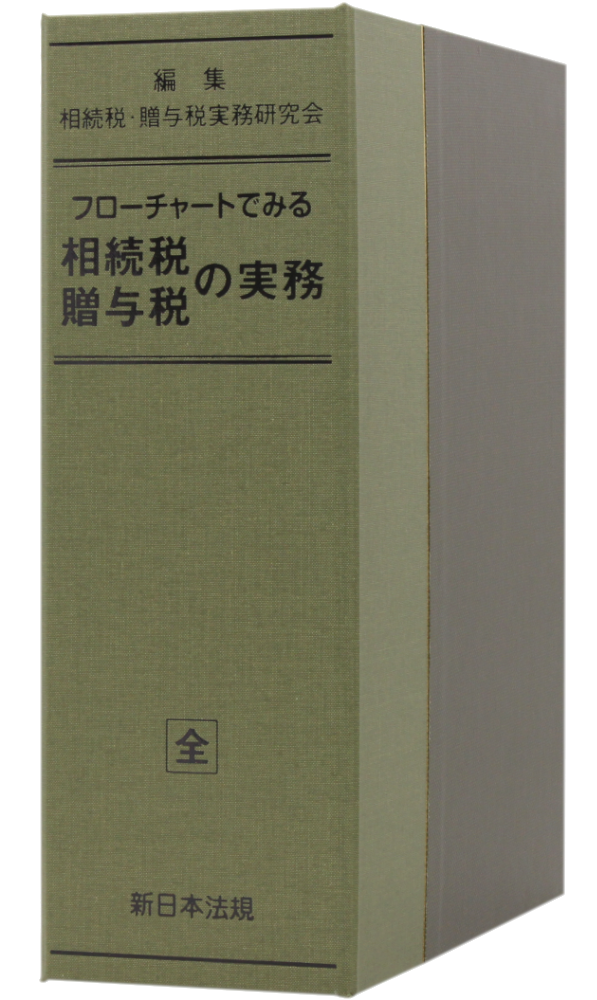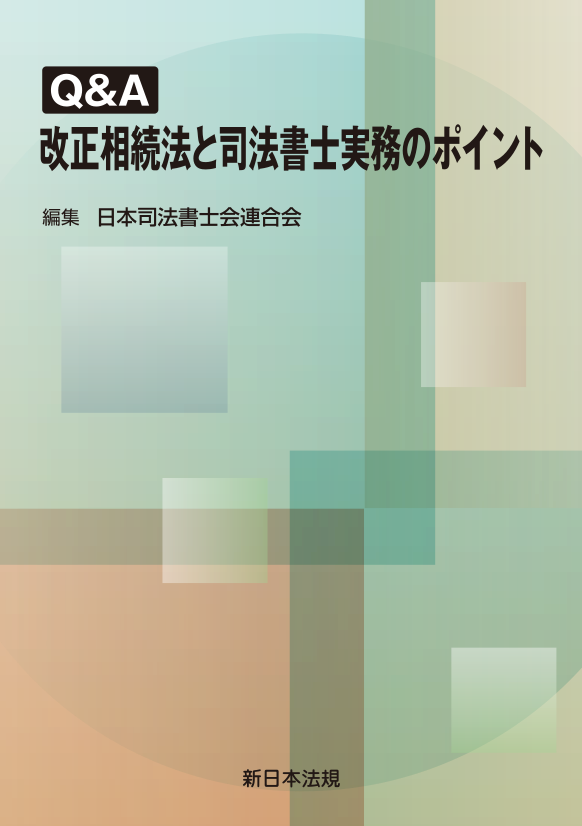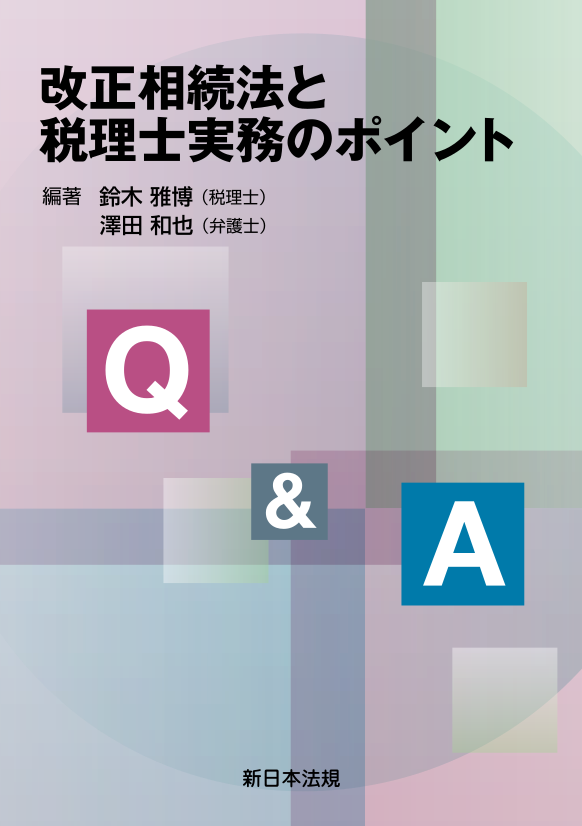相続・遺言2020年07月08日 相続法が変わった(2) 自筆証書遺言書保管制度のメリット 執筆者:北村明美
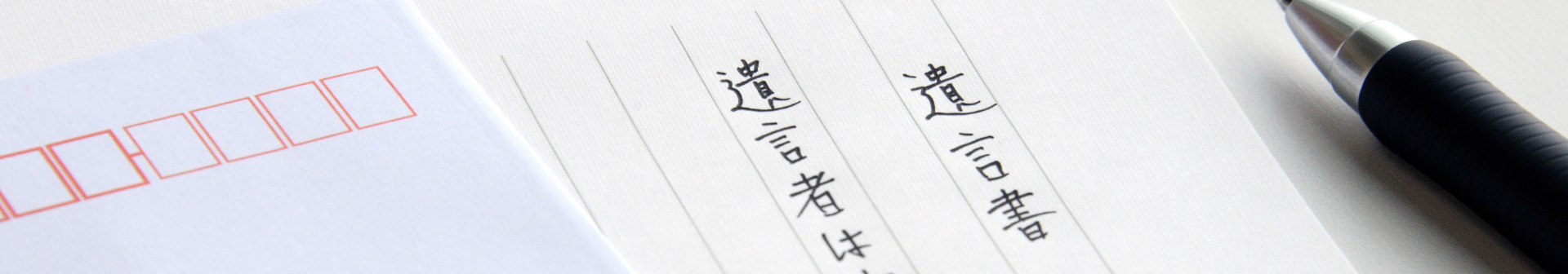
1.遺言が有効か無効かの争い
ここ数年、遺言が有効か無効かが争点となる事件を何件かやっている。
(1)自筆証書遺言
①自筆証書遺言は、偽造したと疑われて、争われやすい。
・筆跡鑑定が行われた一澤帆布事件は有名である。
・養子縁組届の養親欄に、父親から頼まれて息子が代筆した。
父親の昔の愛人の子から養子縁組無効確認訴訟が提起され、当然敗訴。
さらに、愛人の子は、自筆証書遺言無効確認訴訟を提起。
その遺言は、病気をした後、真実、父親が自筆で書いた遺言だった。
しかし、病気をした後だったので、達筆だった筆跡は見る影もなかったが病気前の筆跡に似ていた。
筆跡鑑定が行われ、父親の筆跡ではないという結果が出てしまい敗訴。
ここまでは、他の弁護士が息子さんの代理人であった。
2件の敗訴判決のあとを私が引き継いで、文書偽造罪で告訴された刑事事件や損害賠償請求事件、遺産分割事件など長くてつらい闘いの代理人をしたことがある。
②自筆証書遺言は、被相続人が遺言に書いておいたからと言い残していったが、死後、探しても見つからないということがある。
③自筆証書遺言の内容が家訓や説教ばかりで、誰に何を遺贈するのか書いてないものもあった。
(2)そのため、多くの弁護士は、少し費用がかかるけれど、公正証書遺言にした方が確実ですよとアドバイスしてきた。
実際、公正証書遺言の無効を主張して、勝訴できる確率は低い。
公正証書遺言を無効とした裁判例が多いようにみえるが、それは無効とした裁判例の多くが公刊物に載っているからだと思われる。
なぜなら、作成した公証人も立ち会った証人も「口授はあった」「うなずき遺言ではなく、遺言者はかくかく発言した」「よく理解していて、何ら不自然なところはなく、遺言能力がないとは思わなかった」等と証言するからだ。
私は30年以上弁護士をやっているが、公正証書遺言無効を争って、勝訴(勝訴的和解を含む。)したのは2件だけである。重い認知症で遺言能力がないと裁判所が判断してくれたケースであった。
2.法務省民事局から「自筆証書遺言書保管制度のご案内」というパンフレットが出ている。
「令和2年7月10日(金)制度開始」「あなたの大切な遺言書を法務局(遺言書保管所)が守ります。」というキャッチフレーズだ。
いよいよ令和2年7月10日から、法務局が自筆証書遺言書を預かる制度が開始されるのである。
(1)自筆証書遺言書保管制度の一番のメリットは、検認が不要なことである。
これまで自筆証書遺言のデメリットとして、検認が必要なことがあった。
被相続人の生まれてから亡くなるまでの戸籍謄本などはもちろんのこと、相続人全員の戸籍謄本や住民票をそろえて家庭裁判所に検認の請求をする(民法1004条)。1円も相続できず、遺留分もない法定相続人が家庭裁判所に来て「遠くから出てきたのに1円ももらえないのか」と不満の意を露わにされた経験のある弁護士も多いのではないだろうか。
公正証書遺言は検認が不要で、自筆証書遺言は検認が必要だが、自筆証書遺言書保管制度を利用したものは検認が不要となるというわけだ!
***法務局における遺言書の保管等に関する法律
第11条 民法第1004条第1項(検認)の規定は、遺言書保管所に保管されている遺言書については、適用しない。
(2)財産目録作成の簡便性
そのパンフレットには、自筆証書遺言の例示が載っている。財産目録は自書によらず、パソコンでわざわざ打つ必要もない。登記事項証明書のコピーや通帳のコピーに遺言者の署名押印したものを添付すれば、財産目録となる。本文の自書の部分に、別紙1の不動産は誰々に相続させる、別紙2の預貯金は誰々に遺贈する、と書けばよいのである。
このような財産目録でいいのは、改正民法968条2項では「前項の規定にかかわらず、自筆証書にこれと一体のものとして相続財産の全部または一部の目録を添付する場合には、その目録については、自書することを要しない。」という文言になっているからである。
とても簡便だ。
(3)遺言者本人が、保管申請をしたことが証明できる
自筆証書遺言書の保管の申請をする場合、原則予約が必要である。遺言者本人が遺言書を持参し、本人であることを証明する写真付きのものを添付しなければならないことになっている。家族などは付き添ってもいいが、必ず本人が行かなければならない。
運転免許証もパスポートもない方は、マイナンバーカードを作るしかないかもしれない。ここでもマイナンバーカードの推奨だ。
写真付きのもので本人であることを証明するので、その自筆証書遺言が偽造されたという争いはしにくくなるだろう(完全ではないので争うことはできるが・・・)。
保管先は、遺言者の住所地あるいは本籍地、所有する不動産の所在地のいずれかを管轄する遺言書保管所である
(4)安価である
保管申請の手数料は、1通につきわずか3,900円である。
遺言者が亡くなった後、相続人らが遺言書の内容の証明書(遺言書情報証明書)を取得する場合の手数料は1通1,400円である。
(5)さがしてもみつからないということはない
法務局(遺言書保管所)に保管された自筆証書遺言書は、データベース化されて、遺言者死後、全国どこの法務局からでも交付請求でき、見つからないということがない(もちろん、入力ミス等がない場合である。)。
(6)リスクマネージメント
データベース化したデータは、災害等で消失する場合を考え、別の場所にも保管するという。
(7)保管期間
法務局に保管される自筆証書遺言書は、遺言者が死亡してから50年間とのことである。公正証書遺言は遺言者が120歳になるまで公証人役場で保管するときいている。
検認が不要、簡便、争われにくい、安い、保管が確実、という良いことづくめの制度のように思われる。
ヒットする予感がするのは、私だけでなく、法務局(法務省)もそう思って力を注いでいるのではないだろうか。
これからは、自筆証書遺言書保管制度を利用する人が増え、公正証書遺言を選択する人が減るのではないかとさえ思われる。もちろん、公正証書遺言を必要とするニーズはある。
公証人に対しては、新設された保証意思宣明公正証書(事業用融資の保証について、公証人が保証人になろうとする者の意思を確認する手続きのための公正証書)で、公正証書遺言作成の仕事が減る分、あり余る穴埋めになると法務省は考えているのだろうか。
弁護士は公証人にもなれないし(なぜなのだろうか?)いつも蚊帳の外であることがつらい。こんなに弁護士が増えているのに。
(2020年6月執筆)
人気記事
人気商品
関連商品
執筆者

北村 明美きたむら あけみ
弁護士
略歴・経歴
名古屋大学理学部物理学科卒業
コンピューターソフトウェア会社などに勤務
1985年弁護士登録(愛知県弁護士会所属)
著書・論文
「女の遺産相続」(NTT出版)
「葬送の自由と自然葬」(凱風社・共著)など
「医療事故紛争の上手な対処法」(民事法研究会・共著)
「証券取引法の仲介制度の運用上の問題点」(商事法務 ・1285)
執筆者の記事
-

-

団体向け研修会開催を
ご検討の方へ弁護士会、税理士会、法人会ほか団体の研修会をご検討の際は、是非、新日本法規にご相談ください。講師をはじめ、事業に合わせて最適な研修会を企画・提案いたします。
研修会開催支援サービス -

Copyright (C) 2019
SHINNIPPON-HOKI PUBLISHING CO.,LTD.