一般2025年01月27日 SNS上のアスリートに対する誹謗中傷の具体的事案及び法的分析(誹謗中傷問題連載④) 一般社団法人日本スポーツ法支援・研究センターからの便り 執筆者:手塚圭祐
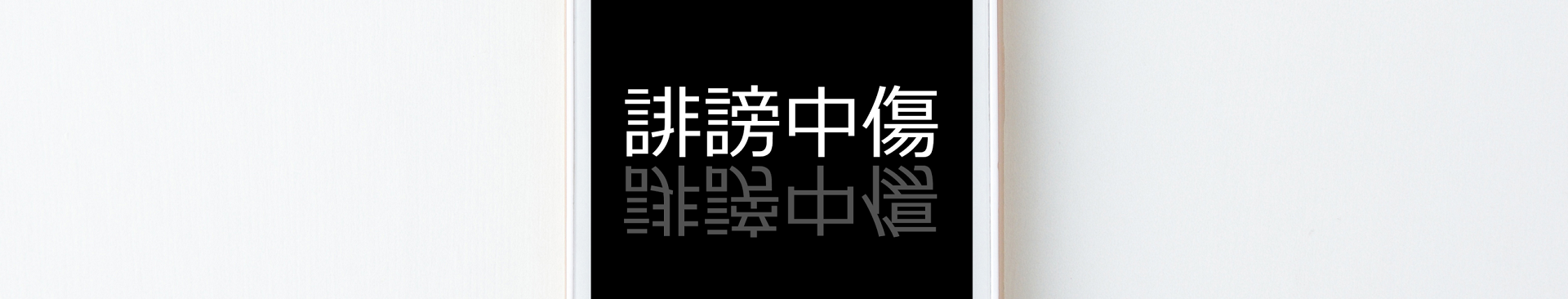
第1 はじめに
第2 具体的な事案及び法的な問題点
第3 まとめ
1 https://www.zelvia.co.jp/news/news-280535/
2 https://jpbpa.net/2024/10/24/11887/
3 https://www.moj.go.jp/keiji1/keiji12_00194.html
4 https://www.yomiuri.co.jp/national/20220614-OYT1T50017/
5 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20240806/k10014538981000.html
6 外部的な社会的な評価を低下させたことを前提とする「名誉権侵害」と、外部的な社会的な評価を低下させず名誉感情を侵害したことを前提とする「名誉感情」に対する侵害(侮辱)とは区別される(中澤佑一「プロバイダ責任制限法と誹謗中傷の法律相談」(青林書院、2023年)203頁参照)。
7 違法性阻却事由の判断枠組みが異なるので、両者を区別して主張することが実務上求められている(前掲注6の210頁参照)。
8 https://www.sn-hoki.co.jp/articles/article3857911/
9 前掲注6の208頁参照(なお、保全手続による場合、保全の必要性として、記事がインターネット上で現に公開され続けており、損害が拡大していることが必要となる。)
10 東京地判令和3年8月24日(令和3年(ワ)第6482号)判例秘書掲載
11 名誉感情の侵害の成否にあたっては、厳密な同定可能性を基準に検討するのではなく、自分が被害者であるという合理的な説明が可能であればよいと考えられる(前掲注6の225頁参照)。
(2025年1月執筆)
(本コラムは執筆者個人の意見であり、所属団体等を代表するものではありません。)
(本記事の内容に関する個別のお問い合わせにはお答えすることはできません。)
人気記事
人気商品
一般社団法人日本スポーツ法支援・研究センターからの便り 全29記事
- スポーツ界におけるフリーランス保護法の影響
- 「スポーツを観る権利」~ユニバーサルアクセス権から考える~
- 日本人陸上選手のアンチ・ドーピング規則違反についてのCAS決定
- 武道と法規範~合気道を例に
- スポーツ団体による事実認定と立証の程度
- アスリートに対する誹謗中傷の問題点と今後求められる取組み(誹謗中傷問題連載⑤)
- SNS上のアスリートに対する誹謗中傷の具体的事案及び法的分析(誹謗中傷問題連載④)
- SNS上のアスリートに対する誹謗中傷への法的対応について(誹謗中傷問題連載③)
- 国内におけるアスリートに対する誹謗中傷問題への対応(誹謗中傷問題連載②)
- 国際大会におけるアスリートへの誹謗中傷とその対策(誹謗中傷問題連載①)
- 部活動の地域移行、地域連携に伴うスポーツ活動中の事故をめぐる法律問題
- スポーツにおけるセーフガーディング
- スポーツ仲裁における障害者に対する合理的配慮
- スポーツ施設・スポーツ用具の事故と法的責任
- オーバーユースの法的問題
- スポーツ事故の実効的な被害救済、補償等について
- 日本プロ野球界におけるパブリシティ権問題の概観
- パルクール等、若いスポーツの発展と社会規範との調和
- ロシア選手の国際大会出場に関する問題の概観
- スタッツデータを取り巻く法的議論
- スポーツ事故における刑事責任
- スポーツに関する通報手続及び懲罰手続に関する留意点
- スポーツ界におけるフェイクニュース・誹謗中傷
- スポーツと地域振興
- アンチ・ドーピング規程における「要保護者」の特殊性
- スポーツにおけるパワーハラスメントについて考える
- アスリート盗撮の実情とその課題
- アンチ・ドーピングについてJADA規程に準拠しない競技団体とその課題
- スポーツチームにおけるクラブトークンの発行と八百長規制の必要性
執筆者

手塚 圭祐てづか けいすけ
弁護士(永淵総合法律事務所)
略歴・経歴
千葉大学法経学部法学科卒業
早稲田大学法科大学院修了
日本スポーツ法学会会員
日本プロ野球選手会公認選手代理人
専門分野はスポーツ法務、企業法務、一般民事、刑事事件
執筆者の記事
関連カテゴリから探す
-

-

団体向け研修会開催を
ご検討の方へ弁護士会、税理士会、法人会ほか団体の研修会をご検討の際は、是非、新日本法規にご相談ください。講師をはじめ、事業に合わせて最適な研修会を企画・提案いたします。
研修会開催支援サービス -























