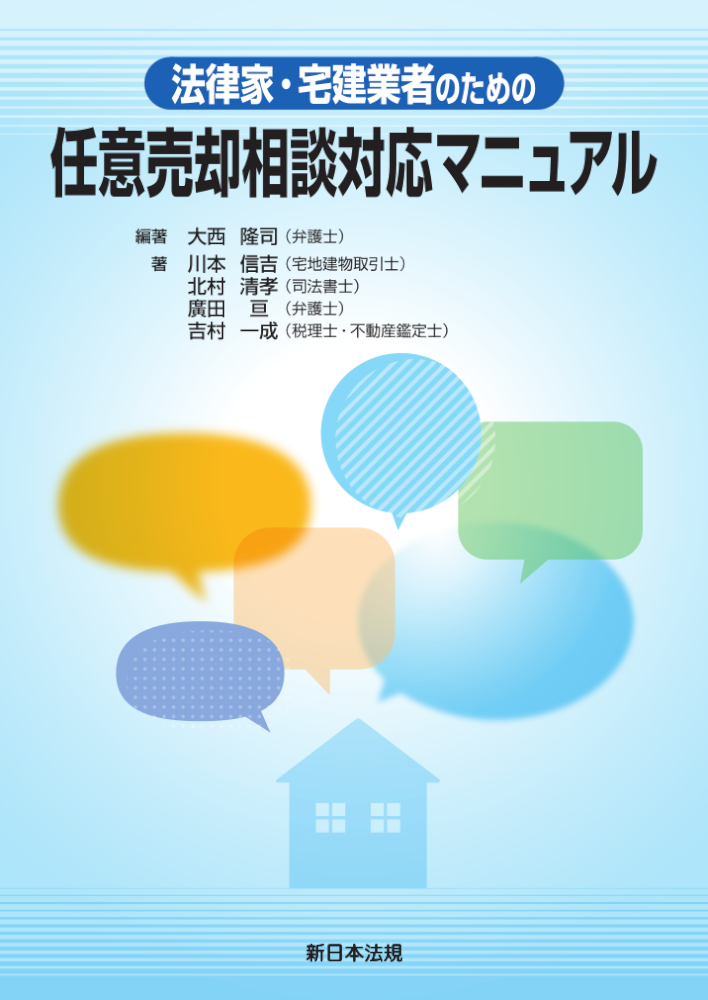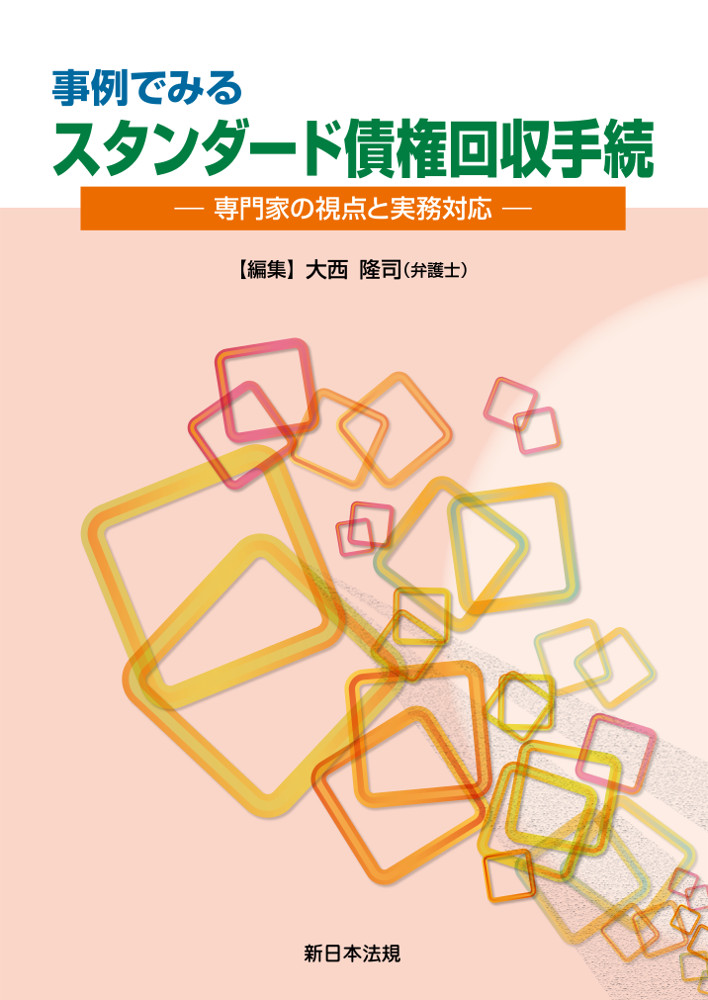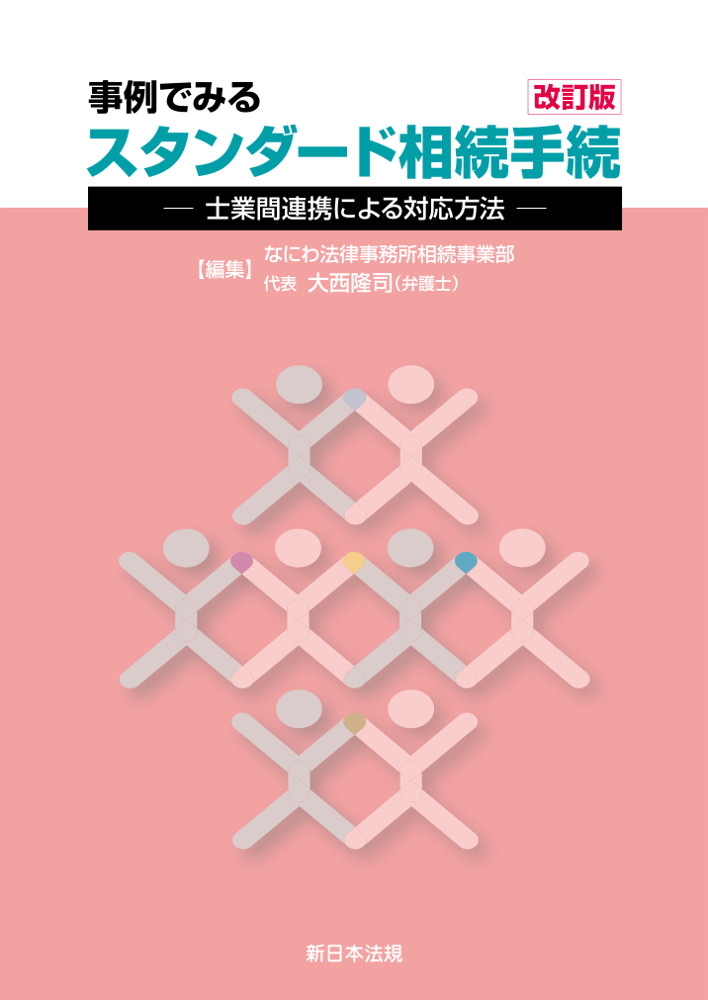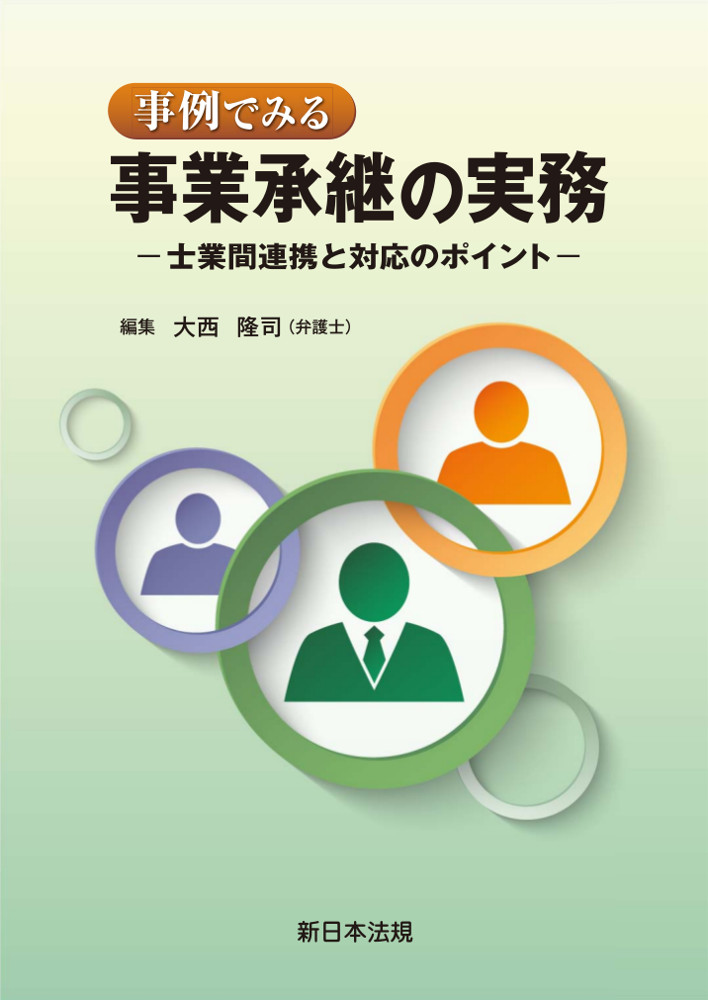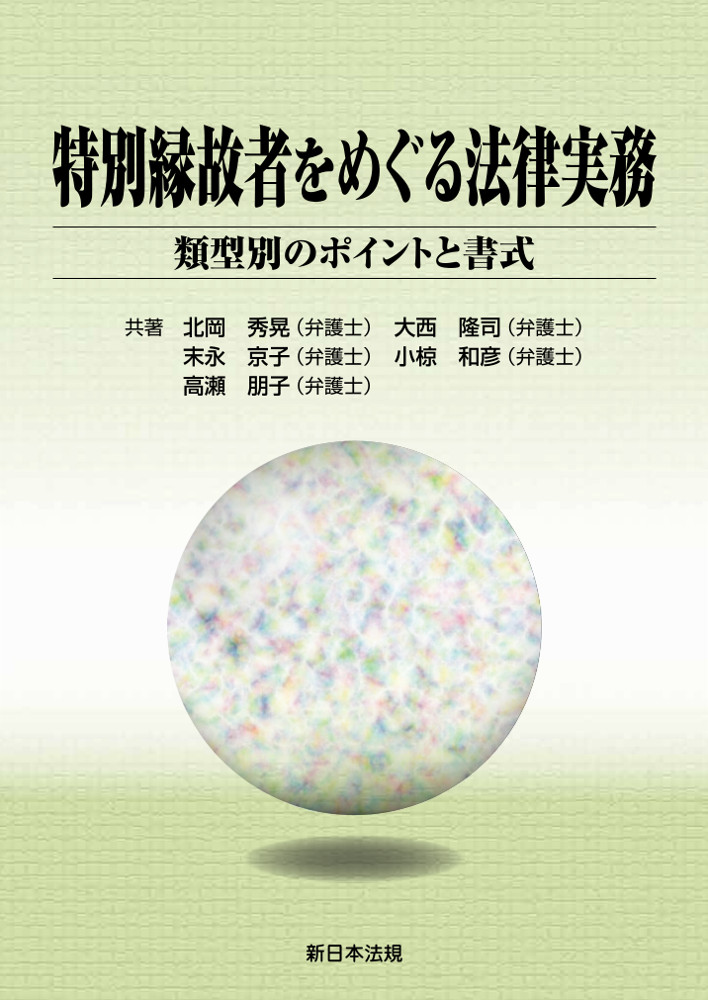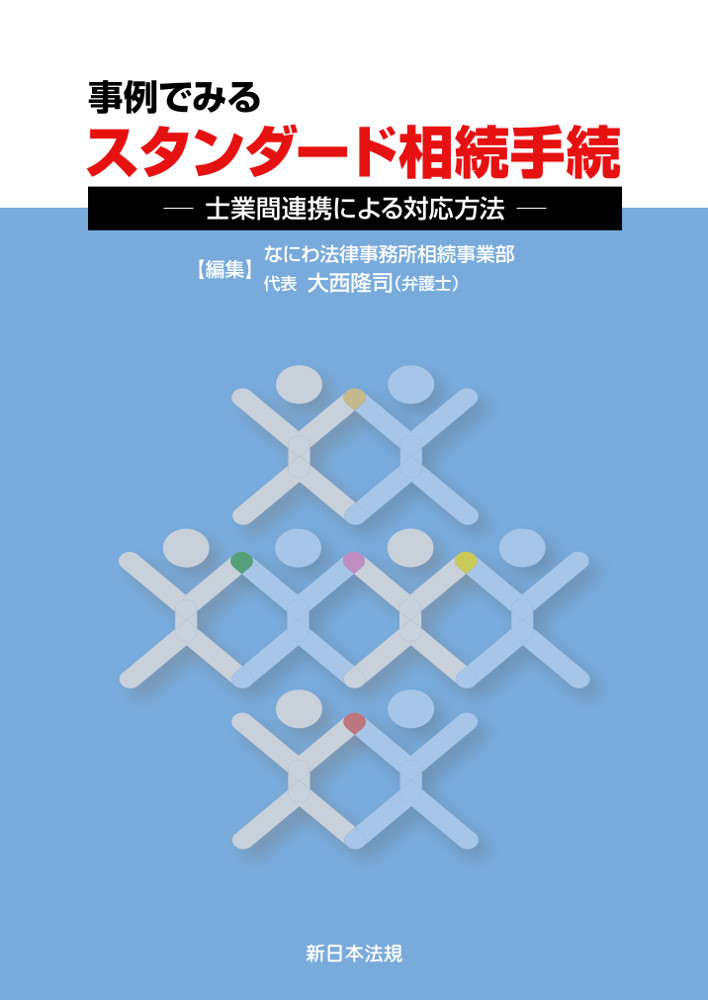人事労務2025年03月26日 行方不明となった従業員の退職手続 執筆者:大西隆司

1 従業員が無断欠勤を続けた場合の会社の対応
従業員が音信不通や行方不明となって無断欠勤が続くケースがあります。
従業員の他の言動(退職願提出など)と相まって、無断欠勤を続けることが退職の黙示の意思表示と評価できる場合を除けば、単に無断欠勤を続けただけで退職の申出があったとして取り扱うことはできず、会社は退職の手続の検討が必要です。
2 解雇による方法
まず、会社から一方的に労働契約を終了させる意思表示を行う解雇の方法が考えられます。
厚生労働省の通達(昭和23.11.11基発1637号、昭和31.3.1基発111号)では、労基法第20条1項但書の「労働者の責に帰すべき事由」として解雇予告が不要となる場合として、「原則として2週間以上正当な理由なく無断欠勤し、出勤の督促に応じない場合」があげられており、事前の届け出をせず、欠勤の理由や期間、居所を具体的に明確にしないままの2週間にわたる欠勤を正当な理由のない欠勤であるとして懲戒解雇を有効にした裁判例(東京地判H12.10.27)もあることから、2週間の欠勤がひとつの目安になるでしょう。
ただし、解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とされます(労働契約法16条)。
これを超える長期の無断欠勤の事例でも、会社は精神科医による健康診断を実施するなどして、必要な場合は治療を勧め、休職などの対応も検討すべきだったとして、正当な理由のない無断欠勤があったとはいえないとした裁判例(最判H24.4.27)や当該欠勤は統合失調症の罹患を契機とし、自由意思による無断欠勤でないことを上司も認識し得たことから、懲戒免職処分を取り消した裁判例(大阪地判H21.5.25)があり、正当な理由のない欠勤であるかどうかは慎重に判断する必要があります。
また、解雇の意思表示は書面等で行いますが、従業員が行方不明の場合は、意思表示を到達させることができず、公示による意思表示の手続を行う必要があります。この制度は、申立てにより、解雇した事実を2週間裁判所の掲示板に掲示することで通知が到達したとみなす制度です。
しかし、掲示があったことは官報に掲載され、会社に行方不明の従業員がいることが知られるというリスクが存在します。
3 自動退職規定の利用
そこで、予め就業規則で、従業員の無断欠勤・音信不通・行方不明など、一定の要件に該当したことをもって、自動的に退職したものとして取り扱う旨を定めることが考えられます。
退職について、懲戒解雇規定のほかに、「従業員の行方が不明となり、14日以上連絡が取れないときで、解雇手続を取らない場合には退職とし、14日を経過した日を退職の日とする 」という退職条項が争われた事案(東京地判R2.2.4)があります。
同裁判例は、同条項の趣旨を「被告が従業員に対して通常の手段によっては出勤の督促や懲戒解雇の意思表示をすることができない場合、すなわち,被告の従業員が欠勤を継続し、被告が通常の手段によっては出勤を命じたり解雇の意思表示をしたりすることが不可能となった場合に備えて、そのような事態が14日以上継続したことを停止条件として退職を合意した」として、当該条項について「従業員が所在不明となり、かつ,被告が当該従業員に対して出勤命令や解雇等の通知や意思表示をする通常の手段が全くなくなったときを指す」としました。
この従業員が、連日、休暇等届と題する書面等を、ファクシミリを利用して送信するとともに、勤務の予定をファクシミリを利用して送信するよう求め、電子メールを送信して、休職を申し出るとともに、電子メールアドレスを開示して電子メールで連絡をするよう求めるなどしていた事案であったため、当該条項にあたらないとしました。
無断欠勤について、解雇事由にもあたる場合には、自動退職規定の処理は、解雇の意思表示ができない場合などに限定して解釈される可能性があります。
自動退職規定の利用は、電話以外の手段でも従業員に連絡が取れないかどうかを確認し、証拠を残した上で選択するようにしましょう。
(2025年2月執筆)
(本記事の内容に関する個別のお問い合わせにはお答えすることはできません。)
人気記事
人気商品
執筆者

大西 隆司おおにし たかし
弁護士(なにわ法律事務所)
略歴・経歴
なにわ法律事務所URL:http://naniwa-law.com/
「大阪産業創造館 経営相談室「あきないえーど」 経営サポーター(2012年~2015年3月、2016年~2019年3月、2020年4月~)」、関西大学非常勤講師(2014年度〜2016年度)、関西大学会計専門職大学院非常勤講師(2017年度〜)、滋賀県商工会連合会 エキスパート登録(2013年~)、大阪弁護士会遺言相続センター登録弁護士、大阪弁護士会高齢者・障害者支援センター「ひまわり」支援弁護士。
著書
『特別縁故者をめぐる法律実務―類型別のポイントと書式―』(新日本法規出版、2014年)共著
『法務・税務からみた相続対策の効果とリスク』(新日本法規出版、2015年)相続対策実務研究会代表大西隆司(なにわ法律事務所)編著
『事例でみる事業承継の実務―士業間連携と対応のポイント―』(新日本法規出版、2017年)編著
『〔改訂版〕事例でみるスタンダード相続手続―士業間連携による対応方法―』(新日本法規出版、2018年)編著等
『事例でみる スタンダード債権回収手続―専門家の視点と実務対応―』(新日本法規出版、2019年)編著
『相続対策別法務文例作成マニュアル―遺言書・契約書・合意書・議事録―』(新日本法規出版、2020年)著等
執筆者の記事
執筆者の書籍
関連カテゴリから探す
-

-

団体向け研修会開催を
ご検討の方へ弁護士会、税理士会、法人会ほか団体の研修会をご検討の際は、是非、新日本法規にご相談ください。講師をはじめ、事業に合わせて最適な研修会を企画・提案いたします。
研修会開催支援サービス -