一般2025年02月26日 アスリートに対する誹謗中傷の問題点と今後求められる取組み(誹謗中傷問題連載⑤) 一般社団法人日本スポーツ法支援・研究センターからの便り 執筆者:高橋駿
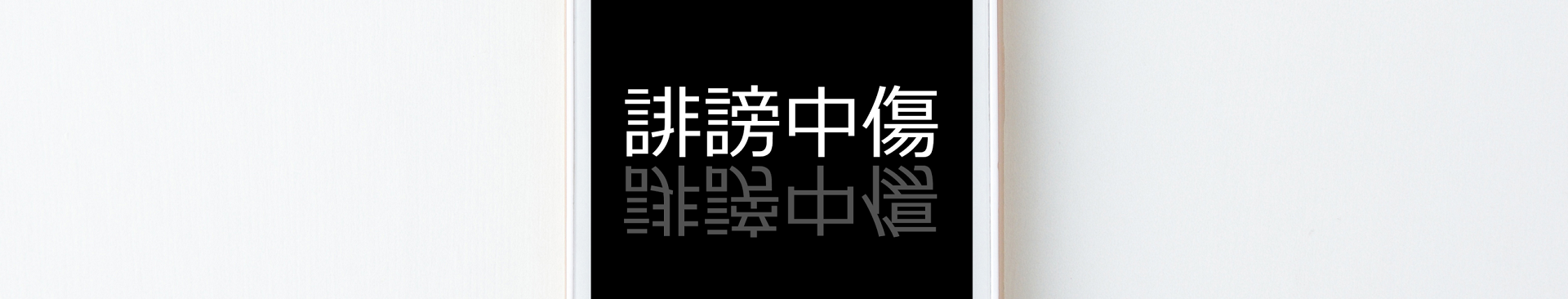
第1 アスリートに対する誹謗中傷の問題点
心無い誹謗中傷を受け、苦しみ悩んでいるアスリートは多く、筆者も弁護士として多くの相談を受けている1。
誹謗中傷は、被害者となったアスリートのメンタルに大きな影響を及ぼすものであり、結果的に、アスリートが不安や恐怖を感じ、競技に集中できなくなったりする等の被害が生じている。
そして、誹謗中傷によりもたらされるアスリートのメンタルヘルス不調は、アスリートのパフォーマンスの低下をも招くことになる2。
誹謗中傷の問題については、被害者であるアスリート自身にとって重大な問題であるのはもちろんのこと、当該アスリートが所属しているクラブ・チームや協会関係者、当該アスリートの素晴らしいプレーを期待するファンを含むスポーツに関わるステークホルダー全体が一丸となって取り組むべき問題というべきである。
第2 アスリートと所属チームやクラブ・協会との関係性を踏まえた誹謗中傷対策
誹謗中傷への対策としては、過去の連載記事に記載のとおり、法的手段を用いること等が考えられるが3、どの組織が主体的にこの問題に取り組むべきなのか。
この点、アスリートへの誹謗中傷対策については、所属チームやクラブ・協会等といった組織のコミットが重要ではあるものの、外部の独立した組織(選手会等)が対策の主体となることも重要であると考えられる。
なぜなら、アスリートと所属チームやクラブ・協会等といった組織との関係は、常に「選ぶ側と選ばれる側」という緊張関係にあり、アスリートは、その構造上、メンタルヘルス等の要素が含まれる相談事項について、所属チームやクラブ・協会等に相談しにくいという状況が考えられるためである4。現に、アスリートは「心の状態について他者に話すことに抵抗を持つ選手が多いこと、チーム内のスタッフは特に相談しにくいこと」が明らかになっている56。
そして、誹謗中傷の問題については、被害者であるアスリートから相談を受ける際には、必然的に「心の状態」についての相談内容(「投稿により嫌な思いをした」、「恐怖を覚えた」等といった内容)を含むことになるため、誹謗中傷対策を主体的に行う機関については、仮に当該アスリートの所属チームやクラブ・協会等が一時的な窓口になるのだとしても、プライバシー等に配慮した形で、外部の機関や選手会等における相談窓口と連携したり、これを活用することで、チームやクラブ・協会等とは独立した機関が誹謗中傷対策を担う等の工夫をすることが重要である7。
このような座組を用意し、かつ、周知することで、アスリートに対して、誹謗中傷の被害にあったとしてもいつでも利害関係のない第三者へ相談できるという安心感を与えることができれば、アスリートの競技パフォーマンスを高める効果も期待できるだろう8。
第3 アスリートはSNSをやめるべきなのか。
誹謗中傷の問題に対して、「そもそもアスリートはSNSを使わなければいい」等といった対策を提示する有識者もいる。
たしかに、一切SNSを見なければ、誹謗中傷を目にして傷付く機会を減少させることができるかもしれない。もっとも、アスリートの短い競技人生において、引退後も見据えたセルフブランディング構築の観点で言えば、SNS等の利用は当該選手にとっては大きなメリットになりうるところ、そのメリットを得る機会を「誹謗中傷をしたい人」のためにアスリートに放棄させるのは酷というほかない。
また、アスリートの中にはファンとのつながりを重視し、それにより大きなモチベーションや力を得ている選手も多い。SNSを辞めろという対策は、これらのメリットを享受するなとアスリートに強いることになりかねない。
さらに言えば、そもそも、アスリートがSNSをやめたところで、第三者を通じて被害の実態を見聞きしてしまうことも多く、問題の根本的な解決には至らないばかりか、アスリートからSNSの利用の機会を奪うことは、アスリートがSNSを使った対抗言論による自衛(自身に関するニュースや週刊誌の誤報道などを指摘する)の手段を奪うことになり、この点は明確なデメリットといえる。
以上から、アスリートに対して「SNSを使わなければいい」という対策のみを押し付けるのはアスリート目線の意見ではないというのが筆者の見解である。
あくまで誹謗中傷対策は、アスリートファーストという観点からも、アスリートがSNSを利用することを前提として(相談窓口の設置やAIによる誹謗中傷のフィルタリングシステムの導入等)構築することが重要ではないか。
1 弁護士ドットコム株式会社の実態調査によれば、誹謗中傷の対象として「スポーツ選手」が対象になりやすい傾向があるといえる
(https://www.bengo4.com/corporate/news/article/k5mz4nbhm/)。
2 アスリートのメンタルヘルス不調がもたらす問題については、『日本ラグビーフットボール選手会によるPlayer Development Programの実践報告』(2022.10.1)等に詳しい(https://www.jstage.jst.go.jp/article/sposun/32/4/32_4_481/_pdf)。
3 『SNS上のアスリートに対する誹謗中傷への法的対応について(誹謗中傷問題連載③)』(2024.12.17)参照
(https://www.sn-hoki.co.jp/articles/article3857911/)。
4 オリンピック等の大規模な大会を中心に、各国協会には代表選手の選考権限が与えられているし、チームやクラブはどの選手を試合に起用するかについての権限を有している。したがって、アスリートがこれらの組織にメンタルヘルス等の悩みを相談することについては、選考・起用にどのような影響を及ぼすのかという不安等(「メンタルが弱い」と思われてしまうのではないか等)が内在してしまうため、それ自体を躊躇してしまう可能性があると考えられる。
5 注2の483頁参照。
6 『選手の心の悩み「チーム関係者には特に話しづらい」"第三者"が支えるPDPとは?ラグビー選手会が試験導入』(2022.7.25)参照
(https://www.huffingtonpost.jp/entry/story_jp_62bbb2f2e4b056531639bff3)。
7 誹謗中傷に関する外部相談窓口として、筆者が関わっているCOAS等の団体も存在している(https://www.coas-lawyers.com/)。
8 アスリートの将来への不安という問題点に対して、キャリア支援を行うことが競技パフォーマンスを高める効果があることがわかっている(注2の482頁以下参照)。この点、誹謗中傷による被害をもし受けたらという不安に対しても、相談窓口を設置し、その存在を周知したりすることで、競技パフォーマンスにポジティブな影響を及ぼすことが期待できる可能性がある。
(2025年2月執筆)
(本コラムは執筆者個人の意見であり、所属団体等を代表するものではありません。)
(本記事の内容に関する個別のお問い合わせにはお答えすることはできません。)
人気記事
人気商品
一般社団法人日本スポーツ法支援・研究センターからの便り 全29記事
- スポーツ界におけるフリーランス保護法の影響
- 「スポーツを観る権利」~ユニバーサルアクセス権から考える~
- 日本人陸上選手のアンチ・ドーピング規則違反についてのCAS決定
- 武道と法規範~合気道を例に
- スポーツ団体による事実認定と立証の程度
- アスリートに対する誹謗中傷の問題点と今後求められる取組み(誹謗中傷問題連載⑤)
- SNS上のアスリートに対する誹謗中傷の具体的事案及び法的分析(誹謗中傷問題連載④)
- SNS上のアスリートに対する誹謗中傷への法的対応について(誹謗中傷問題連載③)
- 国内におけるアスリートに対する誹謗中傷問題への対応(誹謗中傷問題連載②)
- 国際大会におけるアスリートへの誹謗中傷とその対策(誹謗中傷問題連載①)
- 部活動の地域移行、地域連携に伴うスポーツ活動中の事故をめぐる法律問題
- スポーツにおけるセーフガーディング
- スポーツ仲裁における障害者に対する合理的配慮
- スポーツ施設・スポーツ用具の事故と法的責任
- オーバーユースの法的問題
- スポーツ事故の実効的な被害救済、補償等について
- 日本プロ野球界におけるパブリシティ権問題の概観
- パルクール等、若いスポーツの発展と社会規範との調和
- ロシア選手の国際大会出場に関する問題の概観
- スタッツデータを取り巻く法的議論
- スポーツ事故における刑事責任
- スポーツに関する通報手続及び懲罰手続に関する留意点
- スポーツ界におけるフェイクニュース・誹謗中傷
- スポーツと地域振興
- アンチ・ドーピング規程における「要保護者」の特殊性
- スポーツにおけるパワーハラスメントについて考える
- アスリート盗撮の実情とその課題
- アンチ・ドーピングについてJADA規程に準拠しない競技団体とその課題
- スポーツチームにおけるクラブトークンの発行と八百長規制の必要性
執筆者

高橋 駿たかはし しゅん
弁護士(Field-R法律事務所)
略歴・経歴
2016年 早稲田大学法学部卒業
2018年 早稲田大学法科大学院修了
2020年1月 シティユーワ法律事務所 入所
2024年2月 Field-R 法律事務所 入所
取り扱い分野の中心はスポーツ法務や企業法務
・中央大学法学部非常勤講師(2023年~「健康・スポーツ科学B(スポーツ法)」担当)
・日本スポーツ法学会 スポーツ契約等研究専門委員会 副委員長(2023年〜)
・スポーツ界における誹謗中傷抑止のための団体「COAS」代表
その他経歴、肩書などは、https://field-r.com/people/shun-takahashi/参照。
執筆者の記事
関連カテゴリから探す
最近閲覧した記事
-

-

団体向け研修会開催を
ご検討の方へ弁護士会、税理士会、法人会ほか団体の研修会をご検討の際は、是非、新日本法規にご相談ください。講師をはじめ、事業に合わせて最適な研修会を企画・提案いたします。
研修会開催支援サービス -























