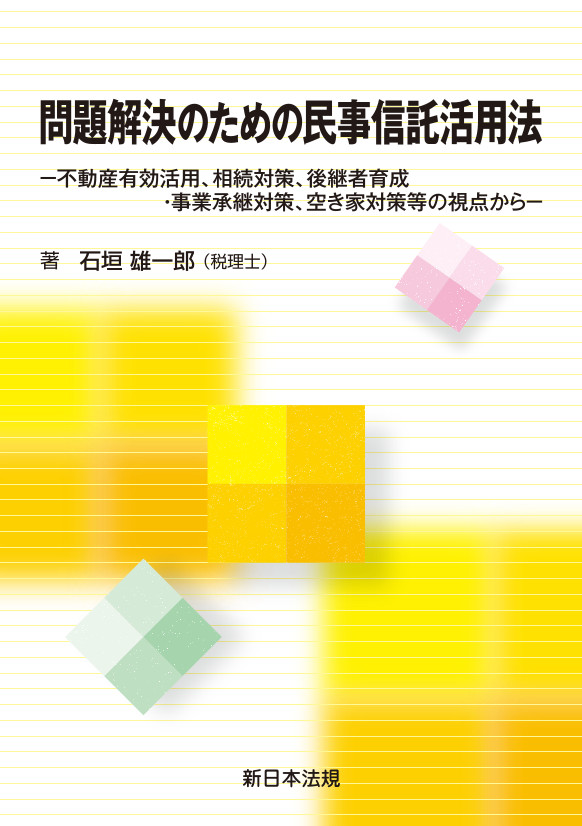相続・遺言2020年03月12日 民事信託こぼれ話 第4話(後編) 信託受託者として一般社団法人を新設した事例~受益権設定をめぐる法律の専門家と実務者の見解の相違~ 民事信託特集 執筆者:澁井和夫

今回の事案では、委託者の要望が多岐にわたり、かつ信託財産の承継についても具体的な指示が示されていたので、これらに応えるべく契約に盛り込む内容の検討を行う一方、実務的に委託者の要求を実現し達成できる態勢の整備、仕組み作りにも注力しました。信託受託者を一般社団法人として、長期的に信託受託者の地位を安定させる措置を取り入れたのもこのためです。
この様々な検討の中で論点となったことについて、補足しておきたいと思います。ここでは、次の3点について考察してみます。
〇第2次受益者が多数になる場合の受益者代理人の設置
〇信託受益権と相続の関係
〇受託者の安定性・継続性の検討
5.第2次受益者が多数になる場合の受益者代理人の設置
前編で記述したとおり、委託者の要望は、自分の死後、信託財産の受益権は、先ず兄弟姉妹かその子たちに引き継がせ、最終的に1人の男子(甥の子:信託設定時未成年者)に集中させようとするものでした。
このとおりに信託スキームを組成した場合、第2次受益者あるいは第3次受益者は多数になります。一旦、資産は大勢の親族に受益権の形で共有され、その上で親族の中の1人に、その多数に分割された受益権が集中して承継される過程を辿ります。
筆者は実務者として、このような案を拒否したため、このスキームは回避されましたが、不動産が信託受益権に形を変えて多数の受益者に配分されるスキームは、信託の特徴的な方法として、例えば不動産の証券化などの世界では、当たり前に行われている手法です。
不動産の証券化などの世界では、信託受益権が金融商品として位置づけられ、金融商品取引法や信託業法など、いわゆる商事の世界で信託受益権が取り扱われ、信託受益権を購入する不特定多数の投資家に対して、消費者保護や投資家保護の観点から様々な法的な手当が行われています。現信託法改正時に新設された「受益者代理人の制度」もそのひとつです。
しかし、それが本事案のような親族の信託で使うのがよいかどうかには疑問があります。
本事案では、結果として当初受益者の受益権を親族に分割承継させるスキームを取らず、直接最終の承継者にそっくり引き継ぐ仕組みとしましたが、中間的には、本事案においても、受益者代理人を置いて、多数の信託受益者の利益の保護と信託事務の円滑な処理を確保できるようにしてはどうかと検討がなされました。
受益者代理人は、信託契約の中に信託代理人となるべき者を指定する定めをすれば、これを選任することができます。そこで、受益者となった多数の親族がそれぞれの代理人として共通して1人の親族を選任することにすれば、多数の親族の受益者の権利を代理人として選任された1人の親族が代理することとなり、受益者と受託者の間のやり取りは円滑になるであろうと考えるわけです。仕組みとしてそれは可能なのですが、実務者としては、その仕組みが実質的に適切に機能するかどうか心配が残ります。仮に、信託の設定時は親族間の足並みが揃っていたとしても、その後の時間の経過によりそれぞれの親族の状況は変化します。その中で破綻が生じないか、また、代理人の代理人たる責任もそれなりに重いので継続してやり切れるか、万一代理人が欠ける事態となったときはどうするか等々です。一方で、受託者は受益者の意思判断が一本化されていないと、信託財産の運用管理の事務に支障をきたす事態を恐れます。受益者の権利や利益の保護と受託者の信託事務の円滑な処理とが背反すると信託は立ち往生してしまいます。
というわけで、本事案において結果として、中間的に多数の信託受益者が生まれる信託スキームは採用しなかったのです。
6.信託受益権と相続の関係
信託受益者が多数生じると、受益者の意向がバラバラになって信託受託者の事務に支障をきたす恐れがあることは、5.で述べましたが、信託受益権は相続との関係でどのような取扱いになるのでしょうか?これも、信託受益権が複数に分割されると、その行く末は更に細分化していきそうで不安定な感がします。本事案では、最終的に1人の親族に受益権は集中し、資産は分散化せず継承されることが大きな目的となっていますが、中間的に受益権が親族間に分割所有された後、本当に1人の親族に集中させることは、民法の相続の規定に反することなく実現できるのでしょうか?
(1) 法的な考察
(受益者の死亡により他の者が新たに受益権を取得する旨の定めのある信託の特例)
信託法第91条 受益者の死亡により、当該受益者の有する受益権が消滅し、他の者が新たな受益権を取得する旨の定め(受益者の死亡により順次他の者が受益権を取得する旨の定めを含む。)のある信託は、当該信託がされた時から30年を経過した時以降に現に存する受益者が死亡するまで又は当該受益権が消滅するまでの間、その効力を有する。
これが、いわゆる「跡継ぎ遺贈型の受益者連続の信託」であることは、読者の皆さまもご存じのところと拝察します。
この条文にある「受益者の死亡により順次他の者が受益権を取得する旨の定め」を信託契約のなかに丁寧に書き込めば、本事案のような信託委託者の要望は法的な効力を有し、実現可能となると考えられます。
民法の相続では、被相続人の所有権が相続の対象と考えられます。所有権は恒久的な権利です。したがって、「期限付きの所有権」という概念は認められません。
一方、信託受益権は所有権ではありません。その存続期間を契約などで定めることが可能です。ですから、「受益者の死亡」を信託受益権存続の期限とし、期限到来で受益権は消滅すると定めることができます。それと同時に新たな受益権を生じさせ、それを新たな受益者に取得させることも可能です。また、信託受益権の内容についても、信託契約の中に定めることができます。信託財産からどのような利益を受益者に与えるのか信託契約の中に細かく書き込むこともできます。
ところで、委託者が信託した信託財産の所有権は受託者が保有しています。信託財産は信託が終了するまでは受託者が所有し、信託が終了すると信託契約の定めにより信託残余財産帰属者に引き継ぎます。信託受益者が信託残余財産帰属者になることは自然な形だと思いますが、そうしないこともできないわけではありません。
以上のように、所有権と信託受益権は権利の概念が違うので、「跡継ぎ遺贈型の受益者連続の信託」が認められたと考えられます。
ただし、注意しなければならないのは、法律上有効と言えるものの、民法の遺留分制度を潜脱することは許されないことです。
本事案の場合、委託者は、「受益者を指定し、または変更する権利」を持っていますから、受益者連続の信託を行うことはできますが、その過程において、遺留分潜脱に当たるようなことが起きないかどうか(親の取得した信託受益権が財産権として子に相続されることはないのか)、筆者には不安がありました。そこで、遺留分潜脱のおそれがない方法として、委託者兼当初受益者である甲の次の受益者をいきなり甲の甥の子のCにすることにしたのです。この局面で、甲の相続人は甲の兄弟姉妹と兄弟姉妹の代襲相続人の甥姪しかいませんので、遺留分侵害額請求の権利を有する者はいません。信託財産の受益権は100%、Cが取得できます。
(2) 税務の考察
税務では、信託財産の所有者は信託受益者とみなします。法的には、信託財産の所有権は委託者兼受益者である「甲」から、「は」を理事長とする一般社団法人「○○家族トラスト」に移転し、この法人が所有者となりますが、税務は委託者が当初受益者であって、受益権が「甲」にある限り、所有権の移転はないものとみなすわけです。したがって、「甲」からこの法人への所有権移転登記の登録免許税は非課税です。信託財産の所有者となったこの法人に、不動産取得税も課税されません。税務は、信託財産である不動産の名義は形式的に移転しただけで、実質的な所有者は「甲」であると判定しているからです。
そこで、今後信託受益権がどのように移転するか(誰が新たに信託受託者になり、「甲」の信託受益権を引き継ぐのか)に応じて、課税をしていくものと考えられます。
その信託受益権の移転が、信託財産である不動産の売買とみなされるのか、贈与とみなされるのか、相続あるいは遺贈とみなされるのか、それらの実態に応じて財産の移転があったとして課税を行うことになると考えられます。
本事案の当初案のように信託受益権が第1次受益者から順次第4次受益者に引き継がれる場合、その引継ぎの都度、不動産に関する権利の移転があったとみなされ、課税がなされることになるでしょう。これらを全てひっくるめて税額の試算を行うなどの作業は、実務的には不確実で極めて煩雑な、意味のないものとならざるを得ません。また、納税義務者も多岐にわたることが予想されますので、結局はこのプロジェクトを支えていく信託受託者に実務上の負担が生じてくるものと思われます。最終案はこれらを回避する案としたわけです。
7.受託者の安定性・継続性の検討
本事案の特徴として、委託者が第2次受益者として未成年者を指名している点があります。委託者兼当初受益者である「甲」は90歳に近い高齢者で、第2次受益者である甥の子の「C」は10歳に満たない未成年者ですから、委託者兼当初受益者が亡くなった後、しばらくの間、第2次受益者は未成年であることが想定されます。
したがって、受益者のために信託財産の管理運用に当たる受託者は、この資産の承継を全うすべく、親族の一員として大きな責務を負うことになります。
通常、民事信託では、受託者が委託者の親族の一員である個人である場合が多いのですが、本事案の場合、受託者の安定性、継続性を重んじて、受託者を個人でなく一般社団法人としました。本事案では、委託者には子がありません。相続人は兄弟姉妹とその代襲相続人の甥姪で、多人数です。子がいれば、それが複数いたとしても、その中で資産を承継する者を選ぶのが自然な道筋でしょう。特別な事情がない限り、子が財産を承継することに異論を唱える親族はいないと思います。しかし、本事案の場合は子がいませんので、他の親族としても、被相続人に生前に財産承継について明確な意思表示をしてもらった方が安心であると思われます。それが本事案の眼目でもあるわけです。遺言に代わる役割を果たす親族間の信託です。
ところで、受託者が個人の場合、受託者が病気になったり、事故に遭ったり、また不慮の死を遂げるおそれもあるので、不安定な面は否めません。通常はこれを補うため、あらかじめ「新たな受託者」(第2次受託者)を決めて信託契約に明示しておく方法がとられます。例えば、委託者が親の場合、その子達のうち長男が受託者になり、親と長男の間で締結する信託契約に、「長男が欠けた場合は二男が受託者になる」というように書き込み、このことについて、二男の同意を得ておくという方法です。これなら、長男に万一のことが起こっても、すぐに二男が受託者の事務を引き継ぐことで、信託事務が滞ることを防げます。信託終了まで長男が受託者の役割を全うできた場合は、二男の出る幕はありませんが、あらかじめこのように決めておくことで長男も安心です。
すなわち、受託者が欠けてしまうと信託の事務は止まってしまうので、実務上は困ったことになります。「受託者不在」となることは回避しなければなりません。受託者が信託事務の切り盛りをしているわけですから、これがいなくなると信託は機能不全に陥ってしまいます。このように、信託を円滑に安定的かつ継続的に行いうる態勢を確保することは重要なことです。本事案の場合は、個人から個人へ引き継ぐ形の態勢を整えておくのではなく、個人ではない法人を受託者にすることで、これを確保することにしました。親族は受託者法人に参加することやその活動報告を知ることで信託にタッチしていけます。また、経理や税務・法務の専門職能者を法人に取り込むことで信託事業の円滑な運営を図ることもできます。
しかし、法人が信託受託者になる場合には、信託業法に触れないように留意しなければなりません。反復継続して信託を引き受けることになると、「業として」信託を行うことにつながり、信託業の届出など、信託業法上のルールが適用されることになります。つまり、民事の枠からはみ出して商事の世界に入ってしまいます。
特に、株式会社などの本来営利を目的とする法人を設立して信託受託者の事務を行うことは、民事信託を逸脱し、商事信託としての信託の引受けを行っているとみられることも十分考えられ、この点には注意が必要と思われます。
(2020年3月執筆)
人気記事
人気商品
民事信託特集 全22記事
- 民事信託こぼれ話 第10話
- 民事信託こぼれ話 第9話
- 民事信託こぼれ話 第8話(後編)
- 民事信託こぼれ話 第8話(前編)
- 民事信託こぼれ話 第7話
- 民事信託こぼれ話 第6話(後編)
- 民事信託こぼれ話 第6話(前編)
- 民事信託こぼれ話 第5話
- 消滅する受益権(信託法91条)の時価評価~平成30年9月12日東京地裁判決を前提に~
- 民事信託こぼれ話 第4話(後編)
- 民事信託こぼれ話 第4話(前編)
- 税理士業務の中の民事信託(第4回)
- 民事信託こぼれ話 第3話(後編)
- 民事信託こぼれ話 第3話(前編)
- 民事信託こぼれ話 第2話(後編)
- 民事信託こぼれ話 第2話(前編)
- 民事信託こぼれ話 第1話(後編)
- 民事信託こぼれ話 第1話(前編)
- 税理士業務の中の民事信託(第3回)
- 税理士業務の中の民事信託(第2回)
- 税理士業務の中の民事信託(第1回)
- 後見と民事信託
執筆者

澁井 和夫しぶい かずお
世田谷信用金庫顧問
略歴・経歴
三井信託銀行(株)(現・三井住友信託銀行(株))入社後、不動産開発部長兼不動産鑑定部長を最後に退社、その後㈱鑑定法人エイ・スクエアを設立し、取締役副社長を務め、(社)日本不動産鑑定協会(現公益法人日本不動産鑑定士協会連合会)主任研究員を経て、世田谷信用金庫顧問に至る。 世田谷信用金庫では、2007年6月のコンサルティング・プラザ玉川(最寄駅:東急田園都市線「二子玉川駅」)開設を機に、信託・不動産に精通するスタッフを投入して、高齢者の不動産を主とした資産の管理に、信託スキームを提案するコンサルティング業務を手がけるなど、金融界における民事信託の先駆者でもある。
不動産鑑定士、資産評価政策学会理事。
執筆者の記事
執筆者の書籍
最近閲覧した記事
-

-

団体向け研修会開催を
ご検討の方へ弁護士会、税理士会、法人会ほか団体の研修会をご検討の際は、是非、新日本法規にご相談ください。講師をはじめ、事業に合わせて最適な研修会を企画・提案いたします。
研修会開催支援サービス -

Copyright (C) 2019
SHINNIPPON-HOKI PUBLISHING CO.,LTD.