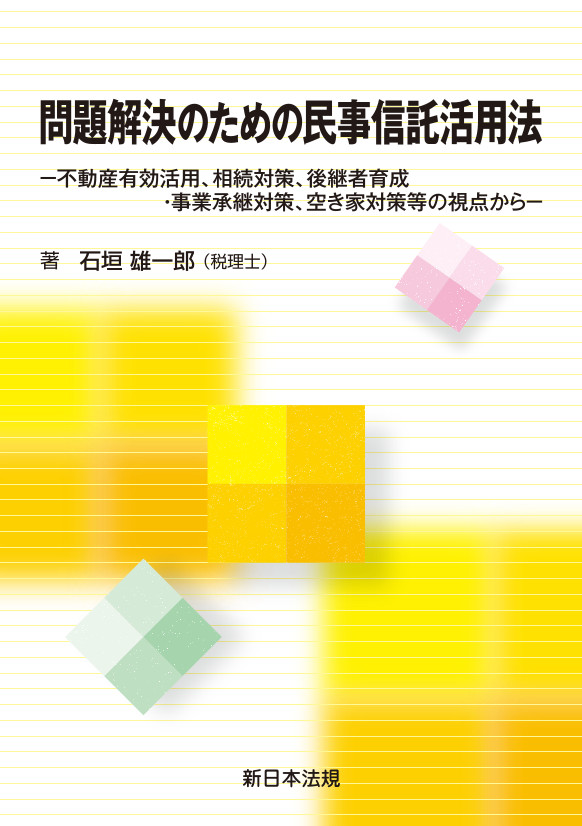相続・遺言2020年02月03日 民事信託こぼれ話 第3話(後編) 続・信託口をめぐる話 民事信託特集 執筆者:澁井和夫

第3話は、あくまで私見であることを前提としながら、本稿では、前稿において先送りした論点「預貯金を信託できるか」について、記述することとします。
なお、①預金保険の取扱い ②「信託口であることを金融機関に告げずに口座開設した場合」の留意点、③「信託口開設時の金融機関の関心事」については、第2話(前編・後編)をご参照ください。
2.「預貯金」を信託できるか
(1)原則として「預貯金」は信託できない
前回のこぼれ話(民事信託こぼれ話第3話前編)で触れたとおり、一般論として、預貯金債権は指名債権であり、通常、金融機関の定める約款により「譲渡禁止特約」が付されています。ですから、金融機関にお金を預けている者(寄託者)が勝手に、寄託債権である預貯金債権を第三者に譲渡することは禁止されています。
したがって、金融機関が「譲渡禁止特約」が付されているにも拘わらず、この特約を解約した場合(譲渡について例外的に承諾した場合)を除き、信託契約者である委託者の預貯金を「譲渡禁止特約」を破って、信託契約締結を拠り所に受託者に移転することはできないと考えられます。
そもそも信託は、信託財産の委託者から受託者への財産権の移転があってはじめて効力を発すると考えられるので、この信託の成立要件の「財産権の移転」と預貯金の債務者(金融機関)による「譲渡禁止特約」とは相反するので、権利の移転が認められないのでは、信託そのものが有効に成立していないと解される恐れがあります。
したがって、前編に登場した信託契約の「信託預貯金に関する権利は、本信託開始日に受託者に移転する。」のように、「預貯金」を寄託している(預けている)金融機関の承諾を得ずに、信託委託者が委託者名義の「預貯金」(消費寄託債権)を受託者に移転するとした信託契約は、乱暴ではないかと言わざるを得ません。果たして、これが有効なのかどうか、(当該金融機関が預貯金者の名義の変更を追認してくれればよいのかもしれませんが)疑義があるところです。
寄託と言えば、荷物の一時預かりが典型的な例ですが、寄託の場合は、受寄者は受寄物そのものを返還する義務を負います。カバンを預かったとすると、その特定された預かったカバンそのものを返還しなければなりません。しかし、消費寄託では、預かったモノそのものを返す義務はなく、預かったモノと同じ価値(同等、同種、同量)のモノを返せばよいので、1万円札を10枚、10万円預かったとして、預かった1万円札10枚そのものを返さなくとも、違う番号の1万円札でもよいから1万円札を10枚返せば義務を果たしたことになります。
指名債権は、その譲渡において、原則として、債務者への通知又は債務者の承諾を要します。債務者が異議を申し立てず承諾したときは、債務者は譲受人に対抗できません。
(2)金融機関の対応
では、一般論として、金融機関はどのように対応するでしょうか。これは前編と同様になりますが、「譲渡禁止特約」に抵触せずに、実質的に同様の効果をもたらす方法として、委託者名義の預貯金を解約により払い出し(この行為は信託受託者ではなく、預貯金名義人の信託委託者に求められるケースが通例でしょう。信託契約により当該預貯金は信託財産になったのだから、信託受託者が解約できるという主張は認められないと思います。では、当該預貯金の解約手続について、信託委託者から代理権を付与されていたらどうでしょうか。つまり、信託契約に基づくのではなく、別の代理契約によって、当該預貯金の解約行為を信託委託者の代理人として信託受託者が行おうとするものです。これは、本稿の「預貯金を信託できるか」から外れた話ですが、可能であると考えます。ただし、金融機関は、この代理関係について、本人に意思確認すべきと考えるでしょう。そのために、個々の金融機関がどのような方法をとるのかは、それぞれの金融機関の裁量に委ねられます。もっとも確実な方法は、金融機関の担当者が、本人である信託委託者を訪問して面談し、意思確認をとる取扱いです。)、払い出された解約金を信託受託者の「信託口口座」に払い込む事務手続を執ると考えられます。つまり、これは、「預貯金を信託する」のではなく、「金銭を信託する」行為に信託される財産の内容が変えられているのです。
この際、第2話で触れたとおり、金融機関は、窓口に現れて払出の手続をしようとしている者がいったい何者であるのか、しっかりと確認しなければなりません。当該預貯金の名義人と信託契約を締結したと言っているが、それは真実か。信託受託者だと言っているが本当にそのような立場にあり、預貯金を取り扱う権限を持っているのか。持っているとすればその根拠は何か。信託受託者本人である証拠はあるのか。このような確認作業には、一定の時間を要し、窓口に来た者以外から聞取り確認をするなどの手間も必要かもしれません。どのような確認の手続を、どれくらい詳細にしなければならないか、現状では、金融機関に共通したガイドラインのようなものはありません。やがて、共通の取扱手続がまとめられていくと期待されますが、現段階では、まだまだ整備に時間を要する段階と言わざるを得ません。
(3)そもそも「信託」は「譲渡禁止」の対象として妥当か
以上述べたように、現状の実務においては、預貯金は指名債権とされ、商品として「譲渡禁止特約付」であるから、権利の移転を要件とする信託は、原則としてできないと解されます。(注:あらかじめ譲渡が認められている「譲渡性預金=CD」という商品があることからも、通常の預貯金は原則譲渡不可であることがわかります。)
実務的な整理はそれで終わりなのですが、さらに一歩突っ込んで、そもそもこの譲渡禁止特約が、信託に因る権利移転をも予定したものであったのかというと、不明と言わざるを得ないと思われます。信託の委託者がイコール受益者でもある場合、信託財産の名義は受託者に移転するものの、実質的な権利は受益者である委託者、すなわち、信託前の権利保持者に留まっているとされている(税務上も受益者を信託財産の持主とみなし、財産の受託者への移転は形式的な移転に過ぎず、実質的には委託者(=受益者)のままとみなし、このため、不動産の信託に因る所有権の移転登記の登録免許税は非課税とされています。)ので、このような形式的な移転(実質的には財産権は移動しない。)についても、譲渡禁止の対象となるのかは議論されたことがないのではないかと思います。つまり、信託財産の特殊性について、預貯金の事務においてどのように取り扱うかを正面から議論したことはないと考えられます。
筆者は、預貯金の譲渡禁止特約は、預貯金の実質的な権利者の権利が移転することを禁止しているのであって、実質的な権利の移転が起こらない場合は、これに当たらないのではないか、「信託に因る名義移転」は従来の「譲渡禁止特約」の対象から逸脱しているのではないかと考えますが、この議論も現状では手がついていないと言えましょう。
繰り返しになりますが、預貯金の信託を行うためには、その前提として預貯金の譲渡禁止特約を何らかの形で解約する手続が必要であり、一方金融機関は、実務上こなれている方法として、預貯金を解約して新たな名義先へ振り込むという手続を採用し、譲渡禁止特約に触れないようにするでしょう。つまり、預貯金の信託は行われず(預貯金は解約されて消滅し解約金である金銭が残ることになります。)、金銭の信託が行われることになるのです。
(2020年1月執筆)
人気記事
人気商品
民事信託特集 全22記事
- 民事信託こぼれ話 第10話
- 民事信託こぼれ話 第9話
- 民事信託こぼれ話 第8話(後編)
- 民事信託こぼれ話 第8話(前編)
- 民事信託こぼれ話 第7話
- 民事信託こぼれ話 第6話(後編)
- 民事信託こぼれ話 第6話(前編)
- 民事信託こぼれ話 第5話
- 消滅する受益権(信託法91条)の時価評価~平成30年9月12日東京地裁判決を前提に~
- 民事信託こぼれ話 第4話(後編)
- 民事信託こぼれ話 第4話(前編)
- 税理士業務の中の民事信託(第4回)
- 民事信託こぼれ話 第3話(後編)
- 民事信託こぼれ話 第3話(前編)
- 民事信託こぼれ話 第2話(後編)
- 民事信託こぼれ話 第2話(前編)
- 民事信託こぼれ話 第1話(後編)
- 民事信託こぼれ話 第1話(前編)
- 税理士業務の中の民事信託(第3回)
- 税理士業務の中の民事信託(第2回)
- 税理士業務の中の民事信託(第1回)
- 後見と民事信託
執筆者

澁井 和夫しぶい かずお
世田谷信用金庫顧問
略歴・経歴
三井信託銀行(株)(現・三井住友信託銀行(株))入社後、不動産開発部長兼不動産鑑定部長を最後に退社、その後㈱鑑定法人エイ・スクエアを設立し、取締役副社長を務め、(社)日本不動産鑑定協会(現公益法人日本不動産鑑定士協会連合会)主任研究員を経て、世田谷信用金庫顧問に至る。 世田谷信用金庫では、2007年6月のコンサルティング・プラザ玉川(最寄駅:東急田園都市線「二子玉川駅」)開設を機に、信託・不動産に精通するスタッフを投入して、高齢者の不動産を主とした資産の管理に、信託スキームを提案するコンサルティング業務を手がけるなど、金融界における民事信託の先駆者でもある。
不動産鑑定士、資産評価政策学会理事。
執筆者の記事
執筆者の書籍
-

-

団体向け研修会開催を
ご検討の方へ弁護士会、税理士会、法人会ほか団体の研修会をご検討の際は、是非、新日本法規にご相談ください。講師をはじめ、事業に合わせて最適な研修会を企画・提案いたします。
研修会開催支援サービス -

Copyright (C) 2019
SHINNIPPON-HOKI PUBLISHING CO.,LTD.