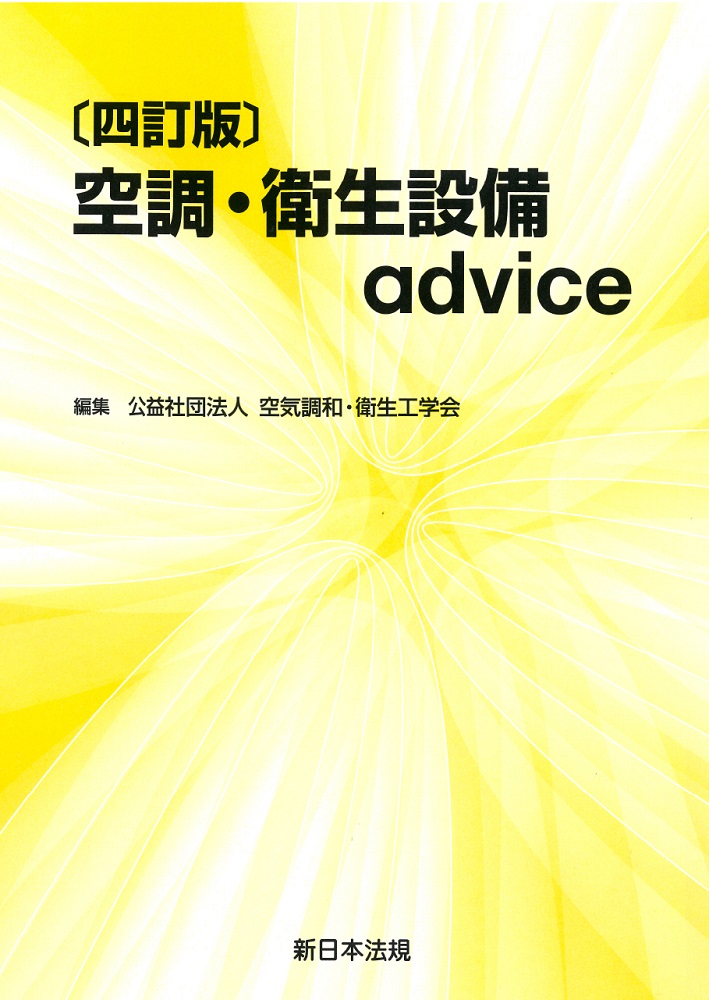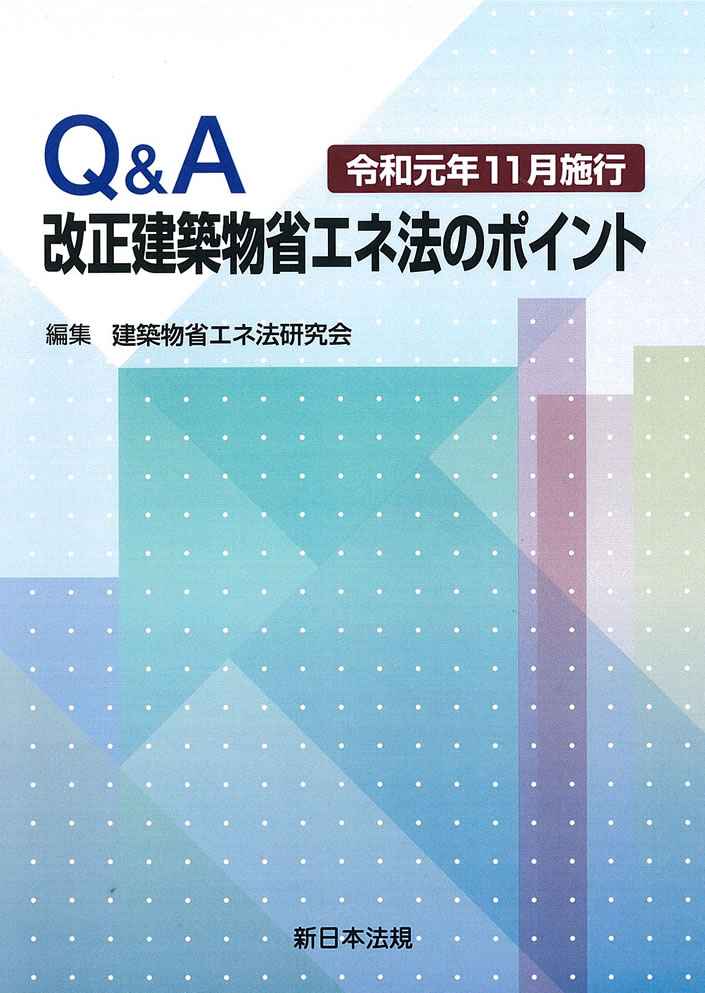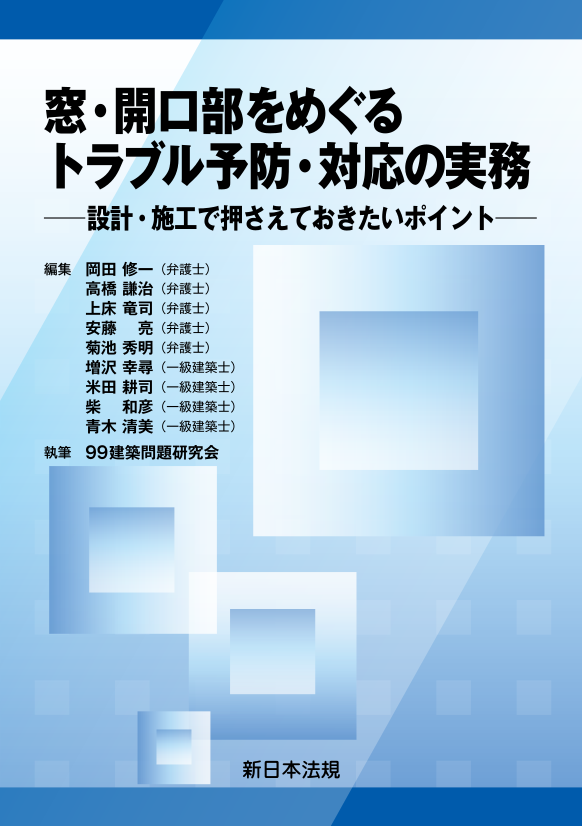環境2022年06月28日 建築物分野での省エネ対策を加速! 法令ダイジェスト 脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律 (令和4年6月17日法律69号)

概要
2050年カーボンニュートラル、2030年度温室効果ガス46%削減(2013年度比)の実現に向け、エネルギー消費の約3割を占める建築物分野での省エネ対策を加速させ、あわせて、木材需要の約4割を占める建築物分野での木材利用を促進し、吸収源対策の強化に寄与するため、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部について所要の改正が行われました。
施行
公布の日から起算して3年を経過した日から施行(一部の規定を除く。)
建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律の一部改正関係
1)題名
題名を「建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律」に改めることとされました。
2)目的
建築基準法の一部改正関係
1)建築確認を要する木造の建築物の範囲の拡大
建築士法の一部改正関係
地階を除く階数が3以下であり、高さが13mを超え、16m以下である建築物及び建築物の部分等を新築する場合における設計及び工事監理については、一級建築士の業務独占範囲から除き、二級建築士がすることができることとされました。
独立行政法人住宅金融支援機構法の一部改正関係
独立行政法人住宅金融支援機構は、住宅のエネルギー消費性能の向上を主たる目的とする住宅の改良に必要な資金の貸付けを行うこととされました。
新日本法規出版株式会社
(2022年6月)
人気記事
人気商品
関連商品
法令ダイジェスト 全42記事
- 社会保険の加入対象の拡大等、年金制度の見直しを実施!
- 就業環境のさらなる整備のために!
- 譲渡担保契約・所有権留保契約のルールを明文化!
- マンションの大規模修繕や建替え・売却の要件が緩和されました!
- さらなる職場環境の整備を推進!
- 児童虐待防止と保育現場の人材確保・体制強化!
- 基礎控除の引上げ等の見直しを実施!
- 子どもを性犯罪から守るための日本版DBS!
- 技能実習制度に代わり、新たに育成就労制度を創設!
- さらなる柔軟な働き方の実現に向けた措置を拡充!
- 離婚後の「共同親権」が導入される!
- 所得税・個人住民税の定額減税を実施!
- 送還・収容ルールの見直しのほか、紛争避難民等の保護が図られました!
- 空き家対策のさらなる強化のために!
- DVから被害者を守るため、 保護命令制度が拡充される!
- 働き方の多様化に対応し、 フリーランスの法的保護を図るために!
- ADRでの和解の一部で、 差し押さえなどの強制執行が可能に!
- 子どもの権利を護るため、 嫡出や懲戒をめぐる規定を120年ぶりに見直し!
- 懲役と禁錮が「拘禁刑」に一本化!
- こどもの権利を包括的に保障する基本法が制定される!
- こども関連政策を担う司令塔として、こども家庭庁が設置される!
- 建築物分野での省エネ対策を加速!
- 子育て世帯に対する支援体制を強化!
- さらなる消費者被害の防止・救済の強化が図られる!
- 民事裁判の全面的なIT化が図られる!
- さらなる利用促進と災害発生の防止のために!
- 賃上げ促進税制が拡充されました!
- デジタル社会における消費者保護が図られる!
- 出生時育児休業制度を新設するなど、 さらなる仕事と育児・介護の両立を促進!
- 匿名者によるネット誹謗中傷被害救済のため、 発信者情報開示制度の見直しが図られる!
- 所有者不明土地問題の解決のために!
- 相続等により取得した土地所有権の国庫帰属が可能に!
- DX投資促進税制が創設されました!
- 中小企業の廃業を防ぎ、成長できる環境を整備するために!
- 事業者の不祥事を早期に是正し、被害の防止を図るために!
- 消費者からの個人情報の利用停止・削除・開示請求への対応が厳格化!
- 全世代型社会保障の構築に向けた改正!
- 高年齢者の就業増加や副業解禁など、昨今の労働環境の変化に対応する改正!
- グループ通算制度が創設されました!
- 土地についての基本理念等が見直されました!
- 賃金請求権の消滅時効期間が3年に!
- 社外取締役設置や報酬決定方針の開示を義務化!