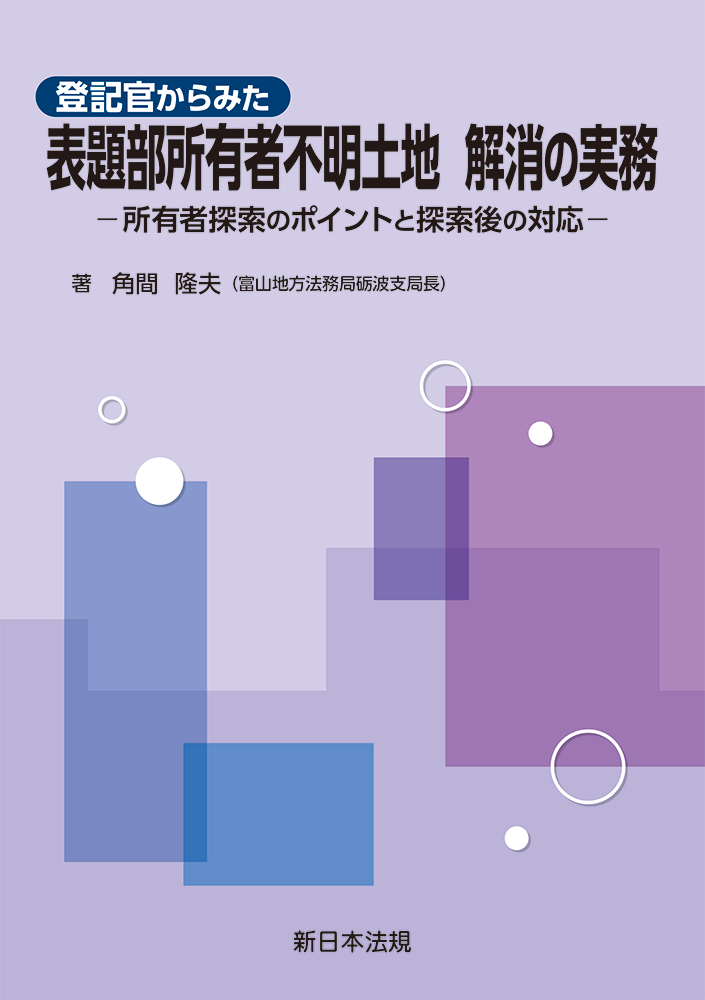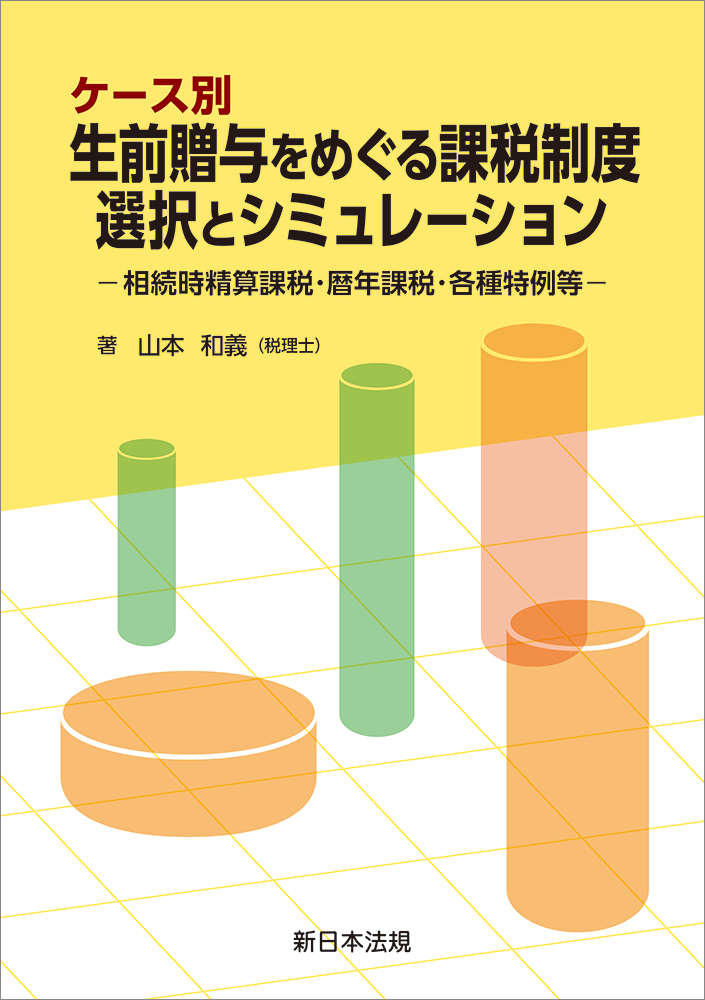一般2005年11月02日 くれぐれも御用心 日本人弁護士が見た中国 一般社団法人日中法務交流・協力日本機構からの便り 執筆者:稲田堅太郎
最近、日本人が中国各地において、覚醒剤や麻薬等の密輸容疑で逮捕され裁判にかけられるという事件が増えています。
大連においても何名かの日本人が裁判にかけられて厳しい有罪判決を受けているようです。
その内の一件では見知らぬ中国人から荷物を預かり、日本に運ぶよう依頼を受けたという事案であったようです。
皆さん、メルボルン事件というのを御存知でしょうか。
随分古い話になりますが、1992年にオーストラリアのメルボルン空港で日本人観光客が所持していた旅行カバンの中から約13キログラムものヘロインが発見されて、一行7人のうち5人がヘロイン輸入の嫌疑で逮捕され裁判にかけられました。
そのまま身柄を長期間にわたって拘束され、2年後の1994年6月10日に判決の言渡があったのですが、なんと4人に対して懲役15年、残りの1人に対しては懲役25年(後に20年に変更されている)の厳しい実刑判決が下されました。
この様なとんでもない事件に巻き込まれた日本人ツアーの一行は安い費用でオーストラリア旅行ができるということで喜びいさんでツアーに参加したのです。
このツアーでは途中マレーシアのクアラルンプールで一泊することになっており、一行は到着後、街のレストランで夕食をとることになりました。ところがレストランで夕食中に車中に置いていた4人の旅行カバンが車ごと何者かに盗まれてしまったのです。そのため大騒動となったのですが、一行を案内していた現地のガイドが必死になって探しまわってくれた結果、ほどなくガイドからカバンが見つかったとの連絡が入りホッとしたのも束の間、カバンが引き裂かれて使用できない状態になっているということで、新しいカバンをガイドの方で用意してもらったのです。一行は親切に対応してくれたガイドさんに感謝しながら、新しいカバンをひっさげてオーストラリアに向けて出発したのです。
恐るべきことに、一行が所持することになった新しい旅行カバンの中に大量のヘロインが何者かによって仕込まれていたのです。おそらく、一行に対して親切にふるまった現地ガイドとその仲間達によって仕組まれたものと思われます。
彼ら日本人にとっては、全く身に覚えのないことであり、冤罪であるということが明白であったにもかかわらず有罪とされ、しかも懲役15年とか25年という厳しい実刑判決が言い渡されたことになります。
オーストラリアという国家からみて彼等が日本人という外国人であることから警察での取調べや裁判において言葉が通じにくかったことや、通訳との意思疎通が充分でなかったことから満足な裁判活動ができなかったことも厳しい実刑判決の要因になっているものと思われます。
その後、この裁判内容があまりにもひどいということから、日本の弁護士達が協力して国際的な支援活動を展開するまでに至っています。
自分の所持しているカバンからヘロイン等の違法な物品が発見された場合、自分の知らないことだといくら弁明してもなかなか通用するものではありません。メルボルン事件で示されたように中国という日本からみて外国に当たる国においてはなおさらのことです。
私自身、大連空港において搭乗手続をしている最中に、次の様な経験がありました。
沢山の荷物を所持して、乳飲子をかかえた若い母親から、通関手続をする際に手荷物を預かってもらえないかという依頼があったのです。乳飲子が泣きさけんでいるために、つい預かってやろうかとの親切心が出かかったのですが、心を鬼にしてことわりました。預かった手荷物の中に、何が入っているか判らないからです。
旅行中には、たとえ幼児づれの若い女性であっても、見知らぬ人からカバン等を預かって通関手続をしないようくれぐれも気をつけて下さいネ。
(2015年10月執筆)
人気記事
人気商品
一般社団法人日中法務交流・協力日本機構からの便り 全122記事
- 中国からの撤退について
- 中国の離婚法制
- 大連訪問と中国の銀行更新手続き
- 中国における定年延長の決定
- 刑法改正のポイント
- 中国「会社法」改正のポイント
- 中国に銀行預金を残して死亡した場合の解約手続について
- 中国所在の不動産を巡る紛争と裁判管轄の問題
- 「老後は旅先で」~シニアの新しい生き方~
- 中国に出資しようとする外資企業に春が来た
- 「企業国外投資管理弁法」の概要
- 楽しさと便利さが、庶民の生活を作る。
- 中国会社法「司法解釈(4)」の要点解説
- 日本産業考察活動メモ
- 長江文明・インダス文明、再来の始まりを予感
- 中国国務院より「外資誘致20条の措置」が公布されました
- 中国の対日投資現状とトレンド(2)~中国の対日投資の論理とトレンド~
- 観光気分の危機管理
- 訴訟委任状に公証人の認証が必要か?
- 『外商投資企業設立及び変更届出管理暫定弁法』の解説
- 婚活は慎重に!とある中国人女性と日本人男性の事例
- 新旧<適格海外機関投資家国内証券投資の外国為替管理規定>の比較
- 中国では、今年から営業税から増値税に切り換え課税するようになりました。
- 土地使用権の期限切れ
- 過度な中国経済悲観論について思うこと
- 『中華人民共和国広告法(2015年改正)』の施行による外資企業への影響(後編)
- 203高地への道
- 中国大陸における債権回収事件(後編)
- 中国大陸における債権回収事件(前編)
- 訪日観光は平和の保障
- 大連事務所15周年&新首席代表披露パーティーを行いました
- 再び動き出した中国の環境公益訴訟
- 「国家憲法の日」の制定
- 中国独占禁止法
- 道路の渡り方にみる日中の比較
- 日本の弁護士と中国の律師がともに講師となってセミナー
- 日中平和友好条約締結35周年に思う
- 中国におけるネットビジネス事情
- 敦煌莫高窟観光の人数制限と完全予約制の実施
- 両国の震災支援を両国民の友好につなげたい
- 公共交通機関のサービス体制
- 「ありがとう」を頻繁に口にすることの効果
- 久しぶりの上海は穏やかだ
- 事業再編の意外な落とし穴
- 強く望まれる独禁法制の東アジア圏協力協定化
- いまこそ日本企業家の心意気を持って
- iPadに見る中国の商標権事情
- 人民元と円との直接取引がスタート
- 中・韓のFTA(自由貿易協定)交渉開始と日本
- 固定観念を打破し、異質を結びあわす閃きと気概
- 若い世代を引きつける京劇
- 大都市は交通インフラが課題だ!
- 杭州市政府の若手職員の心意気
- 13億4000万人を養う中国の国家戦略
- 「命の安全」を考える。
- 大連で労働法セミナーを開催しました
- 中国でも「禁煙」規定が発効
- 中国における震災報道から思う
- IT通信手段は、不可欠だ。
- 日本人は計画的?中国人は行きあたりばったり?
- 広州・北京に見るストライキ事情
- 商業賄賂で処罰
- 大連事務所は開設10周年を迎えました!
- 顔が見える交流
- 日本は人治、中国は法治?!
- 日本の公証人制度
- 充電スタンド建設の加速
- 上海の成熟した喧噪と法意識の違い
- 中国における日本人死刑執行の重み
- 中国の富裕層は日本経済の「救世主」か
- 日本に追いつき追い越せ/パートII
- 国際交流を望む中国研究者にとって日本は遠い国だ
- 「文化産業振興計画」の採択
- 国慶節に思う
- IC身分証明と在日外国人取締強化
- 「日本人は・・・・・」「中国人は・・・・・・・」
- 中国の携帯電話産業
- メラミン混入粉ミルク事件
- 大連市の公証人役場
- 東北アジア開発の動きと長春の律師
- 循環型経済促進法の制定
- 北京オリンピックと私たち
- 四川大震災に想う
- 日・中企業間の契約交渉の実例
- 東アジア共同体
- レジ袋の有料化
- 通訳の質について
- 「中国餃子バッシング」に思う
- 中国の休日
- インドを見てから、あらためて中国を見る
- 日中韓の国境は障害を乗り越え、確実に近くなっている。
- 北京市の自転車レンタル事業から中国の環境政策を見る
- 福田首相と日中友好
- 上海の空、東京の空 四日市公害裁判提訴(1967年)から40年後の今に想う
- 物権法の制定過程
- 司法より行政に権力がある
- 中国の『走出去』戦略を読む
- 中国の環境問題
- 中国のオーケストラ
- 春節
- 「いじめ」は共通語だ!
- 中国を見る眼
- 最高人民法院を訪問しました
- 機内食のコップ あっという間の進歩
- 冷静な眼と暖かい心
- 自主的な総合的力量を備える
- 宴席は丸か四角か
- 「十一五」規画始動!
- 依頼人の人権擁護
- 身の安全
- 中国で「勤勉さ」を学ぶ
- 203高地や旅順口などの戦跡を訪れて思う
- 「ソウルで味わった韓流の逞しさ」
- 中国と日本の立法・行政・司法
- くれぐれも御用心
- 海外旅行は、法リスクの宝庫だ。
- 互いの理解
- 信頼関係の形成に向けて
- 中国憲法における「改革・開放」路線
- 苦情処理センターの効用
- 信頼できる中国人パートナーを得る
- 外国への進出と契約
この記事に関連するキーワード
-

-

団体向け研修会開催を
ご検討の方へ弁護士会、税理士会、法人会ほか団体の研修会をご検討の際は、是非、新日本法規にご相談ください。講師をはじめ、事業に合わせて最適な研修会を企画・提案いたします。
研修会開催支援サービス -