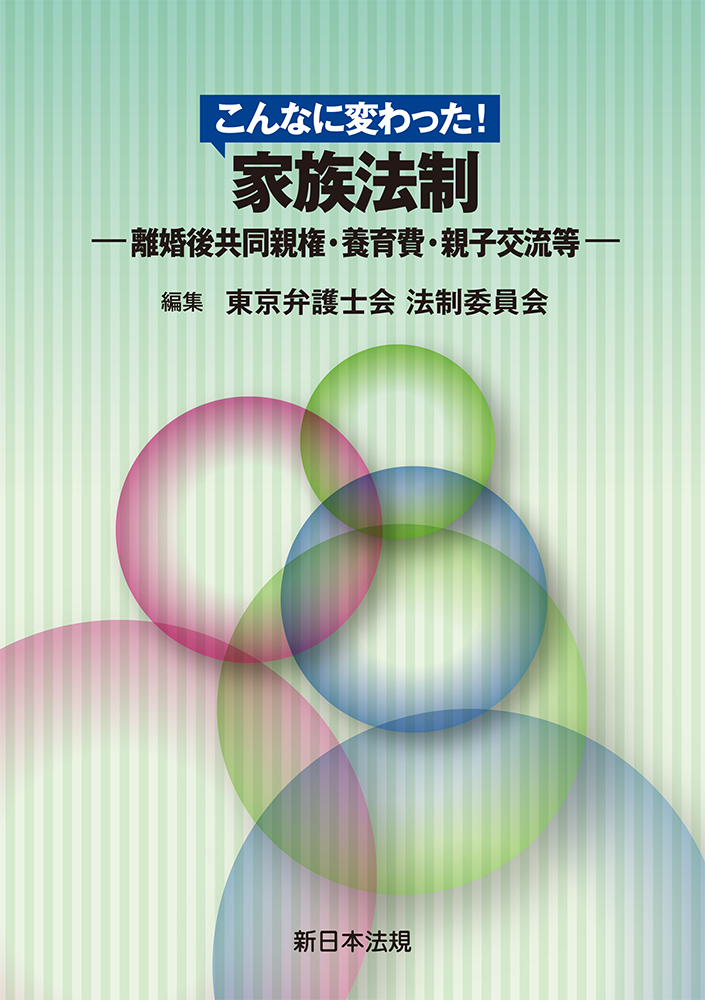一般2018年05月08日 次世代の用地職員への贈り物(法苑184号) 法苑 執筆者:中嶋靜夫

1 公共用地取得事務 五〇年の思い出
思えば、公共用地取得業務あるいはその周辺事務に従事して、五〇年になろうとしています。愛知県庁土木部名古屋土木事務所用地課を皮切りに本庁監理課用地係、知立土木事務所、本庁用地指導課、収用委員会事務局、本庁で二〇年間現場指導を行い、定年後は補償コンサルタント業(株)中部テックで損失補償現場の相談をお受けし、平成一三年から一期収用委員を拝命して貴重な経験をしてきました。
また、大場民男弁護士が編集代表をされている新日本法規出版の書籍(「問答式 用地取得・補償の法律実務」一九九一・四出版)の執筆のお手伝いを始めておよそ三〇年になります。この経験も私の公共用地取得一筋で過ごしてきた素晴らしい体験となっています。
私が補償基準の企画・指導担当になったのは一九七〇年代のことです。当時は地方自治体でも社会福祉の標榜が始まっていた頃で、シビルミニマムという言葉が盛んに言われていました。損失補償においては、相当補償説と完全補償説が対立した一九七三年の「倉吉都市計画」を巡って、最高裁で完全補償説が確立しています。
学説でも、華山謙東京工大教授による、ダム水没者の生活再建、起業地周辺に居住する人々への悪影響、事業施行による被害者と受益地の住民の格差などへの対応が問題提起されていました。高原賢治東京教育大教授による「小さな財産権」と「大きな財産権」の区分による損失補償の在り方への問題提起もありました。
その中でも、渡辺洋三東京大教授による主張は、損失補償は「人権としての財産」には財産権の補償に加えて生存権保障を取り入れた補償を行うべきであり、「人権でない財産」には純粋に財産価値のみ補償すればよいとした学説で、以後の私の小さな信条にも大きな影響を与えてくれたものでした。
この頃は、正に百家争鳴のごとくいろいろな学者や実務者から個性豊かな主張があり、それらの著作を懸命に勉強したことを懐かしく思い出しています。
この他にも用地職員として担当した事案は、いろいろ思い出されます。特に、私がこれほど長く用地取得という同一事務を担当した要因の一つである、愛知県刈谷市に立地した「境川流域下水道」の収用事件は印象深く残っております。私は、この事務に一〇年間従事しました。当時は、反権力闘争ともいわれた「成田空港三里塚収用事件」の余韻が続いていたころで、その前にあった「松原・下筌ダム収用事件」と共に、三大収用事件の一つとも言われていた事件でした。
土地所有者の団体、刈谷市民、名古屋市職員などからなる反対三団体を相手に、任意交渉、収用法適用、最後には反対三団体による団結小屋の撤去に機動隊による一〇〇余名の強制排除などの行政代執行事務がありました。そして、一九八一年に収用裁決取消訴訟が提起されて以降は、一九九三年二月に名古屋地裁判決勝訴、二〇〇二年四月最高裁勝訴まで続きました(そういえば収用裁決申請を行ったときは、大場民男先生が収用委員に就任されていました。)。
この時、土地所有者の反対理由は主に二つありました。一つは、終末処理場の位置が地元の意向も聞かず、当時の選良たちの思惑で決められたこと。その二は、この事業予定地は第二次世界大戦後の食糧増産のために干拓地を埋め立てした造成土地で、事業決定された頃までに海水の塩抜きなどが行われてようやく収穫が上がってきた美田で、自分たち居住地の至近距離にあり、正に生業そのものであることを挙げていました。
2 用地取得担当職員の職務
公共事業は、基本的には事業に必要な土地の取得から始まります。もちろん、その構想・企画段階では地域社会の共同参画があって公共事業は行われるのですが、用地取得をされて生活の本拠地を移転しなければならない者、生業の基本である農地などの買収により生業の変更をしなければならない者等は、いわば一種の「犠牲者」と捉えることもできます。このような人々の言い分を丁寧に聞き、移転後の生活再建の方策の相談に乗りながら、用地取得の必要性を納得してもらう。これを遂行する用地取得担当者の作業は、大変な労苦を伴います。
もともとこれらの人々の日常生活なり生業を全て金銭に換算して金額を提示し、納得を得ることが用地取得の作業で、資本主義の世界では仕方がないことではありましょうが、正に「夜討ち朝駆け」で当事者の全人格をかけたものとなります。
3 用地取得を困難にしている一般社会に存在する制度の仕組み
用地職員に求められる資質は、これだけではありません。一般社会には、土地所有の仕方にもいろいろな法制度や地域の仕組みが存在していますので、これらを丁寧に解きほぐしていかなければなりません。
例えば、「ため池を歩道設置のために少し用地買収する」とします。ため池が存する地域は歩道設置事業には大賛成ですが、ため池の所有者は、その設置は下流部の灌漑用のもので、その所有の形態も様々(単独所有、ため池の受益者全員の共有、受益地の地域の所有、地方公共団体所有、受益地の所有者の総有など)であったりしますので、この説得作業は多くの時間と労力を要することになります。これらの所有を示す不動産登記記録も共有総代、部落有、多数人名義など、多種多様です。
また墓地の場合も、古い施設であれば墓地管理者がないままの地域の総有であったり、町村合併前のある地域に居住している者のみに墓地使用を認めていたりする場合があったりします。
名古屋の周辺では、第二次世界大戦で被災した人たちが河川の堤防敷地を利用して(いわば無断占用)家を築造して居住しているケースがあちらこちらにみられますが、これらの者に対してどのような損失補償が行い得るのか、誠に難問というべきです。
最近では、日本に居住して長い年月を重ねた後、亡くなる外国人土地所有者の相続問題に遭遇することがあります。また外国へ移住する日本人が増加していますが、このような方々への用地交渉を行うには、まず住所から見つけなければなりません。また、居住先は見つかったものの、用地取得契約の方法、はたまた代金の支払い方法、租税特別措置法上の取扱いはどうするのかなど、解決すべき問題がいくつもあります。
このような事例に遭遇した用地取得担当は、正に途方に暮れてしまいます。こうした事例は、過去に担当した「職員の知恵」として残っていますが、残念ながらこれらを収録した図書はほとんどなく、埋もれてしまっています。つまり、公共用地取得の現場に、「過去の経験(知恵)」がなかなか生かされていないのが実情です。
最近は、職員も担当する事務が三〜五年程度で変わることが多くなっていますし、行政機関のスリム化や経験豊富
な団塊の世代の大量定年などもあり、公共用地取得担当職員数の減少もこれらの実情の悪化に拍車をかけているように思われます。このため、せっかく関係法規の勉強や制度の理解をして事案処理を蓄積をしても、その蓄積が次に生かされようがないことになってしまいます。
4 発刊の喜び
そのような中、二〇一七年五月に用地取得実務をテーマにした本を編集し、出版しました(「困難事例にみる 用地取得・損失補償の実務」新日本法規出版)。私にとって、人生の掉尾を飾る快挙でした。齢八〇歳にして、私の名前を冠した本が出版されましたことを心から喜んでいます。
先ずは、新日本法規出版(株)の関係者の皆様にお礼を申し上げます。二〇一五年の暮れでしたか、この図書の構想についてお聞きし、編集・執筆の協力を依頼されました。素敵な企画であり、協力は惜しまないことを約束しました。
その後、執筆者の人選と執筆協力依頼、過去の実務経験で一筋縄ではいかなかった困難事例のリストアップに着手し、二〇一六年六月に執筆者を集めての編集会議を経て、いよいよ執筆が始まりました。執筆者は、私を含めて用地職員のOB五名、現役の用地職員五名の計一〇名で、用地職員のベテランがそれぞれの経験を改めて整理し、原稿を執筆していきました。原稿は、同年一〇月が締切期限でした。
各執筆者から提出された原稿の校正は、まずは私が一次校正、ついで出版社の校正担当へ依頼し、概ね締め切り期限には原稿がまとまりました。この校正段階で、新日本法規出版の校正担当のその緻密で行き届いた校正に驚嘆したのを思い出しています。印刷用の確認原稿(ゲラ刷り)が私の手元に届いたのは、二〇一七年二月中旬、その校閲締め切りは三月中旬という予定でした。
ところが、ここでアクシデントが発生しました。私が三月初めに肺炎を患ってしまったのです。治療のため二か月間入院してしまい、出版社の担当者と共同執筆者の佐藤弘俊さんに病院まで校閲の打ち合わせに来ていただき、ご迷惑をお掛けしました。今思いますと、私は肺炎の苦しさを、校閲作業を行うことで紛らし、結果的には救われました。改めてお許しをいただきたいと思います。
そして五月に無事出版することができ、本の出来あいの良さとその重さに感激でした。
私が用地取得の現場で様々な経験をしてきたように、次世代の用地職員にも難しい局面が訪れることがあるでしょう。この拙著が、日々用地取得の現場で苦労している用地職員のほんの少しでも手助けになり、その公共事業が一日も早く完成することができれば、こんな嬉しいことはありません。
(総合補償士)
人気記事
人気商品
法苑 全111記事
- 裁判官からみた「良い弁護士」(法苑200号)
- 「継続は力、一生勉強」 という言葉は、私の宝である(法苑200号)
- 増加する空き地・空き家の課題
〜バランスよい不動産の利活用を目指して〜(法苑200号) - 街の獣医師さん(法苑200号)
- 「法苑」と「不易流行」(法苑200号)
- 人口減少社会の到来を食い止める(法苑199号)
- 原子力損害賠償紛争解決センターの軌跡と我が使命(法苑199号)
- 環境カウンセラーの仕事(法苑199号)
- 東京再会一万五千日=山手線沿線定点撮影の記録=(法苑199号)
- 市長としての14年(法苑198号)
- 国際サッカー連盟の サッカー紛争解決室について ― FIFAのDRCについて ―(法苑198号)
- 昨今の自然災害に思う(法苑198号)
- 形式は事物に存在を与える〈Forma dat esse rei.〉(法苑198号)
- 若輩者の矜持(法苑197号)
- 事業承継における弁護士への期待の高まり(法苑197号)
- 大学では今─問われる学校法人のガバナンス(法苑197号)
- 和解についての雑感(法苑197号)
- ある失敗(法苑196号)
- デジタル奮戦記(法苑196号)
- ある税務相談の回答例(法苑196号)
- 「ユマニスム」について(法苑196号)
- 「キャリア権」法制化の提言~日本のより良き未来のために(法苑195号)
- YES!お姐様!(法苑195号)
- ハロウィンには「アケオメ」と言おう!(法苑195号)
- テレビのない生活(法苑195号)
- 仕事(法苑194号)
- デジタル化(主に押印廃止・対面規制の見直し)が許認可業務に与える影響(法苑194号)
- 新型コロナウイルスとワクチン予防接種(法苑194号)
- 男もつらいよ(法苑194号)
- すしと天ぷら(法苑193号)
- きみちゃんの像(法苑193号)
- 料理を注文するー意思決定支援ということ(法苑193号)
- 趣味って何なの?-手段の目的化(法苑193号)
- MS建造又は購入に伴う資金融資とその担保手法について(法苑192号)
- ぶどうから作られるお酒の話(法苑192号)
- 産業医…?(法苑192号)
- 音楽紀行(法苑192号)
- 吾輩はプラグマティストである。(法苑191号)
- 新型コロナウイルス感染症の渦中にて思うこと~流行直後の対応備忘録~(法苑191号)
- WEB会議システムを利用して(法苑191号)
- 交通事故に基づく損害賠償実務と民法、民事執行法、自賠責支払基準改正(法苑191号)
- 畑に一番近い弁護士を目指す(法苑190号)
- 親の子供いじめに対する様々な法的措置(法苑190号)
- 「高座」回顧録(法苑190号)
- 知って得する印紙税の豆知識(法苑189号)
- ベトナム(ハノイ)へ、32期同期会遠征!(法苑189号)
- 相続税の申告業務(法苑189号)
- 人工知能は法律家を駆逐するか?(法苑189号)
- 土地家屋調査士会の業務と調査士会ADRの勧め(法苑189号)
- 「良い倒産」と「悪い倒産」(法苑188号)
- 民事訴訟の三本の矢(法苑188号)
- 那覇地方裁判所周辺のグルメ情報(法苑188号)
- 「契約自由の原則」雑感(法苑188号)
- 弁護士と委員会活動(法苑187号)
- 医療法改正に伴う医療機関の広告規制に関するアウトライン(法苑187号)
- 私の中のBangkok(法苑187号)
- 性能規定と建築基準法(法苑187号)
- 境界にまつわる話あれこれ(法苑186号)
- 弁護士の報酬を巡る紛争(法苑186号)
- 再び大学を卒業して(法苑186号)
- 遺言検索システムについて (法苑186号)
- 会派は弁護士のための生きた学校である(法苑185号)
- 釣りキチ弁護士の釣り連れ草(法苑185号)
- 最近の商業登記法令の改正による渉外商業登記実務への影響(法苑185号)
- 代言人寺村富榮と北洲舎(法苑185号)
- 次世代の用地職員への贈り物(法苑184号)
- 大学では今(法苑184号)
- これは必見!『否定と肯定』から何を学ぶ?(法苑184号)
- 正確でわかりやすい法律を国民に届けるために(法苑184号)
- 大阪地裁高裁味巡り(法苑183号)
- 仮想通貨あれこれ(法苑183号)
- 映画プロデューサー(法苑183号)
- 六法はフリックする時代に。(法苑183号)
- 執筆テーマは「自由」である。(法苑182号)
- 「どっちのコート?」(法苑182号)
- ポプラ?それとも…(法苑182号)
- 「厄年」からの肉体改造(法苑181号)
- 「現場仕事」の思い出(法苑181号)
- 司法修習と研究(法苑181号)
- 区画整理用語辞典、韓国憲法裁判所の大統領罷免決定時の韓国旅行(法苑181号)
- ペットの殺処分がゼロの国はあるのか(法苑180号)
- 料理番は楽し(法苑180号)
- ネット上の権利侵害の回復のこれまでと現在(法苑180号)
- 検事から弁護士へ― 一六年経って(法苑180号)
- マイナンバー雑感(法苑179号)
- 経験から得られる知恵(法苑179号)
- 弁護士・弁護士会の被災者支援―熊本地震に関して―(法苑179号)
- 司法試験の関連判例を学習することの意義(法苑179号)
- 「スポーツ文化」と法律家の果たす役割(法苑178号)
- 「あまのじゃく」雑考(法苑178号)
- 「裁判」という劇薬(法苑178号)
- 大学に戻って考えたこと(法苑178号)
- 生きがいを生み出す「社会システム化」の創新(法苑177号)
- 不惑のチャレンジ(法苑177号)
- タイ・世界遺産を訪ねて(法苑177号)
- 建築の品質確保と建築基準法(法苑177号)
- マイナンバー制度と税理士業務 (法苑176号)
- 夕べは秋と・・・(法苑176号)
- 家事調停への要望-調停委員の意識改革 (法苑176号)
- 「もしもピアノが弾けたなら」(法苑176号)
- 『江戸時代(揺籃期・明暦の大火前後)の幕府と江戸町民の葛藤』(法苑175号)
- 二度の心臓手術(法苑175号)
- 囲碁雑感(法苑175号)
- 法律学に学んだこと~大学時代の講義の思い出~(法苑175号)
- 四半世紀を超えた「渉外司法書士協会」(法苑174号)
- 国際人権条約と個人通報制度(法苑174号)
- 労働基準法第10章寄宿舎規定から ディーセント・ワークへの一考察(法苑174号)
- チーム・デンケン(法苑174号)
- 仕事帰りの居酒屋で思う。(健康が一番の財産)(法苑173号)
- 『フリー・シティズンシップ・クラス(Free Citizenship Class)について』(法苑173号)
- 法律という窓からのながめ(法苑173号)
最近閲覧した記事
-

-

団体向け研修会開催を
ご検討の方へ弁護士会、税理士会、法人会ほか団体の研修会をご検討の際は、是非、新日本法規にご相談ください。講師をはじめ、事業に合わせて最適な研修会を企画・提案いたします。
研修会開催支援サービス -

Copyright (C) 2019
SHINNIPPON-HOKI PUBLISHING CO.,LTD.