一般2021年09月22日 仕事(法苑194号) 法苑 執筆者:佐々木聡史
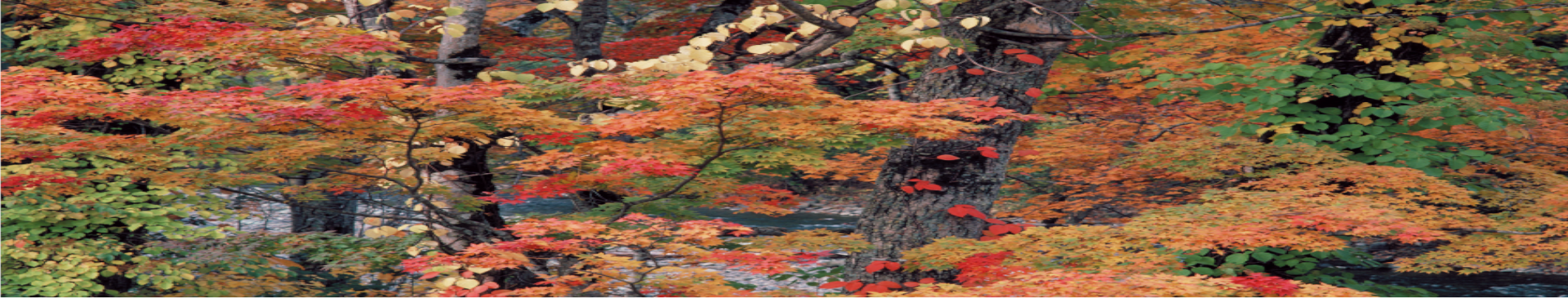
二八歳で司法書士事務所を開業し、四四歳となった。
脱サラし、業界未経験のまま、見知らぬ所で開業した。大げさだが、小舟で海へ漕ぎ出した気持ちだった。今も何も見えてはいないが、自営業は性に合っているということだけが頼りである。
まだまだ新人のつもりであり、自分の人生を振り返るほどでもないが、法苑の執筆をさせていただく機会をいただき、少し現在地を確認してみた。
●幼いころの記憶
母方の祖父母は専業農家で、祖父は農業委員や地域の世話役をしたりして、農作物のことはもちろんのこと、社会的なことも良く知っていた。また、兵士として戦争体験者であり、私が小学生の頃に過酷な戦場での話を聞かせてくれたりもした。たまに「じーちゃんがな、鉄砲でバーンと撃って戦車をやっつけたんじゃ」とか(今思えば、多分嘘。)武勇伝も聞いた。
父方の祖父母は田舎の自営業者で、昔の景気が良かった時の話を聞くと驚くばかりであり、宵越しの金は持たないような商売人であった。祖父母の家に遊びに行くと、店にくる客とのやり取りを見ることがあり、適当にしているようで、気配りがあり、自然な立ち居振る舞いであったのを記憶している。また、母方の祖父と同様に兵士として当時の満州国で戦争を体験していたことから、教科書にはない戦争の話を聞くことができた。
小学生の頃は、祖父母からは教えられることばかりであり、祖父母というのは、どこの家でも農家や自営業者ばかりで戦争体験者であると思っていた。幼いころは、極めて狭い社会で生活し、その見える社会がすべてであり、そこから大きな影響を受けるものだと思う。
●学び、知る環境
私の父は大学を卒業して公務員となり、母は専業主婦であった。父母から何かを教わったような感覚は薄いが、大学に行かせてもらい、今の仕事ができているということは、父母から様々なものを与えてもらい、学んだからだと思う。日常的に与えられているものというのは、なかなかに実感しないが、自然に目に入り、感じることは、将来に大きな影響を与えるものだと今になって気付いた。
私は、大学卒業後、地元の小さな会社に就職した。サラリーマン時代は実家暮らしで、当時は父もまだ現役で働いていたが、私の仕事が昼から夜遅くにかけての仕事であったことから、仕事について話をすることは少なかったように思う。
その後、脱サラし、司法書士になった。
親族、友人には、所謂士業は一人もいなかったし、仕事上で司法書士と付き合いがあるような人もいなかった。
高校の時からによく行く地元の理髪店の主人は、「司書の仕事どうや?」
(略して言っているのか、職業自体を間違えているのか不明。)
母は、「弁理士の仕事面白い?」
(多分、「弁護士」と違う方という認識。)
従兄は「代書屋さんな、どうや?」
(それほど間違えてはいない。)
このあたりの問いかけについては、職業を正しく伝えることに加え、仕事の内容を説明してから、現在の状態を述べることになるので、話の流れ上、概ね「ぼちぼちやね」と流れに身を任せることになり、その結果特に支障がない。
司法書士の仕事がわかり、話が盛り上がるような場合は、既に司法書士の業務について相談がある場合であり、一般的には日常生活でそれほど司法書士に依頼するようなことが頻繁にあるわけではない。
現に、母はしばらく私のことを何士かわかっていなかったが、親族の相続手続があったころから、「司法書士」となった。
父は、公務員であったことから、どうやらある程度のことはわかるようで、それほどまとはずれなことは言わないが、息子が司法書士だからと言って、それについて詳しいわけではない。興味があるのは、もっぱらゴルフと囲碁である。
●専門家との距離
最近では、「相続」に関係することがスポットライトを浴びることが多くなり、そのような仕事も増えてきたように思う。司法書士にとって、相続に関する業務は日常的なものである。特に相続登記については、絶えず依頼がある状態であり、その他家庭裁判所に提出する書類の作成や相続による預金の払戻しの代行等に関連して、毎日、事務所内の誰かは依頼に関係する戸籍を見ているような状態である。
司法書士界では、長期相続登記等未了土地、空き家、所有者不明土地等の問題に取り組み、行政機関と連携したり、相談会で対応したりしている。
相続手続といえば、「司法書士」と言われたい。
ポツンと一軒家での生活がテレビで流れたりしているが、そこまでいかないにしても、似たようなことはよく耳にする。知人との話の中でも田舎の実家の空き家の話があったりするが、「あれど~なった?」と聞いたりすると、
「あ~あれな、あんなもん引き受けたらたまらんで、『俺はいらんで相続放棄する。』って兄貴にゆ~といたから(言っておいたから)、え~んや(問題ない)。」
とのこと。
ご存知のとおり、相続放棄とは、家庭裁判所に書類を提出して行うものであり、「相続放棄する」と言えばそうなるものではないし、「兄貴にゆ~たら」何とかなるものでもない。
「引き受けたらたまらん」のであれば、家庭裁判所で相続放棄をすべきであり、裁判手続まではハードルが高いとしても、相続人全員で遺産分割協議をして、誰かが引き受けることとし、相続登記まで完了させてこそ問題は解決される。
まだまだ問題の発生地点から専門家までの距離があると感じる。
●当事者と専門家の立場
私には、兄があり、父母と同居をしてくれている。
三年ほど前に、父が「遺言でもしとこうか・・・」と言ったことがあった。それは、司法書士としての私に言ったのか、それとも単に自分の子どもである私に言ったのかわからなかった。「遺言しようと思うが、相談にのってほしい」だったのか?
父親から見ると、いくつになっても子どもは子どもなのだろうと思う。父親から相談されることなど今までなかったし、私自身も父親に私が何かアドバイスをするなどということは考えもしていなかった。
日頃、遺言書作成の相談を聞いたり、公正証書遺言作成時の証人になったり、遺言書を使った相続登記の依頼を受けたりしており、遺言については日常業務であると言える。遺言書の作成を迷っている人がいれば、ほどよくアドバイスできていると自負している。
ところが、いざ自分の父親から遺言について切り出された時には、歯切れが悪い答えしかできなかった。正直何を話したか覚えていない。
父の年齢から考えれば、当然に遺言を考えてもおかしくないし、昨今の遺言書作成ブームを見れば、自然な発言だったはず。
一般的には、人生の中で遺言を含めた相続について、当事者となることは数えるほどしかない。私は当事者としては未経験であり、正にこの時、当事者となることの不意打ちを食らったのである。
兄とはここ数年ほとんど会っていないが、話ができない仲ではないし、兄は良い意味で兄らしく振舞おうとするところがあるので、相続において、私たち兄弟がもめることは考えられないし、相続をすること自体を考えたことがない。いや、自分には相続が起こらないとすら思っているのではないか。そんなことだから、父の「遺言でもしとこうか・・・」が完全な不意打ちとなったのかもしれない。
私が勝手にもめないと思っているだけで、相手方はそう思っていないかもしれない。勝手に警戒されてもたまったものではないから、やっぱり遺言をしておいてもらおうか、しかも兄から変に疑われない様に、私以外の別の専門家に相談してもらって。
でも今更、こちらからそのことを切り出すのは、不自然だし、時には、「遺言は家族の誰かに言われてやるようなことではない。」とかわかったようなことを言ったりしている身でもある。
父からは、それ以降は一度も遺言の話は出ていない。相談もない。
大人になったことを噛みしめる機会を逃したと思う。
しかし、「まあ、うちは大丈夫。」と本当に思っている。
まがりなりにも専門家と称している自分がこんなのであるのなら、事務所に相談に来る人は、なおさらであることを再認識しなければならない。
●現在
「なあ、パパ司法書士なんやってな!」
先日、小学生の子どもが突然私の職業を確認するように話しかけてきた。
「ちがうで。」
と私は突然切り返した。実は、子どもには自分の職業についてほとんど話をしていない。親の職業に興味を持ってもらえるのはうれしいことだが、自分の職業のことについて、子どもに話をすると、将来の選択肢を狭めてしまうのではないかと思うからである。
考えすぎかもしれないが、子どもの頃に感じたことは将来に大きな影響を及ぼす可能性は大きいと思っている。
子どもからの問いが続く。
「司法書士なんやろ!?」
どうやら誰かに聞いたようで、確信があり、興味があるようだ。
取調べってこんな感じかな?
しかし、かわいい。小学生で「司法書士」という単語を発した子がどれほどいるだろうか。
私が「司法書士」を知ったのは、大学生の時だった。
私は話をうまく逸らした。YouTubeをネタにすれば、子どもの興味を逸らすことなどたやすい。だが、子どもが「司法書士」が何者であるか、私が何者であるかを知るのは時間の問題だろう。何と言ってもこのインターネット社会である。スマホに話しかければ大抵のことは解決できる。
子どもに知られて、恥ずかしくない仕事をしようと急に思う。
うちの子は、他の子に比べて司法書士との距離が近くなりそうだ。少し安心する反面、不安も感じる。自分の身に何かの問題が降りかかった時は、専門家に相談するという選択肢を忘れないでほしいが、そんな専門家である父ばかりを見てほしくはない。
我々が小学生の頃より、今の小学生は、もっと広い社会が見える環境にある。情報が伝わる速さは比べものにならない。公衆電話に並んで数字を打った時代と比べられるわけがない。
私の子どもが土地を買う時には、私が手続をするのだろうか?
(司法書士)
人気記事
人気商品
法苑 全111記事
- 裁判官からみた「良い弁護士」(法苑200号)
- 「継続は力、一生勉強」 という言葉は、私の宝である(法苑200号)
- 増加する空き地・空き家の課題
〜バランスよい不動産の利活用を目指して〜(法苑200号) - 街の獣医師さん(法苑200号)
- 「法苑」と「不易流行」(法苑200号)
- 人口減少社会の到来を食い止める(法苑199号)
- 原子力損害賠償紛争解決センターの軌跡と我が使命(法苑199号)
- 環境カウンセラーの仕事(法苑199号)
- 東京再会一万五千日=山手線沿線定点撮影の記録=(法苑199号)
- 市長としての14年(法苑198号)
- 国際サッカー連盟の サッカー紛争解決室について ― FIFAのDRCについて ―(法苑198号)
- 昨今の自然災害に思う(法苑198号)
- 形式は事物に存在を与える〈Forma dat esse rei.〉(法苑198号)
- 若輩者の矜持(法苑197号)
- 事業承継における弁護士への期待の高まり(法苑197号)
- 大学では今─問われる学校法人のガバナンス(法苑197号)
- 和解についての雑感(法苑197号)
- ある失敗(法苑196号)
- デジタル奮戦記(法苑196号)
- ある税務相談の回答例(法苑196号)
- 「ユマニスム」について(法苑196号)
- 「キャリア権」法制化の提言~日本のより良き未来のために(法苑195号)
- YES!お姐様!(法苑195号)
- ハロウィンには「アケオメ」と言おう!(法苑195号)
- テレビのない生活(法苑195号)
- 仕事(法苑194号)
- デジタル化(主に押印廃止・対面規制の見直し)が許認可業務に与える影響(法苑194号)
- 新型コロナウイルスとワクチン予防接種(法苑194号)
- 男もつらいよ(法苑194号)
- すしと天ぷら(法苑193号)
- きみちゃんの像(法苑193号)
- 料理を注文するー意思決定支援ということ(法苑193号)
- 趣味って何なの?-手段の目的化(法苑193号)
- MS建造又は購入に伴う資金融資とその担保手法について(法苑192号)
- ぶどうから作られるお酒の話(法苑192号)
- 産業医…?(法苑192号)
- 音楽紀行(法苑192号)
- 吾輩はプラグマティストである。(法苑191号)
- 新型コロナウイルス感染症の渦中にて思うこと~流行直後の対応備忘録~(法苑191号)
- WEB会議システムを利用して(法苑191号)
- 交通事故に基づく損害賠償実務と民法、民事執行法、自賠責支払基準改正(法苑191号)
- 畑に一番近い弁護士を目指す(法苑190号)
- 親の子供いじめに対する様々な法的措置(法苑190号)
- 「高座」回顧録(法苑190号)
- 知って得する印紙税の豆知識(法苑189号)
- ベトナム(ハノイ)へ、32期同期会遠征!(法苑189号)
- 相続税の申告業務(法苑189号)
- 人工知能は法律家を駆逐するか?(法苑189号)
- 土地家屋調査士会の業務と調査士会ADRの勧め(法苑189号)
- 「良い倒産」と「悪い倒産」(法苑188号)
- 民事訴訟の三本の矢(法苑188号)
- 那覇地方裁判所周辺のグルメ情報(法苑188号)
- 「契約自由の原則」雑感(法苑188号)
- 弁護士と委員会活動(法苑187号)
- 医療法改正に伴う医療機関の広告規制に関するアウトライン(法苑187号)
- 私の中のBangkok(法苑187号)
- 性能規定と建築基準法(法苑187号)
- 境界にまつわる話あれこれ(法苑186号)
- 弁護士の報酬を巡る紛争(法苑186号)
- 再び大学を卒業して(法苑186号)
- 遺言検索システムについて (法苑186号)
- 会派は弁護士のための生きた学校である(法苑185号)
- 釣りキチ弁護士の釣り連れ草(法苑185号)
- 最近の商業登記法令の改正による渉外商業登記実務への影響(法苑185号)
- 代言人寺村富榮と北洲舎(法苑185号)
- 次世代の用地職員への贈り物(法苑184号)
- 大学では今(法苑184号)
- これは必見!『否定と肯定』から何を学ぶ?(法苑184号)
- 正確でわかりやすい法律を国民に届けるために(法苑184号)
- 大阪地裁高裁味巡り(法苑183号)
- 仮想通貨あれこれ(法苑183号)
- 映画プロデューサー(法苑183号)
- 六法はフリックする時代に。(法苑183号)
- 執筆テーマは「自由」である。(法苑182号)
- 「どっちのコート?」(法苑182号)
- ポプラ?それとも…(法苑182号)
- 「厄年」からの肉体改造(法苑181号)
- 「現場仕事」の思い出(法苑181号)
- 司法修習と研究(法苑181号)
- 区画整理用語辞典、韓国憲法裁判所の大統領罷免決定時の韓国旅行(法苑181号)
- ペットの殺処分がゼロの国はあるのか(法苑180号)
- 料理番は楽し(法苑180号)
- ネット上の権利侵害の回復のこれまでと現在(法苑180号)
- 検事から弁護士へ― 一六年経って(法苑180号)
- マイナンバー雑感(法苑179号)
- 経験から得られる知恵(法苑179号)
- 弁護士・弁護士会の被災者支援―熊本地震に関して―(法苑179号)
- 司法試験の関連判例を学習することの意義(法苑179号)
- 「スポーツ文化」と法律家の果たす役割(法苑178号)
- 「あまのじゃく」雑考(法苑178号)
- 「裁判」という劇薬(法苑178号)
- 大学に戻って考えたこと(法苑178号)
- 生きがいを生み出す「社会システム化」の創新(法苑177号)
- 不惑のチャレンジ(法苑177号)
- タイ・世界遺産を訪ねて(法苑177号)
- 建築の品質確保と建築基準法(法苑177号)
- マイナンバー制度と税理士業務 (法苑176号)
- 夕べは秋と・・・(法苑176号)
- 家事調停への要望-調停委員の意識改革 (法苑176号)
- 「もしもピアノが弾けたなら」(法苑176号)
- 『江戸時代(揺籃期・明暦の大火前後)の幕府と江戸町民の葛藤』(法苑175号)
- 二度の心臓手術(法苑175号)
- 囲碁雑感(法苑175号)
- 法律学に学んだこと~大学時代の講義の思い出~(法苑175号)
- 四半世紀を超えた「渉外司法書士協会」(法苑174号)
- 国際人権条約と個人通報制度(法苑174号)
- 労働基準法第10章寄宿舎規定から ディーセント・ワークへの一考察(法苑174号)
- チーム・デンケン(法苑174号)
- 仕事帰りの居酒屋で思う。(健康が一番の財産)(法苑173号)
- 『フリー・シティズンシップ・クラス(Free Citizenship Class)について』(法苑173号)
- 法律という窓からのながめ(法苑173号)
-

-

団体向け研修会開催を
ご検討の方へ弁護士会、税理士会、法人会ほか団体の研修会をご検討の際は、是非、新日本法規にご相談ください。講師をはじめ、事業に合わせて最適な研修会を企画・提案いたします。
研修会開催支援サービス -

Copyright (C) 2019
SHINNIPPON-HOKI PUBLISHING CO.,LTD.





















